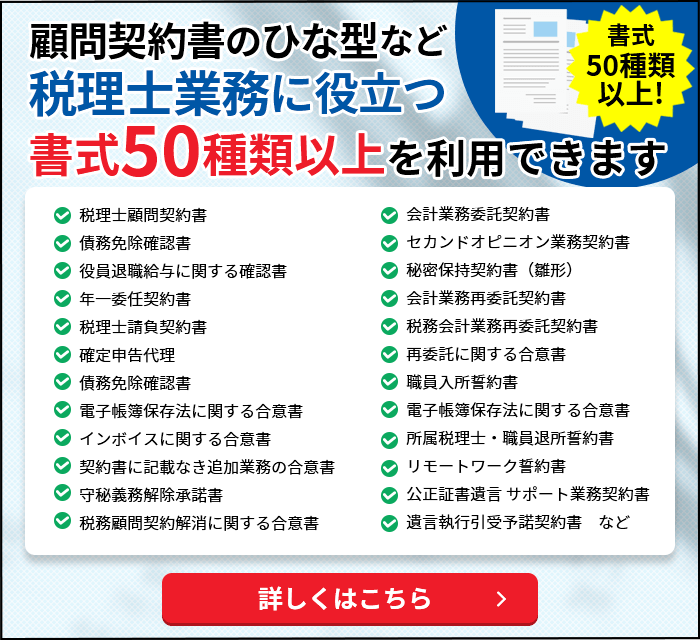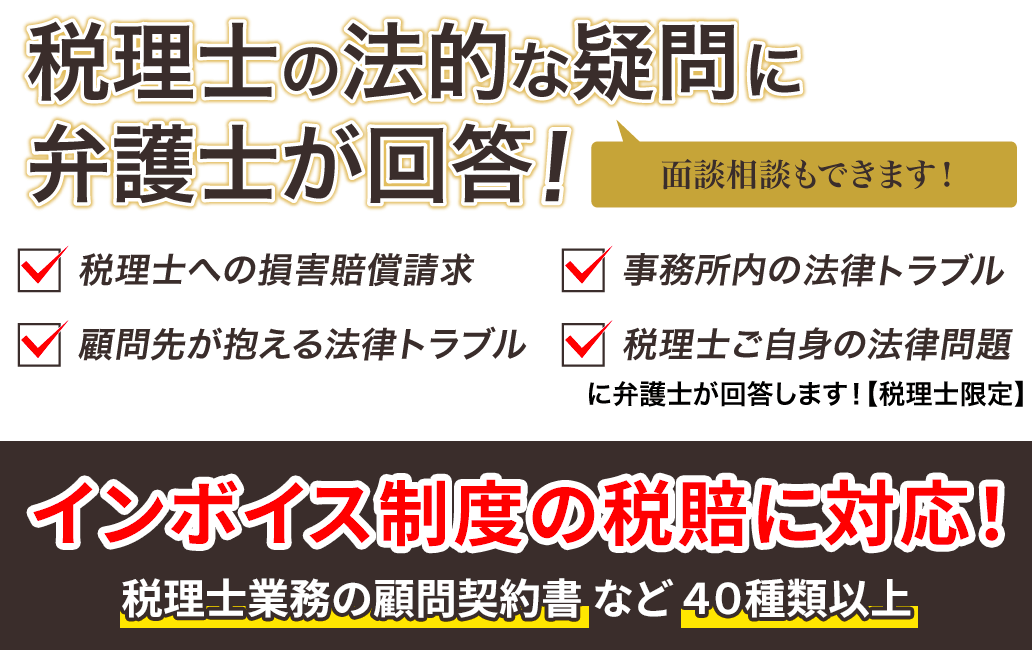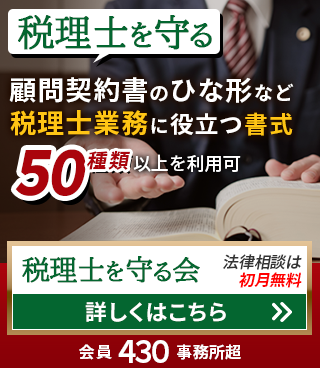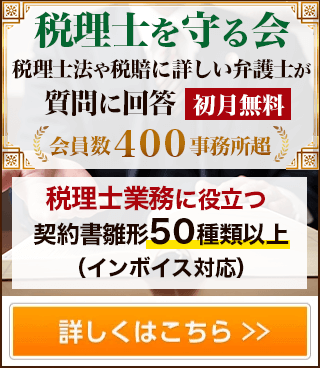今回は、重加算税について積極的行為がない場合に関する最高裁判例について解説をしていきます。
参考書籍としては、私が執筆した『税務のわかる弁護士が教える 税務調査における重加算税の回避ポイント』(ぎょうせい)も参考にしていただければと思います。
【重加算税賦課要件(過少申告)】
重加算税賦課要件の過少申告に関しての条文は、国税通則法第68条1項に規定しています。
①過少申告加算税の規定に該当する場合において、
②納税者が
③その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、
④隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた
このような場合に重加算税が付加されます。
今回は、③の「隠蔽し、又は仮装し」の部分について見ていきます。
国税庁の見解としては、内部文書である「課税処分に当たっての留意点」(平成25年4月 大阪国税局)というものが出ており、名古屋地裁の判決の定義を引用しています。
「『隠蔽』とは、課税標準等又は税額の計算の基礎となる事実について、これを隠蔽し、あるいは故意に脱漏することをいい、また『仮装』とは、財産あるいは取引上の名義等に関し、あたかも、それが真実であるかのように装う等、故意に事実を歪曲することをいう(名古屋地裁昭和55年10月13日判決)」
隠したり、脱漏したり、故意に事実を歪曲したり、ということを「隠蔽・仮装」としています。
多くの場合には、不正経理や二重帳簿等の積極的な行為があるのですが、では積極的な行為がない場合の成立要件とは、どういったものなのでしょうか。
(「つまみ申告」については、また別の機会に解説します)
今回は、最高裁の次の判例から考えていきます。
「最高裁平成7年4月28日判決(民集49巻4号1193頁 TAINS Z209-7518)」
1.事案の概要(積極的行為がない場合)
Xには、株式等の売買により、昭和60年に2600万円余、同61年に1億0800万円余、同62年に2億1000万円余の所得があった。
右売買の回数及び株数は、いずれの年分についても、有価証券の譲渡による所得のうち継続的取引から生ずる所得として、所得税法及び所得税法施行令が非課税所得から除外する所得の要件を満たしていた。2.Xは、昭和60年分、同61年分及び同62年分の所得税について、課税庁に確定申告をしたが、上記1の売買による所得を雑所得として申告すべきであるのに、これを申告書に全く記載しなかった。
しかし、Xは、右売買について、取引の名義を架空にしたり、その資金の出納のために隠れた預金口座を設けたりするようなことはしなかった。3.Xは、右売買による所得を雑所得として申告し、納税するつもりがなく、その計算すらしていなかった。
そして、Xは、右各年分の確定申告書の作成を顧問税理士に依頼した際に、その都度、Xが株式等の売買をしていることを知っていた同税理士から、株式の取引による所得についても課税要件を満たしていれば申告が必要であると何度も念を押され、右所得の有無について質問を受け、資料の提示を求められたにもかかわらず、確定的な脱税の意思に基づいて、同税理士に対し、課税要件を満たす所得はない旨を答え、他の所得に関する資料を交付しながら、株式等の取引に関する資料を全く示さなかった。4.そこで、課税庁は、Xに対し、重加算税の賦課決定処分をした。
積極的な隠蔽・仮装行為はなかった、という事情ですが、この事案において、最高裁判例はどう判断したのでしょうか。
まずは、重加算税の賦課要件について提示しています。
(1)重加算税を課するためには、納税者のした過少申告行為そのものが隠蔽、仮装に当たるというだけでは足りず、過少申告行為そのものとは別に、隠蔽、仮装と評価すべき行為が存在し、これに合わせた過少申告がされたことを要する。
(2)架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまで必要であると解するのは相当でない。
(3)納税者が、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合には、重加算税の右賦課要件が満たされる。
先生方も、この部分を読まれたことがあるかと思いますが、それはこの最高裁判決からきています。
さて、上記規範を提示した上で最高裁は事実に入っていきます。
(ア)Xは、3箇年にわたって、株式等の売買による前記多額の雑所得を申告すべきことを熟知しながら、あえて申告書にこれを全く記載しなかった。
(イ)顧問税理士から、その都度、同売買による所得の有無について質問を受け、資料の提出も求められたにもかかわらず、確定的な脱税の意思に基づいて、右所得のあることを同税理士に対して秘匿し、何らの資料も提供することなく、同税理士に過少な申告を記載した確定申告書を作成させ、これを課税庁に提出した。
従って、これは上記(3)の、「当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上」で、その意図に基づく過少申告をしたのだ、と判断したということです。
そして、顧問税理士から聞かれて、確定的な脱税意志に基づいて嘘を言った、秘匿したということは、当初から外部からうかがい得る特段の行動なのだ、という認定ということになります。
これは、なかなかわかりにくい部分のため、「当初からの意図を外部からもうかがい得る特段の行動」の具体的な例を最高裁の判例解説から見てみます。
「最高裁判所判例解説民事篇平成7年度(上)482頁」
・多額の所得があったにもかかわらず、これをゼロとし、あるいはそのごく一部だけを作為的に記載した申告書を提出し続けた場合。
・そのような所得を得た納税者が通常であれば保管しておくと考えられる原資資料をあえて散逸するにまかせていた場合。
・税務調査に対する非協力、虚偽答弁、虚偽資料の提出等の態度を採った場合。
これだけでは重加算税にはならないのでが、これも一つの事情になるということになります。
では、これらの反論法を考えてみます。
「要件を満たさない場合」
(1)過少申告そのものとは別に、隠蔽、仮装と評価すべき行為がない場合(単なる過少申告ではないか、という場合)
この場合には重加算税が課されない、ということになります。(2)納税者が、当初(申告時までに)から所得を過少に申告することを意図したとは言えない場合
「あとで気づいた」というような反論です。(3)その意図を外部からもうかがい得る特段の行動がない場合
「特段の行動がどこにあるのか」と行動の特定を求めて、「重加算税の課税要件事実の立証責任は課税庁側にある」という反論をしていくということになります。
この判例は、さまざまなところで引用されている有名なものですから、しっかりその反論方法も含めて、頭に入れておいていただければと思います。