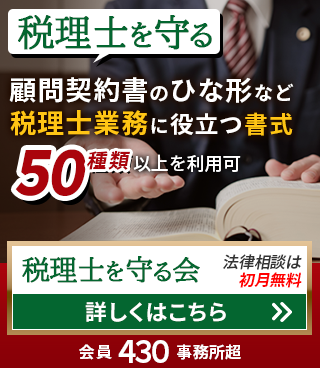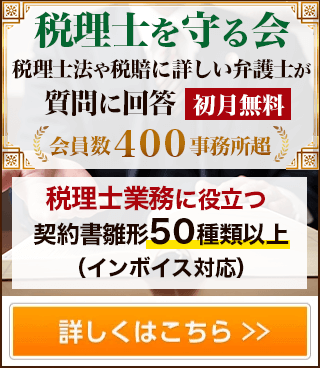【この記事の著者】
【この記事の著者】
公認会計士・税理士 佐藤信祐先生
掲載日 2023/10/5
最三小決令和5年5月24日(株式売買価格決定申立事件)では、譲渡制限株式の売買価格の決定において、非流動性ディスカウントを考慮すべきであると判示しました。
これに対し、本判決が公表される前の最一小決平成 27 年 3 月 26 日(株式買取価格決定申立事件)では、反対株主の株式買取請求における買取価格の決定において、非流動性ディスカウントを考慮すべきでないと判示していました。
本記事では、これらの判決の違いと今後の実務への影響について解説を行います。
非流動性ディスカウント
非上場株式は上場株式に比べて流動性が低く、売買成立の困難性や追加的な取引コストの発生が考えられます。
そして、取引目的の株式評価のうち、少数株主にとっての株式価値を評価する場合には、非流動性ディスカウントを考慮することが一般的です。
そのため、裁判目的の株式評価でも、少数株主にとっての株式価値を評価する場合には、非流動性ディスカウントを考慮すべきであるとする見解が多いと思われます。
これに対し、取引目的の株式評価において、支配株主にとっての株式価値を算定する場合には、非流動性ディスカウントを考慮しなくてもよいとする見解(KPMGFAS『図解でわかる企業価値評価のすべて』149-150 頁(日本実業出版社、平成 23 年)、谷山邦彦『バリュエーションの理論と応用』337 頁(中央経済社、平成 22 年)など)と、少数株主にとっての株式価値を算定する場合に比べてディスカウント率を低く設定しても構わないものの、非流動性ディスカウントを考慮すべきであるという見解(安達和人『ビジネスバリュエーション』331 頁(中央経済社、平成 23 年)など)がありました。
そのような背景があったことから、裁判目的の株式評価においても、非流動性ディスカウントを考慮すべきかどうかについての統一した見解は存在しませんでした。
株式買取価格決定申立事件
最一小決平成 27 年3月 26 日では、
「反対する株主に会社からの退出の機会を与えるとともに、退出を選択した株主には企業価値を適切に分配するものであることをも念頭に置くと、収益還元法によって算定された株式の価格について、同評価方法に要素として含まれていない市場における取引価格との比較により更に減価を行うことは、相当でないというべきである」
と判示されました。
しかし、この判示だと、収益還元法であるから非流動性ディスカウントが認められないのか、株式買取価格決定申立事件であるから非流動性ディスカウントが認められないのかが明らかではありません。
この点については、非流動性ディスカウントは、株式の売りにくさを示す要因に過ぎず、会社の企業価値に影響を与えるものではないことから、企業価値の適切な分配機能を発揮させるという会社法の目的からすると、非流動性ディスカウントを考慮すべきではないと考えられます(滝琢磨「判批」経理情報 1415 号 43 頁(平成 27 年))。
これに対し、取引目的の株式評価において、支配株主にとっての株式価値及び少数株主にとっての株式価値のいずれも非流動性ディスカウントを考慮するような事案であれば、非流動性ディスカウントを加味しないと、少数株主が不相当な利益を享受することから、裁判目的の株式評価においても、非流動性ディスカウントを考慮すべきとする見解もありました(田中亘『会社法』696 頁(東京大学出版会、第4版、令和5年)など)。
ただし、この見解は、たとえ取引目的の株式評価において非流動性ディスカウントを加味したとしても、少数株主にとっての株式価値におけるディスカウント率よりも低くなるといった実態を考慮していないという問題があります。
さらに、会社法の学者の中には、非流動性ディスカウントの実態が小規模ディスカウント(サイズリスクプレミアム)であるとする見解も少なくなく(星明男「非上場株式の買取価格と非流動性ディスカウント」『平成 27 年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊2016 年 4 月 10 日号)』108 頁(有斐閣、平成 28 年)、飯田秀総「非上場株式の評価」『会社法判例百選(別冊ジュリスト 254 号)』181 頁(有斐閣、第4版、令和3年)など)、そのような見解に従うと、小規模ディスカウント(サイズリスクプレミアム)が加味されている場合には、非流動性ディスカウントを加味すべきではないという見解に繋がりかねません。
しかしながら、取引目的の株式評価では、非流動性ディスカウントの実態が小規模ディスカウント(サイズリスクプレミアム)であるとする見解は採用されていないことから、裁判目的の株式評価においても、そのような見解を採用すべきではないと思われます。
株式売買価格決定申立事件
最三小決令和5年5月 24 日では、会社法 144 条2項に基づく譲渡制限株式の売買価格の決定の手続が、譲渡を希望する株主に対して当該譲渡に代わる投下資本の回収の手段を保障するために設けられたものであることから、当該譲渡制限株式に市場性がないことを理由に減価を行うことが相当と認められる事案(すなわち、取引目的の株式評価において非流動性ディスカウントを考慮すべき事案)においては、裁判目的の株式評価でも非流動性ディスカウントを考慮すべきであるとしました。
本事件は、原審における当事者間の主張を見る限り、マイノリティ・ディスカウントは考慮されておらず、かつ、議決権比率が 18.8%、10.7%程度であるものの、亡くなった代表取締役の親族が保有していた株式に対する争いであることからも、支配株主にとっての株式価値について争われていると考えられます。
すなわち、譲渡制限株式の売買価格の決定においては、支配株主にとっての株式価値を評価する場合であっても、非流動性ディスカウントを考慮すべきであるということになります。
この判示に問題があるとすれば、そのディスカウント率です。原審にあるように、支配株主にとっての株式価値の評価において、30%ものディスカウント率を採用することが相当であるかどうかについては、ファイナンスの専門家の中に異論が生じることが予想されます。
さらに、本判決では、
「譲渡制限株式の評価額の算定過程において当該譲渡制限株式に市場性がないことが既に十分に考慮されている場合には、当該評価額から更に非流動性ディスカウントを行うことは、市場性がないことを理由とする二重の減価を行うこととなるから、相当ではない」
とも判示しています。
これは、小規模ディスカウント(サイズリスクプレミアム)が加味されている場合には、非流動性ディスカウントを加味すべきではないという見解に配慮したものと思われ、そのような見解が支配的になった場合には、取引目的の株式評価と裁判目的の株式評価との間に齟齬が生じることが予想されます。
まとめ
このように、組織再編における反対株主の株式買取請求における買取価格の決定においては非流動性ディスカウントを考慮すべきではなく、譲渡制限株式の譲渡における株式売買価格決定申立事件では非流動性ディスカウントを考慮すべきであるとする裁判所の見解が確立したといえます。
しかしながら、ディスカウント率をどのように算定すべきなのか、小規模ディスカウント(サイズリスクプレミアム)との関係をどのように考えるべきなのかについては、見解が分かれる可能性が高いため、今後の実務の動向を見守る必要があります。