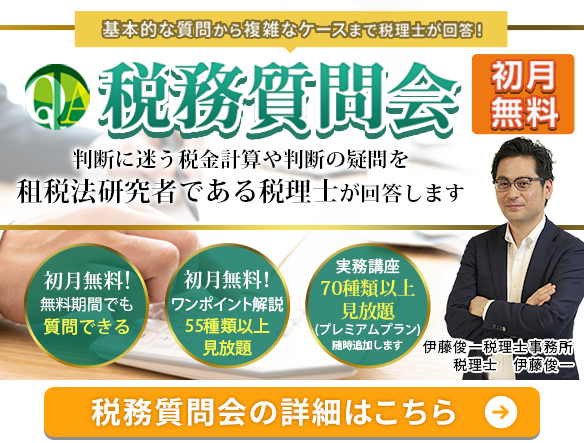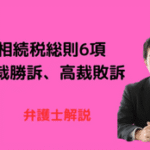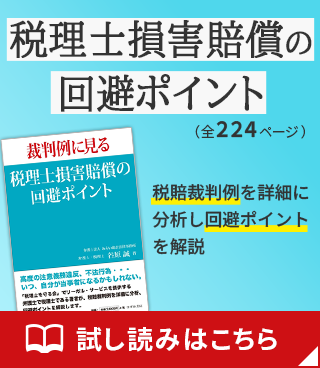相続人が被相続人の預貯金などを承諾なしに処分した場合は、贈与として認定されるのが一般的とされています。さらに、換金した現金の一部を費消していた場合には、遺贈ではなく贈与として判断されることになります。
被相続人の財産処分は本人の意思に基づくことが大前提であり、その意思を証拠資料として残し、財産の帰属を明確にしておくことが求められます。
ここで、以下の2点について確認させてください。
① この「贈与認定」の法理論構成は、次の理解で正しいでしょうか。
相続人が被相続人の財産の一部を承諾なしに費消した場合
→ 費消部分については現存利益がないため、原則として不当利得返還は不要(民法703)
→ しかし、相続税法9条(対価を支払わないで利益を受けた場合)に該当し、みなし贈与として認定される
② 実務上の具体例として、入院中の被相続人の通帳を相続人の1人が管理し、その間に20万円を引き出した場合を想定します。
この20万円のうち、領収書やメモ書きで使途が明確でない部分については、相続税の実務では通常その相続人へのみなし贈与と認定される。
そのため、共同相続人による不当利得返還請求ができる場合を除き、税理士としては贈与として処理して差し支えないと考えてよいでしょうか。
(参考法令等)
・民法703
・相続税法9条
・相続税法基本通達9-1(「利益を受けた」の意義)