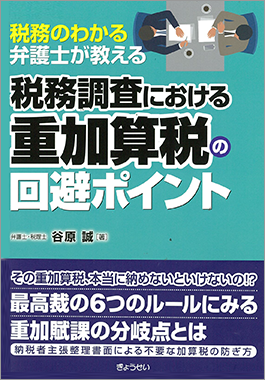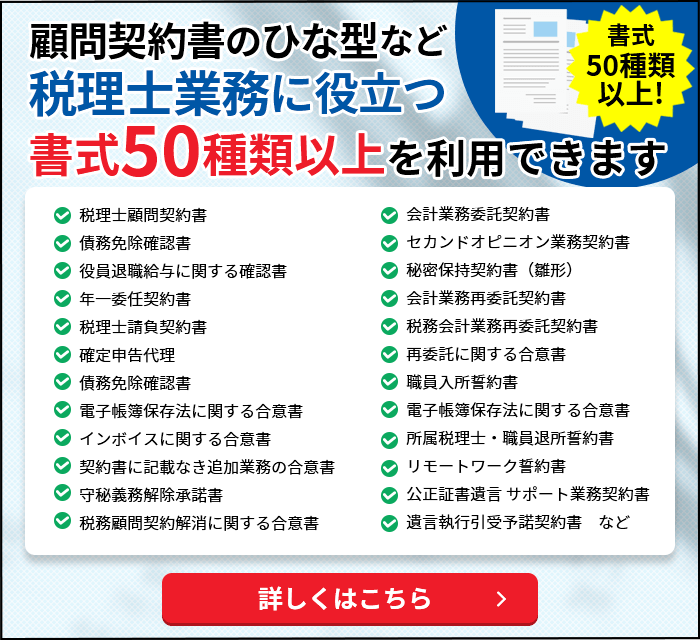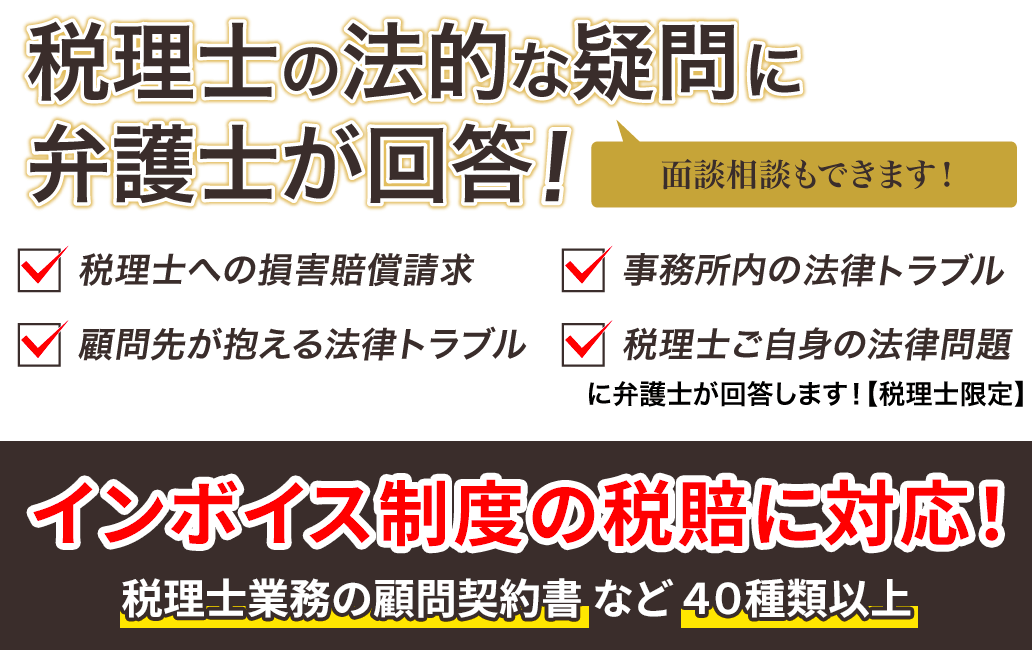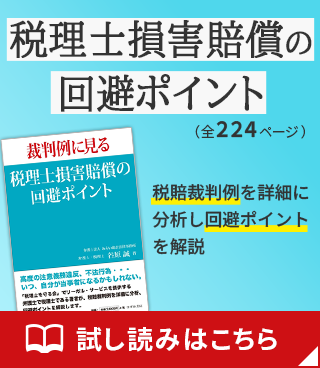税務調査で「重加算税」に備える視点、持てていますか?
税務調査に関わる税理士であれば、「重加算税」の言葉に特別な緊張感を抱かない人はいないと思います。
なにしろ、納税者に“仮装・隠ぺい”があったと判断された場合、35%〜50%にも及ぶ高率の追徴課税が課される制度です。
一度適用されれば、納税者にとっての金銭的・心理的インパクトは非常に大きく、税理士としての対応力や判断力がシビアに問われる局面になります。
しかしながら、重加算税の適用要件というのは、法的にはかなりあいまいです。
実務の中でその境界線を意識的に学ぶ機会は限られており、「実際に課されてから初めて対応に追われた」という声も少なくありません。
ここで重要なのは、調査対応の段階から「どこまでが適法で、どこからが違法か」を見極める視点を持てるかどうか。
たとえば
•重加算税の判断に、最高裁判決がどう影響するのか?
•そもそも今ある判例は、いまの時代にも通用するのか?
•「納税者主張整理書面」は、どう活用すべきなのか?
こうした問いに対して、感覚ではなく、法的根拠を踏まえて判断できるための“基準”や“考え方”を整理しておくことが、税務実務において大きな武器になります。
では、そうした基準はどこでどう学ぶべきか?
日々の顧問業務に追われる中で、判例を一つひとつ読み解く時間を取るのは難しい…という方も多いのではないでしょうか。
そんなとき、「裁判所の実際の判断ルール」に基づいて重加算税の適法性を読み解く視点があると、調査対応や処分後の助言が格段に変わってきます。
重加算税の“判断軸”を整理し、トラブルが起こる前に備える。
そのための知識と視点を、改めて棚卸ししてみてはいかがでしょうか。
おすすめの記事

情報
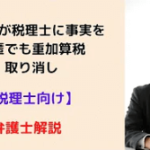
税理士業務に役立つ動画
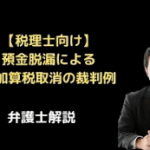
税理士業務に役立つ動画

組織再編税制