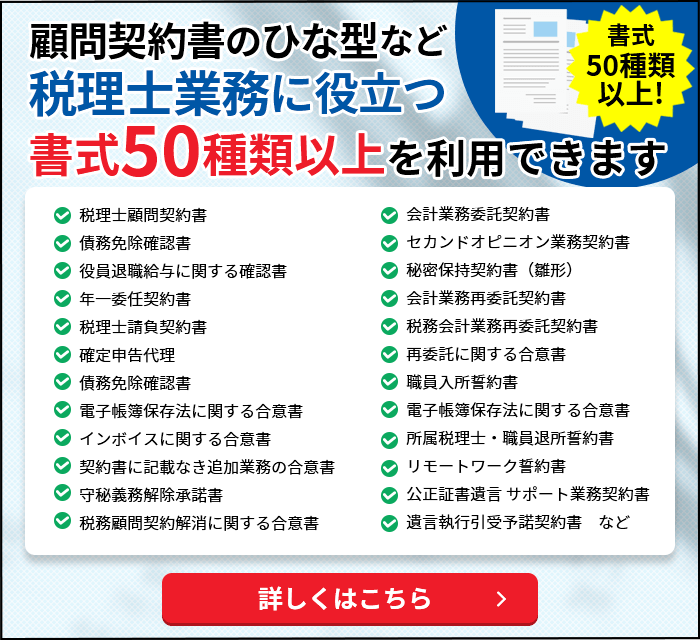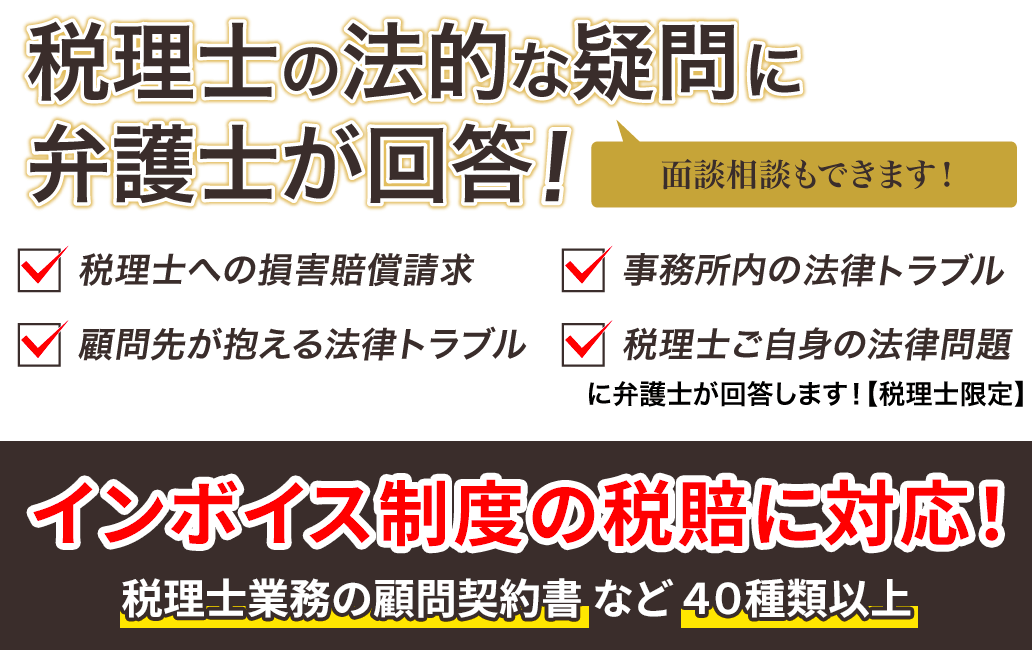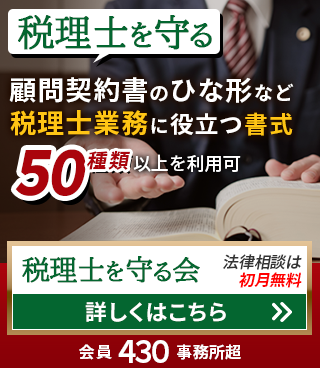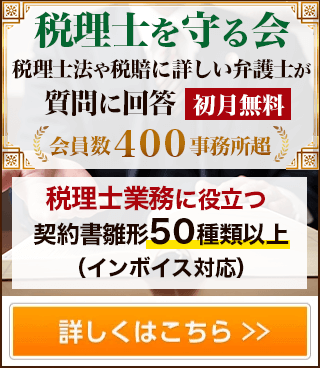今回は最高裁判決前の下級審裁判例を読む時の注意点ということで、特に虚偽答弁について解説します。
大阪地裁昭和55年の判決です。事案は不動産の貸付を業とする納税者が会社に対する貸付金の利息収入(雑所得)を除外して確定申告をした。
税務調査があり、納税者は、税務調査官に対して虚偽の答弁をしたこということで、重加算税賦課決定がされました。
判決です。原告の昭和45ないし同48年分の所得税の申告の内容は別表第1のとおりであって、これには利息収入による雑所得が除外されている。それから原告は本件処分前の被告の職員の調査に際し、その職員に東南商事に貸された金300万円について原告は仲介をしただけで利息収入を得ていないと。
そのほかに650万円をB社に貸したこともないと供述した、これが虚偽答弁ですね。原告が税務調査の際、利息収入がないと答弁したことは当事者間に争いがない。
そうするとこの事実を併せ考えると、原告は故意に課税標準の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき申告書を提出したということで、重加算税賦課要件を満たします、ということになります。
この判例で適示されているのが2点です。
①雑所得が除外されている事実
②税務調査で虚偽の答弁をした
これをもって隠ぺいしたと認定がされております。
ところが、その後、この裁判例の後に最高裁判決が2つあります。
さきほどは昭和55年でした。今度は平成6年です。
(1)各確定申告の時点において、真実の所得金額を隠ぺいしようという確定的な意図を持っておりということなので、隠ぺいする意図は確定申告の時点で必要だということ。
(2)必要に応じ事後的にも隠ぺいのための具体的工作を行うことも予定して、これいつ予定しているかというと、やはり確定申告の時点にもう予定しているということ。
(3)会計帳簿類から明らかに算出し得る所得金額の大部分を脱漏し、所得金額を殊更過少に記載した虚偽の確定申告書を提出した時には、重加算税の賦課要件を満たすということ
ですのでさきほどは昭和55年ですが、最高裁が出た場合には下級審裁判は基本的には、原則的には最高裁の基準に則って判断しますので、先程の事例において確定申告の時点において確定的な意図があったのかと、必要に応じ事後的にも隠ぺいの予定があったのかどうなのかという事実認定をしないと、重加算税賦課要件を満たすかどうかは判断できないということになります。
そのため、結論が違う可能性があるということになります。
もう1つ、最高裁平成7年です。これ有名な表現です。
納税者が、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合には、重加算税の右賦課要件が満たされる。この最高裁判例のこの規範を当てはめる場合もありますので、そうすると先程の大阪地裁昭和55年の事例が、当初からやはり申告時点でそういう意図が必要なんだということです。
かつ、その他にその意図を外部からも伺える特段の行動をしたかどうかということになりまして、虚偽答弁というのは一事情ですね、外部からうかがえる特段の行動の一事情、その他に何か特段の行動があるかどうかということを認定しないといけないということになります。
最高裁が出る前の裁判例の例えば税務調査の時に調査官がこういう判例があたりますよ言ってきたとしても、最高裁後においてはこの最高裁の規範を当てはめて考えないといけないので、結論が違ってくる可能性があるということになってきますので、この点注意です。
そして最後に通達を見ておきたいんですが、申告所得税の重加算税通達、調査等の際の具体的事実についての質問に対し、虚偽の答弁等を行い、又は相手先をして虚偽の答弁等を行わせていること及びその他の事実関係を総合的に判断して、申告時における隠蔽又は仮装が合理的に推認できるかどうかということです。
ですので、この通達においても虚偽答弁だけでは認定できません、ということで、虚偽答弁及び他の事実関係で何かあるかどうか。
そして総合的に判断して、やはり申告時点での隠ぺい又は仮想があるかどうかというのを判断するんだということがこの通達ということになります。
弁護士法人みらい総合法律事務所では税理士を守る会という税理士だけが会員になれるリーガルサービスを提供しております。