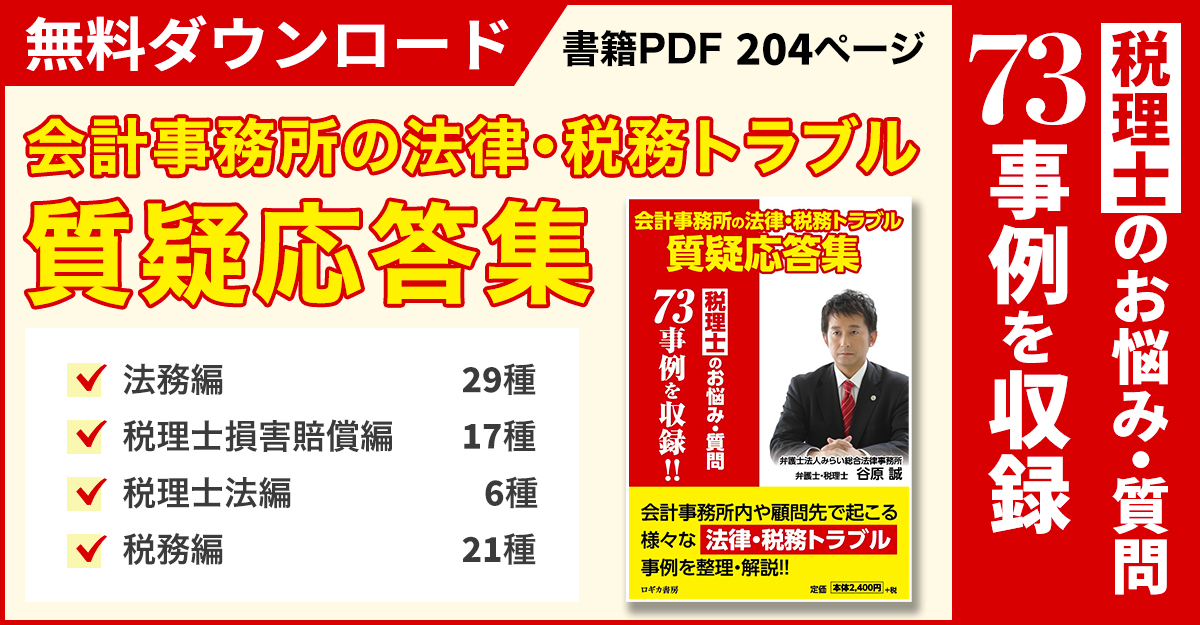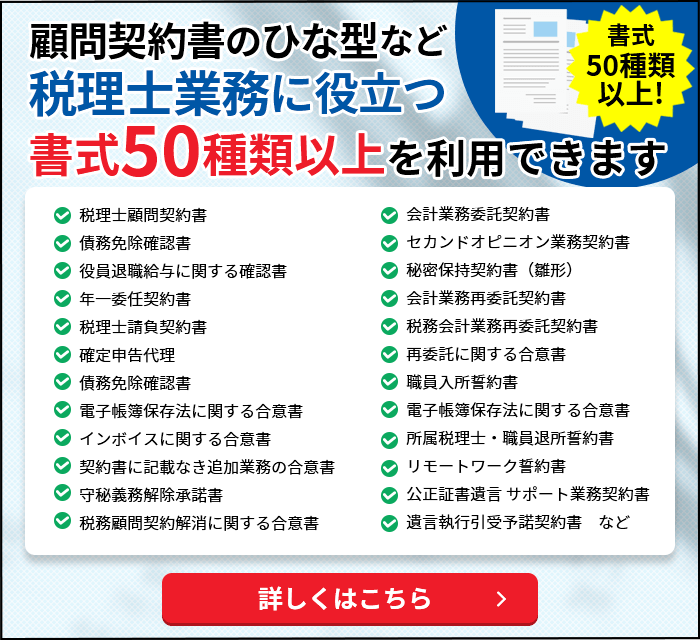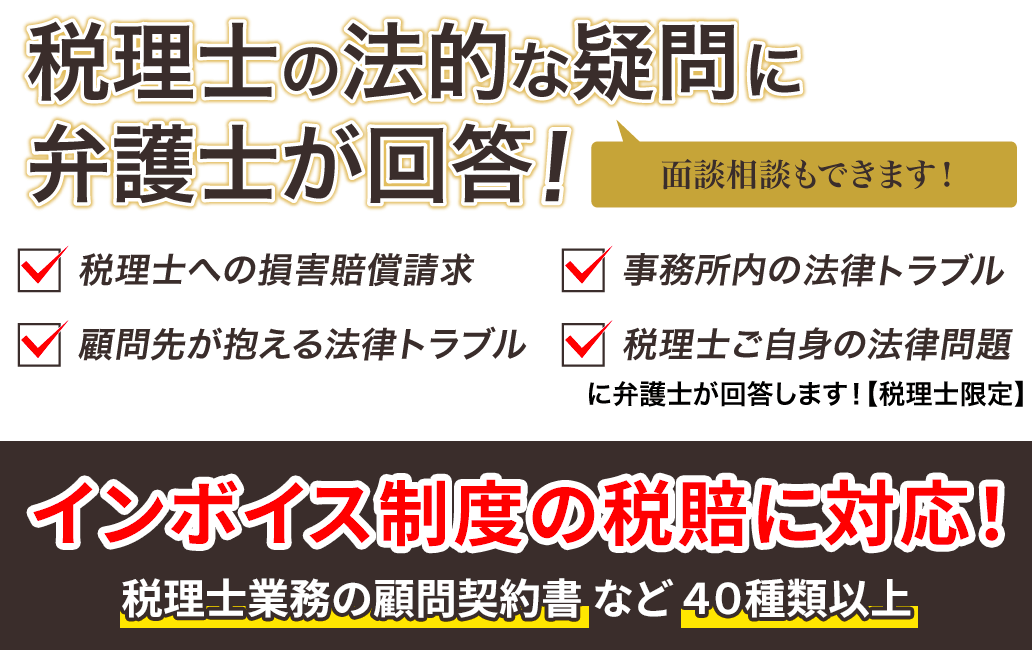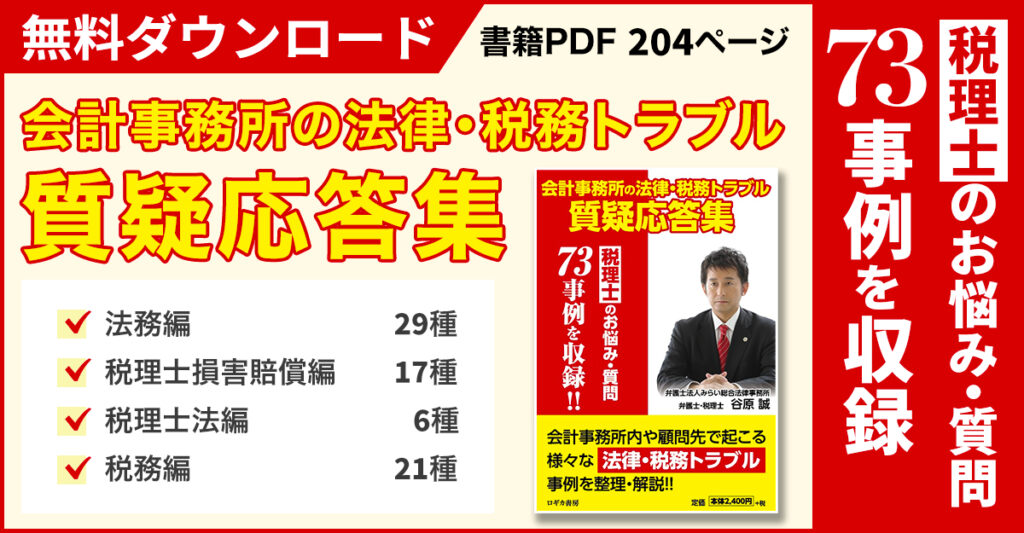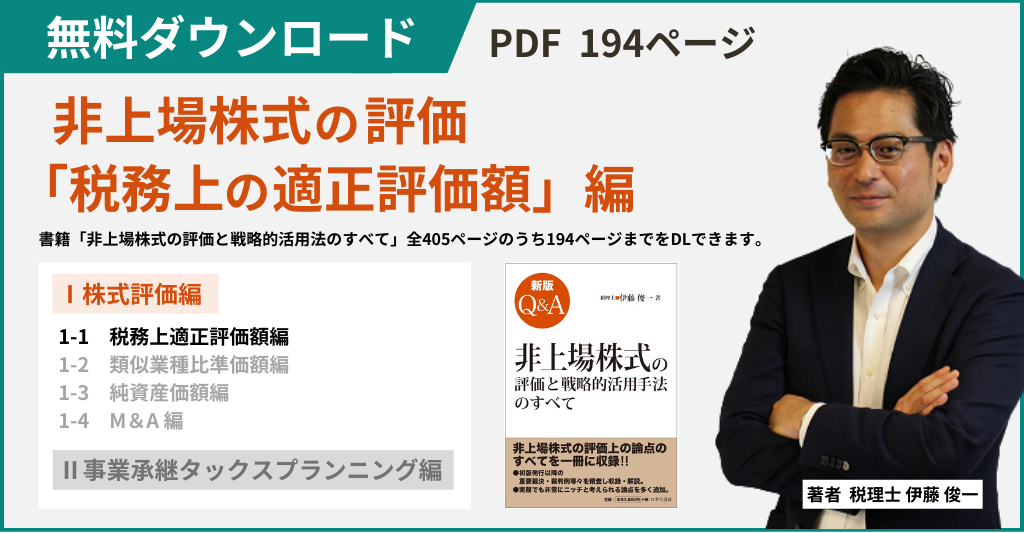執筆:弁護士・税理士 谷原誠

今回は、税理士法人が破産する場合の法的要件や社員の責任について、破産法や会社法、税理士法の規定を踏まえて整理します。
破産申立ができる要件:
株式会社と税理士法人の違い
通常、株式会社などの法人は、以下のいずれかの状態にある場合に破産申立が可能です。
- 債務超過(負債が資産を上回っている状態)
- 支払不能(支払う資金がなく、債務の履行ができない状態)
一方、合名会社については、「支払不能」の場合に限って破産申立が可能とされています(破産法第16条)。
そして、税理士法第48条の21第6項では、以下のように定められています。
「破産法第十六条の規定の適用については、税理士法人は、合名会社とみなす。」
このため、税理士法人も「債務超過」だけでは破産申立ができず、「支払不能」の場合のみ破産申立が可能ということになります。
「支払不能」とは?
「支払不能」とは、単に帳簿上の赤字ではなく、現実に債務の履行ができない状態を指します。
具体的には、
- 十分な収入や資産がない
- 債務の支払期日が到来している
- それにもかかわらず支払えない
といった状況にあることが必要です。
税理士法人破産時の社員の責任
社員は無限連帯責任を負う
税理士法人の社員(税理士)は、法人の債務について無限連帯責任を負います。
これは、税理士法第48条の21により、会社法第580条第1項が準用されていることによります。
【会社法第580条第1項】
「社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合」
つまり、税理士法人の財産で債務を完済できない場合には、社員が連帯してその債務を弁済する責任を負うことになります。
退社した社員の責任
では、既に退社した社員はどうなるのでしょうか?
この点については、会社法第612条が準用され、以下のように規定されています。
【会社法第612条】
「退社した社員は、その登記をする前に生じた債務について、従前の責任の範囲内で弁済する責任を負う。
この責任は、登記後2年以内に請求または請求の予告がなされない場合、2年経過後に消滅する。」
つまり、退社していても、脱退登記から2年間は無限連帯責任を負うとになります。
税理士法人の破産と解散の関係
税理士法人が破産手続開始の決定を受けると、その時点で法人は解散します(税理士法第48条の18)。
多くの定款では、以下のような規定が設けられています。
「破産または解散した場合、社員は脱退する」
この場合、破産開始決定により社員は自動的に脱退し、脱退登記がなされれば、先ほどの退社後2年間の責任ルールが適用されます。
仮に定款にそのような記載がなくても、破産手続が終了すれば法人格が消滅しますので、結果的に社員は脱退扱いとなり、同様の責任を負うことになります。
まとめ
- 税理士法人は「支払不能」の場合にのみ破産申立が可能(合名会社とみなされる)
- 税理士法人の社員は、法人の債務に対して無限連帯責任を負う
- 退社した社員も、脱退登記から2年間は責任を負う
- 破産開始決定により法人は解散し、社員は定款に従って脱退となる