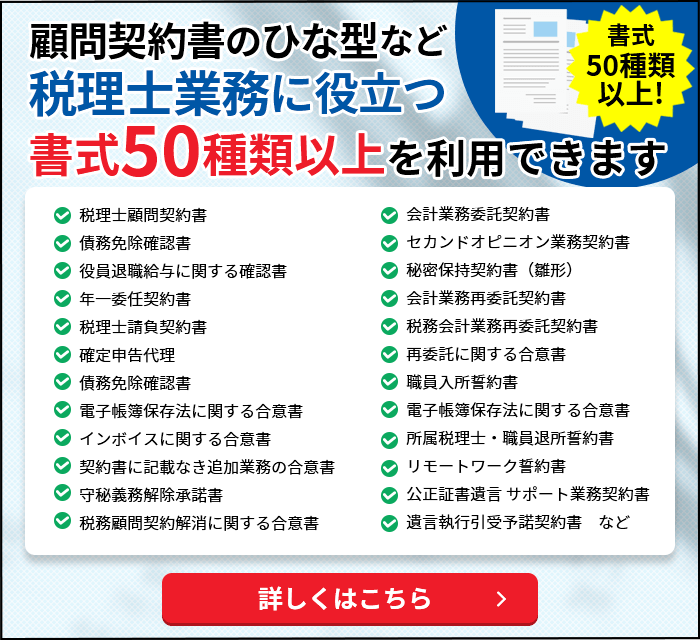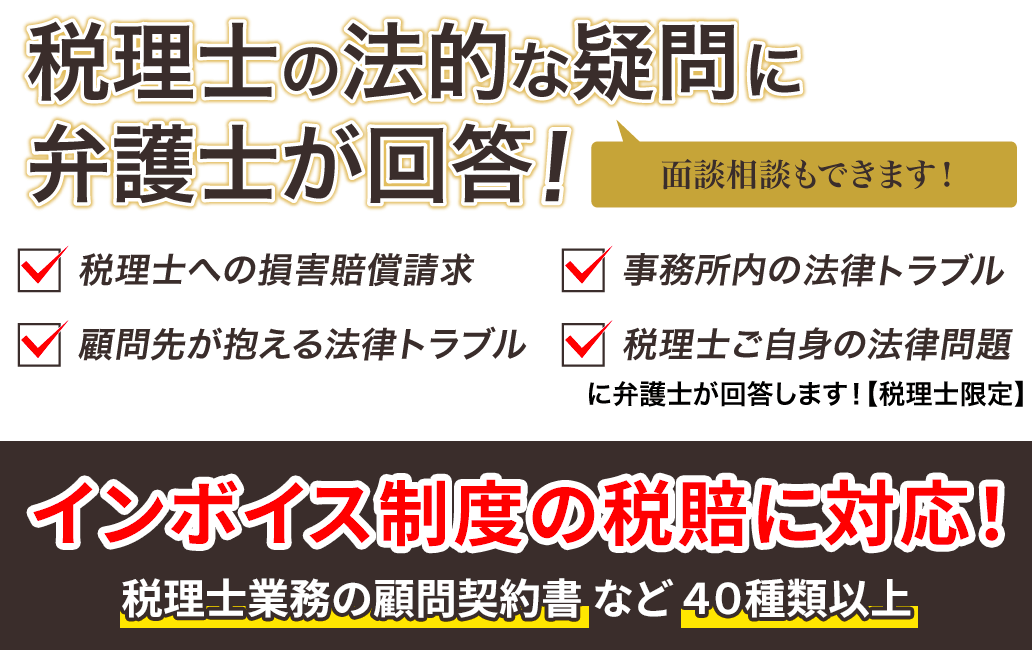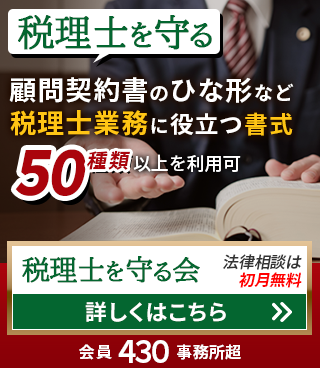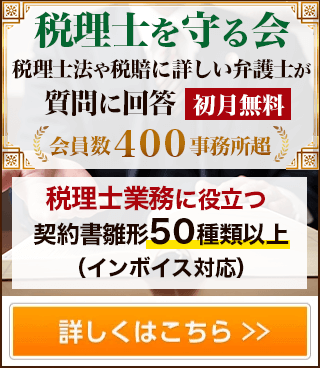今回は、役員や従業員等の行為で重加算税の要件を満たす場合と満たさない場合について解説します。
税務調査等で否認されて重加算税を課せられるというような場合に、代表者の行為ではなくて、その会社の役員や従業員、あるいは家族といった第三者の行為で重加算税を課せられるというようなケースがあると思います。
その際に、重加算税の要件を満たすのはどのような場合なのか、また要件を満たさないのはどのような場合なのか、について考えてみたいと思います。
内容としては、私が執筆している書籍『税務のわかる弁護士が教える 税務調査における重加算税回避ポイント』からご紹介をしていきます。
【重加算税の負荷要件(過少申告)の場合】
「国税通則法第68条1項」
①過少申告加算税の規定に該当する場合
②納税者が
③その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、または仮装し、
④隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していた。
このような場合に重加算税が課せられます。
ここでは、②の「納税者が」といえるのかどうなのか、そして③の「隠蔽し、又は仮装し」といえるのかどうなのかが問題となります。
そこで、役員や従業員、家族等が隠蔽又は仮装した場合は、果たしてこの要件を満たすのか、について考えていきます。
【重加算税に関する判例集】
過去の裁判例としては次のものなどがあります。
「静岡地裁昭和44年11月28日判決」
納税者(法人)の取締役が隠蔽仮装をしたという場合で、重加算税が維持されています。
「名古屋地裁平成4年12月24日判決」
代表者の実弟であり、かつ常務取締役という重要な地位にあった者が隠蔽仮装をしたということで、重加算税が維持されています。
「東京地裁昭和55年12月22日判決」
代表者の元配偶者、かつ会社設立時の代表取締役、かつ現取締役という非常に重要な地位にある者が隠蔽仮装をしたということで、重加算税が維持されています。
代表者と同視されているということです。
「札幌地裁昭和56年2月25日判決」
納税者(法人)の支店長も重要な地位にあったということで、重加算税が維持されています。
「大阪地裁平成10年10月28日判決」
納税者(法人)の代表者の非親族の経理補助業務従業員に重加算税が維持されています。
これは、①この従業員に対する管理監督が不十分だった、②知り得たのに放置していた、③また代表者の遠縁で法人設立時から従業者だった、ということで重要な地位にあったと判断されています。
「大阪地裁昭和36年8月10日判決」
納税者の父親(親族)が行った行為についても重加算税が維持されています。
備考としては、この父親が不動産売却の代理人かつ管理の実権を持っていたということで、大きな権限を与えていたということです。
「大阪地裁昭和58年5月27日判決」
父と共有土地の売却。本人国外で父の処分及び申告を委任、全て任せていたという事例です。
「岐阜地裁平成2年7月16日判決」
納税者の夫の行為で重加算税が維持されました。
これは、本人がお茶などを出していて、知っていたと推認されたという事例です。
この結論について、私は疑問に思っているのですが、判決ではこのようになっています。
「鳥取地裁昭和47年4月3日判決」
重加算税を取り消された事例で、これは納税者の弟の行為です。
共同経営で売り上げを折半しており、弟が売上を脱漏して仮装名義に入金していた事実があったが、それを兄は知らされていなかったというような事実で、このような場合には納税者本人の行為とはいえない、ということになっています。
「国税不服審判所」
共同相続人の一人が被相続人およびその一族の不動産賃貸料収入等を運用した無記名定期預金を隠蔽した事案です。
他の相続人は一切知らなかった、ということで、これは納税者本人の行為と同視することはできないとして重加算税が取り消されました。
この点に関する最高裁の立場はどうなっているでしょうか。
「最高裁平成18年4月20日判決」
これは役員や従業員ではなく、税理士が納税者に無断で隠蔽又は仮装行為をした事案です。
最高裁は、「隠蔽仮装行為を納税者本人の行為と同視できる場合は、重加算税の賦課要件を満たす」と言っています。
本人の行為と同視できるかどうか、そして同視できるかどうかの基準を定立しているということです。
ただ、これは少し関係が遠い税理士の事案ということなので、(ここでは基準自体は紹介しませんが)本人の行為と同視できるかどうかがかポイントということです。
そして、これに基づいて、大阪国税局が「課税処分に当たっての留意点(平成25年4月 大阪国税局 法人課税課 TAINS H-250400 課税処分留意点 179頁)」というものを出しています。
「代表権を有する者が行った不正行為は会社の行為となるが、その他の会社関係者が行った不正行為の結果、過少申告が生じた場合であっても、その不正行為を会社の行為と同視して重加算税を賦課できる場合がある。」
先ほどの最高裁判決を受けての、「会社の行為として同視できるかどうか」という基準です。
「従業員であっても、会社の主要な業務を任され、長期にわたる不正や多額な不正など会社が通常の注意をすれば容易に発見できる不正行為を管理監督しなかったために、これを見過ごし、結果としてこれを起因とする過少申告が生じた場合には、会社の行為と同視することができる。」
「管理監督責任の不履行については事実関係を立証することが困難である場合が多いので、不正行為者がどの範囲まで業務を任され、当該業務がどのようにチェックされていたか等について、特に次の①から③までについて関係者に対する『質問応答記録書』を作成するなどして証拠化しておく必要がある。
①重要な事務を担当していたこと
②当該従業員に業務を任せきりにしていたこと
③法人が何らかの管理・監督をしないまま放置していたこと」
これらについて質問応答記録書を取ってくる、ということになります。
ということは、役員、従業員等の第三者の行為で、税務調査において重加算税の指摘を受けたような場合は、反論としては次のように主張することが考えられます。
(1)不正行為者が重要な事務を担当する地位や権限を有していないこと。
「単なる従業員です」というような主張です。(2)会社が就業規則やルールにより不正を禁止していたこと。
「だから、会社としてはしっかり監督していた」というような主張です。(3)会社が管理・監督していたにもかかわらず不正が生じたこと。
「会社としては、このように禁止していた、報告書の提出義務を課していた、あるいはマニュアルを作成して管理・監督するような仕組みを作っていた。それにもかかわらず、役員・従業員らが不正を働いた」というようなことを反論していく、ということになります。
つまり、先述の①②③の反対側を考えて、事実を引っ張りだしてきて反論していく、ということです。
このように、第三者の行為で重加算税を課されることも結構あると思います。
しかし、課される場合もあるし、課されない場合もあり、それは会社の行為と同視できるかどうか、ということがポイントになります。
この点をよく検討して、不当な重加算税が課されないようにしていただければと思います。