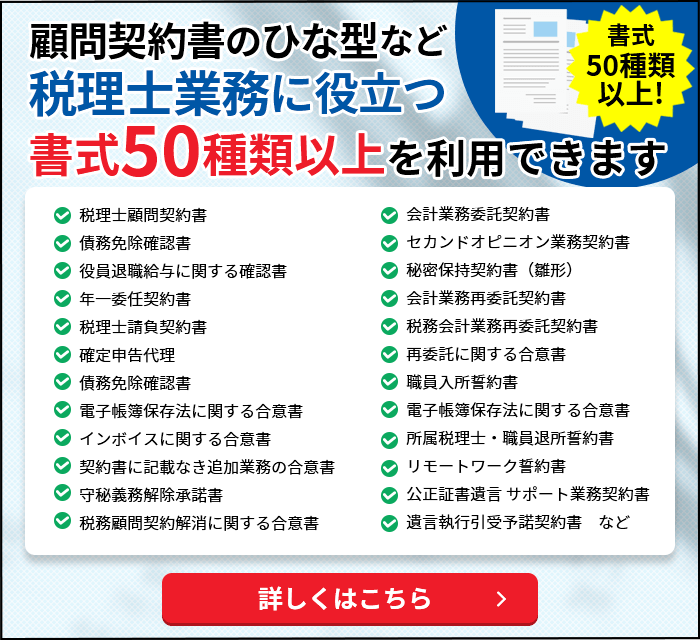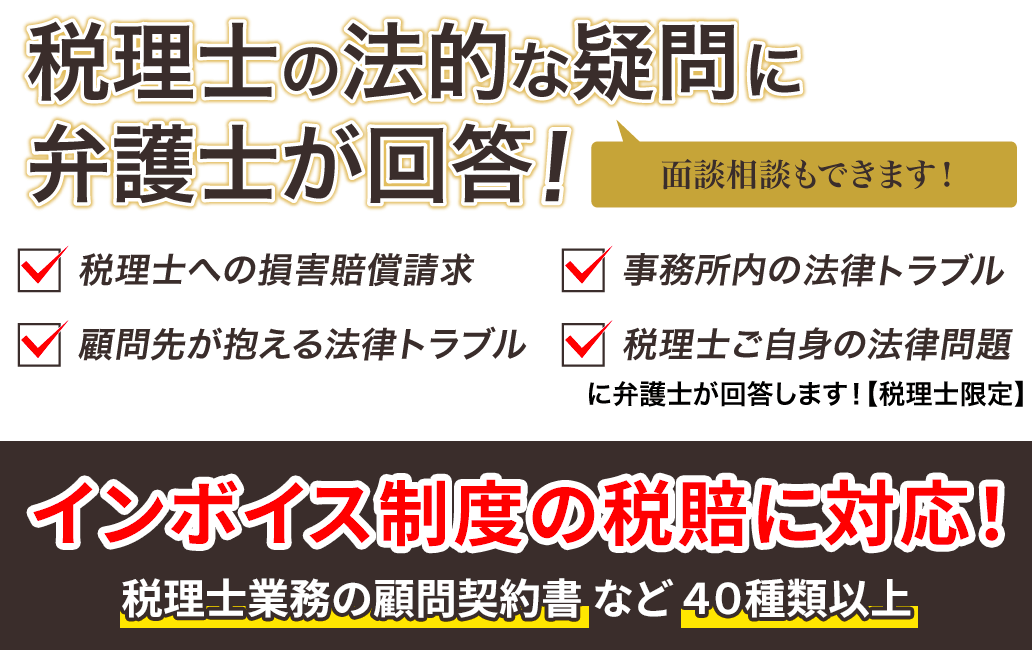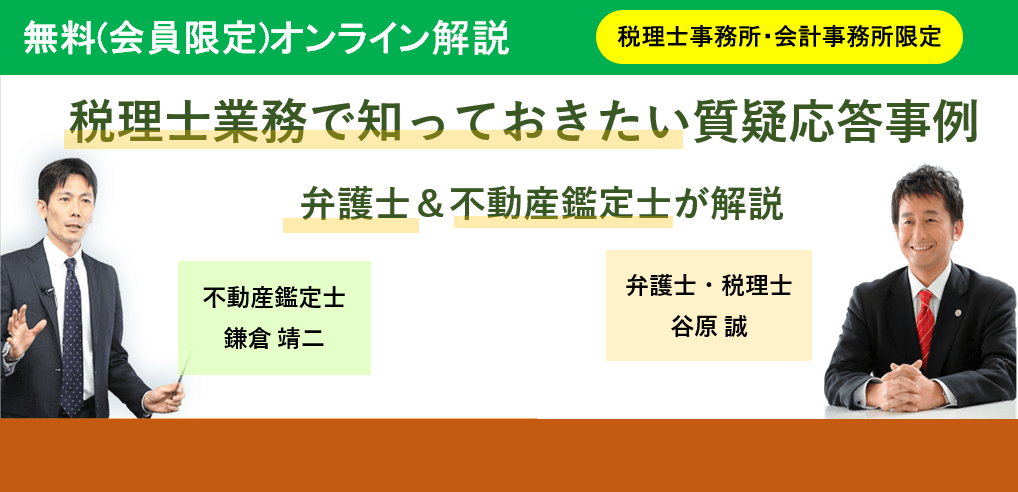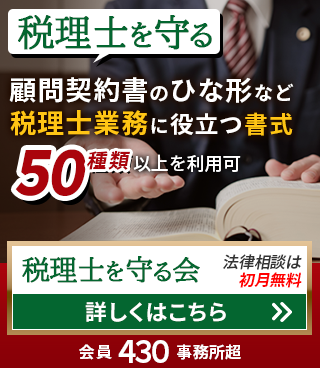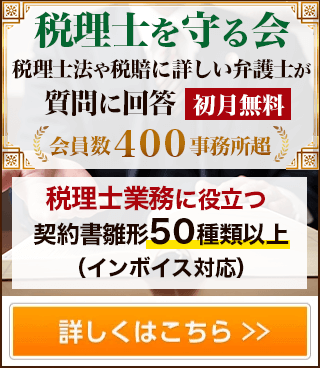執筆:弁護士・税理士 谷原誠
今回は、「給与所得と事業所得の区別と判断基準」のチャプター2ということで解説していきます。
チャプター1を読まないとつながりがわかりませんので、必ずチャプター1から読んでいただきたいと思います。
【事業所得か給与所得かが争われた判例】
前回、多くの裁判例を紹介しましたが、すべて事業所得か給与所得かが争われた判例です。
・最高裁昭和56年4月24日判決(弁護士の顧問料)
この判決では、弁護士の顧問料は給与所得とされています。・最高裁昭和53年8月29日判決(日フィル事件)
オーケストラの楽団員は給与所得と判断されています。・福岡地裁昭和62年7月21日判決
電力会社の検針員は事業所得と判断されています。・最高裁平成13年7月13日判決
民法上の組合員の事業従事は給与所得と判断されています。・京都地裁平成20年10月21日判決
弁護士会の無料相談担当の対価は事業所得と判断されています。・東京地裁平成24年9月21日判決
麻酔科医(手術担当)の報酬は給与所得と判断されています。・東京地裁平成25年4月26日判決
教育機関の講師料、家庭教師料は給与所得と判断されています。・京都地裁平成27年8月21日判決
大学の非常勤講師料が給与所得と判断されています。
以上が裁判例なのですが、今回は国税不服審判所の裁決も見ておきたいと思います。
【国税不服審判所の裁決】
「国税不服審判所平成22年6月23日裁決」
(事案)
ダクト取付等工事業を営む請求人が外注費として支払った金員が給与等に当たるとして源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分等を行った事案で、給与等と認定された。(裁決の理由)
・請求人に常に雇用されていた。(継続的な役務提供の対価であった)
・集合場所から現場までの間は請求人の車両で移動しており、その費用は請求人が負担していた。(独立性の否定、自己の計算と危険の否定)
・作業に必要な高額な器具は請求人が調達して無償で貸与していた。(独立性の否定、自己の計算と危険の否定)
・各現場への人員配置及び各現場の責任者の選任は請求人が行なっていた。(指揮命令下であった)
・行った仕事上の対外的な責任は請求人が負っていた。(自己の計算と危険の否定)
・支払った金員は、月給または従事した日数に日当を乗じた金額に、残業手当を加算した金額である。(継続的な役務提供の対価であった)
「国税不服審判所平成30年1月11日裁決」
(事案)
キャバクラを経営する請求人がキャストらに支払った金員は給与等に該当し、売上金員の一部を請求人の代表者が費消したことは給与等に該当するとして源泉徴収に係る所得税等の納税告知処分等を行った事案で、給与等とされた。
「国税不服審判所平成26年7月1日裁決」(TAINS F0-1-561)
(事案)
スナックのホステスに関する事例で上記と同旨。(裁決の理由)
・キャストは接客業務に従事するに当たり、請求人との間で、給与体系、勤務時間及び店舗規則などの勤務条件について合意していた。(時間的・空間的拘束)
・請求人はキャストの勤務時間又は接客時間を管理していた。(時間的拘束)
・キャストは指名客以外の客に対しても店長の指示により接客していた。(指揮命令下)
・キャストは客に対する売掛金を回収する責任を負っていなかった。(自己の計算と危険の否定)
これらの理由から、給与等と判断されています。
【使用従属関係についての判断基準】
指揮命令下、使用従属性についての判断基準については、少し古いのですが、「労働省労働基準法研究会報告」(1985年)というものがあります。
これには、5つの主要な判断要素と2つの補足的な判断要素が示されており、労働者性、給与かどうかという仕用従属関係についての判断基準となっています。
なお、裁判所もこの基準を引用して判断していることがあります。
「主要な判断要素」
①仕事の依頼への諾否の自由があるかどうか
②業務遂行上の指揮監督があるかどうか
③時間的・場所的拘束性があるかどうか
④代替性があるかどうか
⑤報酬の算定・支払方法がどうなっているか
「補足的な判断要素」
⑥機械・器具の負担、報酬の額等に現れた事業者性
⑦専属性
なんとなく、消費税基本通達もこの資料からいくつか取っているのではないか、とお気づきになるかと思います。
【労働基準法適用の労働者性が認められた裁判例】
次に、労働基準法適用の労働者性が認められた裁判例(所得税法上の給与所得者)を見ていきます。
労働基準法が適用されるということは、指揮命令下にあって、当然、時間的・場所的な拘束を受けるということになるので、所得税法上も給与所得者となるものになります。
「労働基準法適用の労働者性が認められた裁判例」
・吹奏楽団員(岡山地裁平成13年5月16日判決/チボリ・ジャパン事件)
・映画製作の撮影技師(東京高裁平成14年7月11日判決)
・クラブホステス(東京地裁平成22年3月9日判決/第三相互事件)
・高齢者集合住宅に居住して高齢者の世話をする生活協力員(東京高裁平成23年5月12日判決/多摩市シルバーピア事業事件)
・芸能プロダクションのタレント志願者(東京地裁平成25年3月8日判決)
・LPガスボンベ配送・保安点検者(東京地裁平成25年10月24日判決/東陽ガス事件)
・保険代理店の保険勧誘員(大阪地裁平成25年10月25日判決/株式会社MID事件)。
・株式会社の社内弁護士(東京地裁平成21年12月24日判決)
これらは、労働基準法が適用される労働者と認定された事案ということになります。
指揮命令下、場所的・空間的拘束があり、かつ給料は継続的役務提供の対価となるので、当然、所得税法上も給与所得者となるはずのもの、ということです。
これらに該当する事案で、税務調査等で争点となった場合には、税法税務判例ではないのですが、これらの判例を当たることによって、その指揮命令を判定した基準等をピックアップできると思います。
【労働基準法適用の労働者性が否定された裁判例】
次に、労働基準法適用の労働者性が否定された、つまり労働者ではないとされた裁判例を見ていきます。
労働者ではないとなると、今度は他の要素、例えば指揮命令下や時間的・場所的拘束などのどれかが欠けているということになるので、他の要素を検討して、所得税法上の給与所得者かあるいは事業所得者かを認定しなければいけない事案、ということになります。
「過去の事例で労働者ではないとされた事例」
・銀座クラブのママ(東京地裁平成27年11月5日判決/Mコーポレーション事件)
・NHKのフランス語講座担当のフランス人教師(東京地裁平成27年11月16日判決/NHK事件)
・新聞社のフリーランス記者(東京高裁平成19年11月29日判決/朝日新聞社事件)
・日本相撲協会の力士(東京地裁平成25年3月25日判決)
・トラック持ち込み運転手(さいたま地裁平成23年3月25日判決)
・NHKの受信料集金受託者(東京高裁平成15年8月27日判決/NHK西東京営業センター事件)
ただし、労働者ではないからといって、すぐに所得税法上の給与所得者ではない、とはならないので、他の要素を総合的に考慮して認定していかなければならない事案、ということになります。
【消費税法の基本通達1-1-1について】
先生方は、よくこの通達を確認して、事業所得か給与所得か判定されていると思いますが、あくまでも出来高払いの給与であるか、請負による報酬であるかの区分を示した通達であるということは、ご留意いただきたいと思います。
「消費税法の基本通達1-1-1」
事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他のものに従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば次の事項を総合勘案して判定するものとする。
(1)その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2)役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。(自己の計算と危険の負担)
(4)役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
これまでの裁判例を見たうえで、この消費税の基本通達を見ると、大変よく理解できるのではないかと思います。
【東京国税局法人課税課速報について】
次に、国税局の内部資料について見ていきます。
情報開示請求によって開示された、「東京国税局 平成15年7月 第28号法人課税課速報(源泉所得税関係)」(TAINS H150700-28)です。
これは、事業所得か給与所得かを判定するときは、これらの要素を確認して総合的に判定してください、あくまでもこれは「例示」に過ぎないので各事案によって個別に対応してください、と書いてあるものです。
「要件」「給与(YES/NO)」「その他(NO/YES)」という項目があるのですが、例えば「労働基準法の適用を受けるか」という要件項目で、「受ける」となると「給与になる」ということです。
「要件」(給与)
・労働基準法の適用を受けるか
・支払者が作成している組織図・配席図に記載があるか
・役職(部長・課長等)があるか
・服務規程に従うこととされているか
・有給休暇制度があるか
・他の従業員と同様の福利厚生を受けることができるか(社宅の貸与、結婚祝金、レクリエーション、健康診断等)
・通勤手当の支給を受けているか
・他の従業員と同様の手当てを受けることが可能か(住居手当、家族手当等)
・時間外(残業)手当、賞与の制度はあるか
・退職金の支給の対象とされているか
・労働組合に加入できる者であるか
・支払者からユニフォーム、制服等が支給(貸与)されているか
・名刺、名札、名簿等において支払者に帰属しているようになっているか
・その対価の支払者以外の者からの受注を受けることが禁止されているか(兼業の禁止)
・業務に当たって、支払者側のマニュアルに従うこととされているか
・支払者の作ったスケジュールに従うこととされているか
・本来の請負業務のほか、支払者の依頼・命令により、他の業務を行うことがあるか
・勤務時間の指定はあるか
・勤務場所の指定はあるか
・旅費、交通費を会社が負担しているか
・報酬の最低保障があるか
・その対価が材料代等の実費とそれ以外に区分して請求されるか
次の場合に当てはまる場合は、事業になります。
「要件」(事業)
・支払を受ける者の提供する労務が許認可を要する業務の場合、本人は資格を有しているか(例:運送業等)
・その業務に係る材料等の在庫を自己で保管しているか
・報酬について値引き、値上げ等の判断を行うことができるか
・その対価の支払者以外の顧客を有しているか
・以前にも他の支払者のもとで同様な業務を行っていたか
・店舗を有し一般客の求めに応じているものであるか
・同業者団体の加入者であるか
・使用人を有している者でるか
・支払を受ける者がその業務について自己の負担で損害保険等に加入しているか
・業務の遂行の手順、方法などの判断は本人が行うか
・遅刻、無断欠勤の場合、それに見合う報酬が支払われないほか罰金(報酬の減額)があるか
・その対価に係る請求書等の作成がされているか
・その対価が経費分も含めて一括で請求されているか
このような基準が国税局内で保管されていて、調査担当者はこれを見ながら事実認定をしているということになります。
したがって、税理士としても、事業所得か給与所得かが争われそうだという場合には、これらの基準に照らし合わせながら、
・給与所得と認定するのであれば、なるべく給与所得よりの材料を揃える。
・事業所得として認定するのであれば、なるべく事業所得のほうによっている材料を揃えていく。
・また、「請求書を必ず出すようにしてください」、「給料日が違うようにしてください」というような助言指導などをしていく。
ということになります。
この要件項目はチェックリストとして使えるので、ぜひ行っていただければと思います。
【事業所得と給与所得の判断基準】
以上を前提として、最終的に事業所得と給与所得の判断基準について考えていきますが、あくまでも先ほどの通達は、「出来高払いの給与と請負の基準」を示すものに過ぎないので、それ以外のものについては、やはり最高裁判決に戻って認定していく必要があるということになります。
そうすると、「事業所得の要素」は次のようなものになります。
①自己の計算と危険がある
②独立して営まれている
③営利性、有償性を有している
④反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務
他方、「給与所得の要素」は次のようになります。
①指揮命令に服して労務提供している
②空間的、時間的な拘束を受けている
③継続的ないし断続的に労務又は役務の提供を受けている
これらの要素を見ながら判定していくことになると思います。
そして、具体的には先ほど見た国税局の内部資料を参考にしながらチェックをしていくということになります。
「使用従属性の判断基準(主要な判断要素)」
①仕事の依頼への諾否の自由
②業務遂行上の指揮監督
③時間的・場所的拘束性
④代替性
⑤報酬の算定・支払方法
⑥機械・器具の負担、報酬の額等に現れた事業者性
⑦専属性
【判断を間違えてしまった場合の注意点】
では、この判断を間違えてしまった場合はどうなるでしょうか。
「国税庁ホームページ(懲戒事例)」
被処分者は、関与先であるA社及びB社の消費税及び地方消費税の確定申告に当たり、従業員に対する給与について、その一部を外注費に計上することによって、消費税及び地方消費税額を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成した。
これは、給与を外注費に計上してしまった、ということで税理士業務の禁止の処分がされた事例です。
税理士業務の禁止というのは、税理士登録抹消処分をされて、処分日から3年を経過する日まで資格がとれないという大変重い処分になります。
「税理士法」
第45条(脱税相談等をした場合の懲戒)
1.財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、2年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
故意にされる先生はいらっしゃらないかと思いますが、第2項では不注意によって、つまり過失によって行った場合も懲戒事由になっているので、ご注意いただきたいと思います。
【税理士に対する損害賠償の問題】
そしてまた、税理士に対する損害賠償の問題もあります。
給与と認定すべきものを外注費として処理したということで、後日の税務調査で否認されたとなると、消費税、源泉所得税、加算税、延滞税、重加算税の不利益が出ることになります。
特に、加算税、延滞税、重加算税などで、税理士に損害賠償請求がくるという可能性があります。
従って、損害賠償を防ぐためには、まず顧客に対して税理士として説明助言をしておく必要があります。
・外注費として認められるための要件(裁判例や通達の要件)を示して、説明をしておく。
・本件では要件を満たさない可能性を説明しておく。
・将来の税務調査で、これが否認され、給与認定された場合には追加の納税(消費税、源泉所得税等)や附帯税(加算税、延滞税、重加算税等)がかかるという不利益説明もしておく。
・説明をしたことの証拠化をしておく。
事業所得か給与所得か判断に迷う、外注費と認定できそうだけれど給与等として認定される可能性ある、というような場合には、これらの証拠を残しておくということが必要になるかと思います。