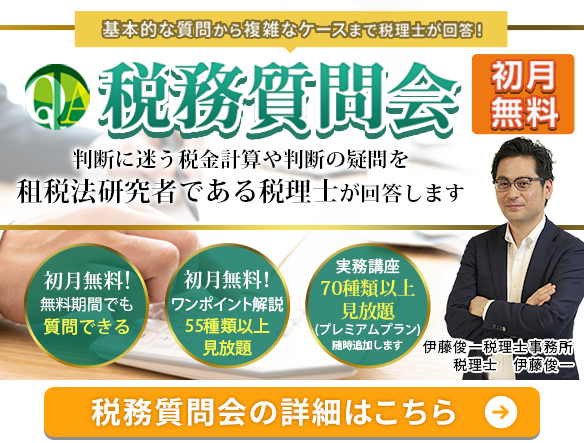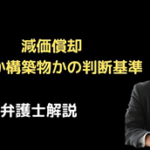【前提】
(1)現在の状況
・A社 → B社 → C社(いずれも100%関係)
・B社はC社を買収(株式取得)する目的で設立されたSPC。
(2)合併の形態
C社はEC取引を行う法人であり、Amazonやその他ECサイトでの販売業者ステータス(優遇措置など)を維持するため、C社がB社を吸収合併する形式を採用(株式以外の資産の交付はなし)。
結果として、A社 → C社(100%)の関係となります。
(3)留意点
C社の役員である甲氏に新株予約権(ストックオプション)を付与予定(発行済株式の5%未満)。付与の時期は合併前後いずれか未定。
【質問1】
本件合併は、法人税法第2条第12号の8、法人税法施行令第4条の3第2項に定める
①株式以外の資産を交付しない
②完全支配関係が継続する
以上の要件を満たすため、適格合併と判断しています。
また、甲氏に新株予約権を付与し、権利行使された場合でも法人税法施行令第4条の2第2項第2号ハに該当し、甲氏の持株は完全支配関係の判定から除外されるため、②の完全支配関係に影響はないと考えています。
・この理解に問題はないでしょうか。
・また、ストックオプション制度を採用する時期については、合併前後いずれであっても適格合併の判定に影響しないという理解でよいでしょうか。
【質問2】
組織再編の経験がなく抽象的な質問となりますが、ストックオプションの形態として一般的に税制適格が多いのかを伺いたいです。
書籍(『ストックオプションの活用と実務』P156、税理士法人AKJパートナーズ)には、通常は税制適格要件を満たす形で発行されると記載されています。ただし、証券会社等を保管委託先に指定する必要があるなど、中小企業にはハードルが高いようにも感じています。
可能であれば、このようなケースで一般的に適格・非適格をどのような要素をもとに判断するのか、ご教示いただければと思います。
【参考:規模感】
・B社:現預金 1,500 / 関係会社株式 160,000 / 固定負債 145,000 / 資本金 21,000 / 利益剰余金 △4,500
・C社:一般事業会社のため詳細は割愛。ただし合併によりB社の関係会社株式160百万を自己株式として処理(企業結合に関する適用指針210~212項に基づき簿価振替)しても、繰越利益剰余金がマイナスとならない程度の利益剰余金を保有。