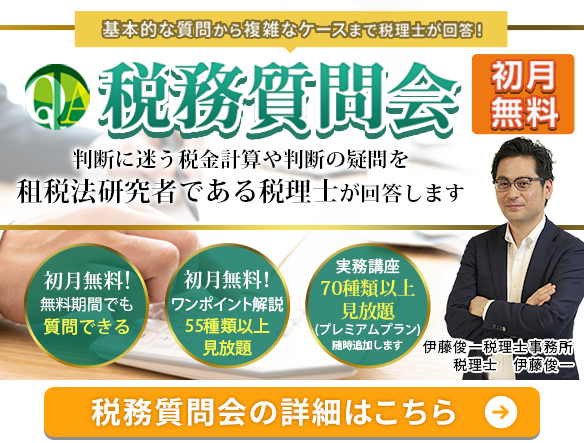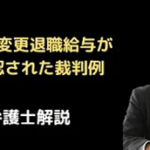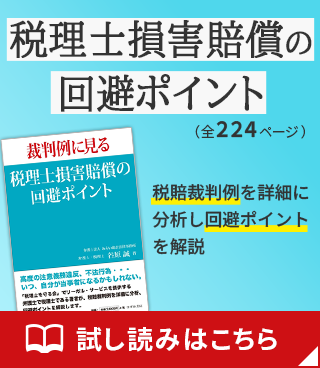令和4年12月決算により、令和4年12月末を解散日とした会社があります。令和5年2月末までに解散申告を行う予定で、2月7日に官報公告を出し、その後「残余財産の確定」を4月末頃と想定し、清算申告の提出は5月末までを予定しています。
12月末時点の会社の状況としては、預金はほとんどなく、負債はわずかな役員借入金のみであり、売上はなく繰越欠損金がある状態です。
解散清算申告について実務経験がなく、以下の点を確認したいです。
このような場合、「残余財産確定時」までに司法書士や税理士への報酬支払や源泉所得税の納付を済ませておく必要があるのか、という点です。
残余財産は最終的にゼロになる予定であり、残余財産確定時の貸借対照表のイメージとしては、現金〇〇万円、未払法人税(均等割)〇〇万円、資本金〇〇万円、利益剰余金△〇〇万円(資本金と同額)を想定しています。
会社に預金がないため、社長が資金を入れて会社預金から支払うか、社長立替で支払うかのいずれかとなります。いずれにしても役員借入金として計上され、その後債務免除をしない限り債務超過が解消されません。ただし、債務免除益が発生しても繰越欠損金が多額にあるため法人税は発生しないと考えています。
なお、参考として「解散・清算の実務(大田達也)」のP82には以下の記載があります。
残余財産の確定の日の時点では、BS上、現金預金や未払金などが残っていて、すべての科目の帳簿価額が0になっているわけではない。税務署に提出する最後事業年度(残余財産の確定の日に終了する事業年度)に係る確定申告書に添付するBSは、この現金預金および未払金などが残っている内容で問題ない。
この記述を踏まえつつ、残余財産確定時に役員借入金や預り金が残っていることが問題となるかどうかを確認したいです。
また、期中に報酬や源泉所得税を立替等で支払ってもらい、その分を役員借入金として計上し、最終的に債務免除を行った上で、残余財産確定時には均等割納付分だけを預金に残しておく形がよいのでしょうか。
仮に預金がない場合には、均等割額相当を「現金/役員借入金」で仕訳し、残余財産確定時までに役員借入金を債務免除する方法をとるべきかとも考えています。
実務的な処理の流れについて明確に整理できず、ご意見をいただきたいです。