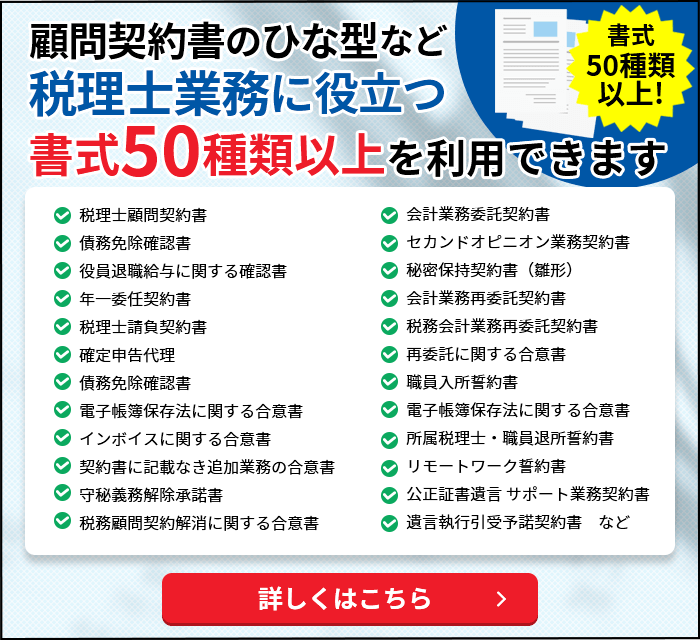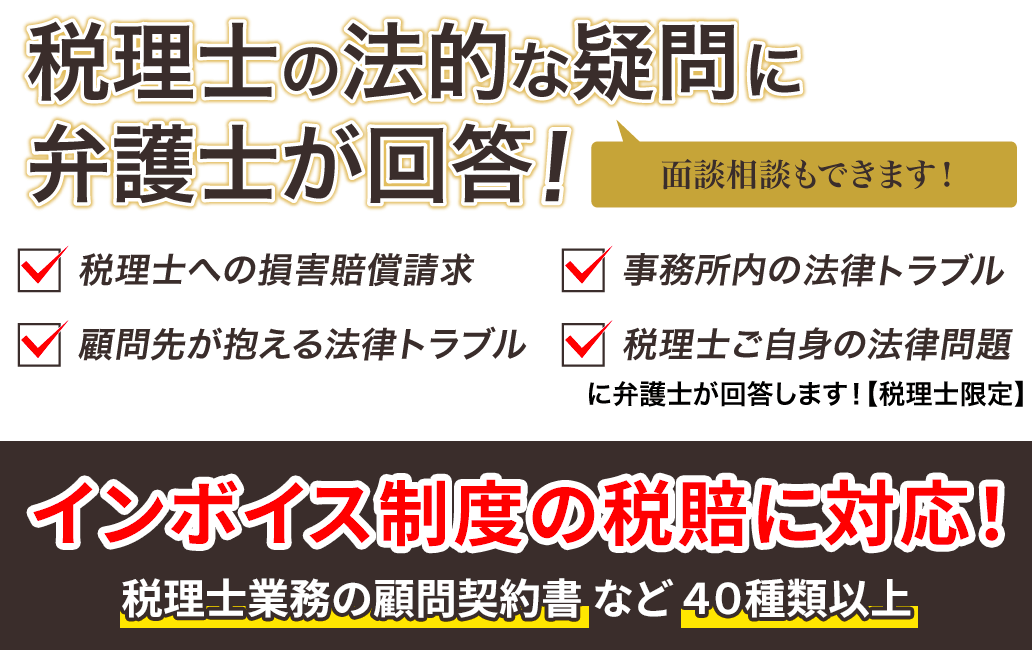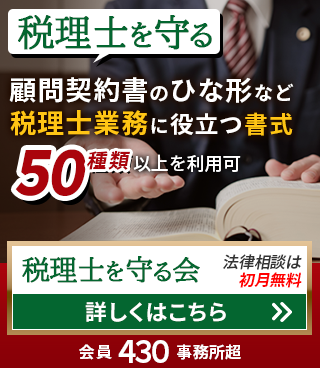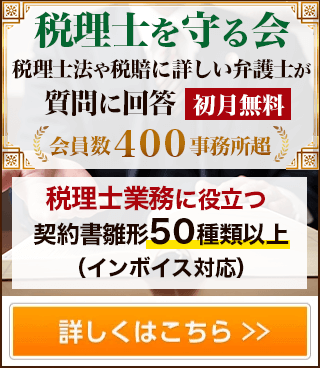解雇・退職に関するトラブルは、労使紛争の中でも最も経営者の頭を悩ますものと言えるでしょう。
解雇した社員が解雇無効を訴え裁判を起こしたり、在職中は真面目に働いていた社員が退職後、弁護士名での内容証明郵便を会社へ送付し未払い残業代を請求するなど問題が長期化し、数百万円あるいはそれ以上の多大な代償を支払うケースもあり、体力のない中小企業では最悪の場合「倒産」に追い込まれることもあるからです。
ある会社で、入社数ヵ月の社員を解雇しました。
この会社では過去にも何名か解雇予告手当を支払うなどして解雇したことがあったそうですが、幸いにも大きなトラブルが起きたことは無かったようです。
ところが今回解雇した社員は外部ユニオンに加入し、会社と争う姿勢を示しました。
また、過去に何度か裁判や労働審判を経験しているにもかかわらず、何ら対策を取っていない経営者を他士業から紹介され、就業規則や給与規程の改定作業を行ったこともあります。改定中に紛争が起きないかとヒヤヒヤしたものです。
解雇や退職トラブルが発生すると、会社が無傷で済むことは滅多にありません。
リスクヘッジのためには労働基準法や労働契約法、裁判例を理解しながら就業規則や労働条件通知書等を整備し、適切な運用をしていくほかないでしょう。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
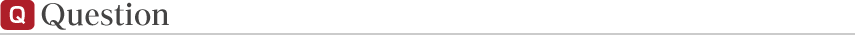
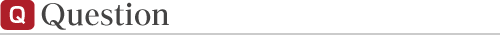
「解雇予告は、30日以上前にしなくてはならない」とよく聞きますが、どのような手続きを踏むのが法的に正しいでしょうか?
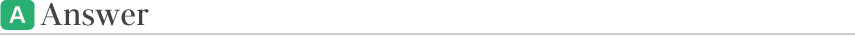
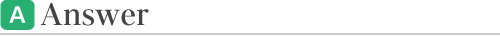
法的にいえば、解雇予告は口頭で伝えても、書面で伝えてもよいことになっていますが、労務トラブル回避という観点でいえば、言うまでもなく、書面を交付して行うのが適切です。
口頭で行った場合には、解雇予告そのものがなかった、あるいは、解雇予告をされた日付が違うなど、紛争が起きても証明することが難しくなる可能性があります。書面には解雇年月日や解雇事由を記載することが一般的です。
解雇予告は、少なくとも30日前に行わなければなりませんが、解雇予告した日は含まれません。例えば7月31日に解雇するのであれば、少なくとも7月1日に解雇予告をする必要があります。
もし、30日前に解雇予告をしないのであれば、30日分以上の平均賃金による解雇予告手当の支払いをしなければなりません。そしてその支払いは、遅くとも解雇する日までに行って下さい。
実務では、会社が解雇予告手当を支払ったこと、被解雇者が解雇予告手当を受領したことを明確にするため「支払通知書」を交付し、「受領通知書」を被解雇者である社員から取得することが望ましいと思われます。
その他の注意点として、「業務上の負傷や疾病による休業期間とその後30日間」「産前産後休業期間とその後30日間」は原則、解雇することができません。
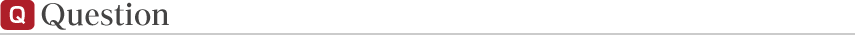
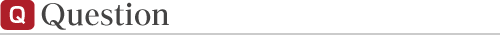
社長に対して反抗的な態度をとる社員がいます。社内の雰囲気が悪くなるので、できれば解雇したいのですが、これは解雇の理由になるのでしょうか?
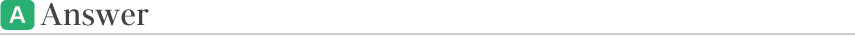
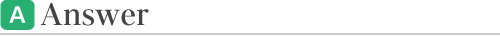
解雇には、協調性がなかったり、勤務態度が不良であったり、能力不足と判断された社員を解雇するような場合をいう「普通解雇」と、企業秩序違反により解雇する場合をいう「懲戒解雇」があり、ご質問のケースでは普通解雇を検討することになるかと思います。
労働契約法第16条には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」と規定しています。
解雇が有効となるのか、それとも無効となるのか、具体的には次のような事項を一つずつ確認し判断していくことになります。
①就業規則に規定している解雇事由に該当するか(該当性)。
②当該解雇が社会的にみて重きに失することはないか(相当性)。
③注意・指導するなど、社員に対し改善を促すような機会を設けたか。
④社員を配置転換するなど解雇を回避するための努力を行ったか。
⑤解雇予告などの手続が、労働基準法の規定に沿った形で適正に行われているか。
以上を踏まえると、社長に反抗的な態度を取る社員の解雇は極めて困難であると言わざるを得ません。
仮に、貴社就業規則に「社長に反抗的な態度を取った場合には解雇とする。」というような規定があったとしても、それをもって解雇とするにはあまりにも重すぎると判断されるでしょう。得策とはとても言えません。
現実的には、注意・指導を何度か行い(書面により記録を残すこと)、改まらないようであれば警告書を発し、それでもダメなら懲戒処分そして最終的に解雇を検討するという長期的な対応が必要です。

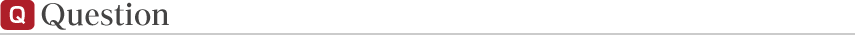
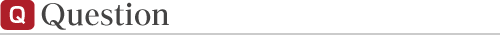
今期の売上が落ちているため、社員を解雇しないと、危機を乗りこえられそうにありません。このようなケースの解雇は、どのような手順で進めればよいでしょうか?
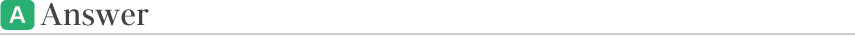
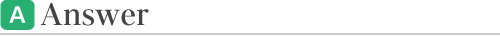
経営不振による解雇を実施する場合、通常「整理解雇」と言われ、普通解雇の一つになりますが、過去の判例・裁判例からも明らかなとおり、その実施には厳しい制約があります。
具体的には「整理解雇の四要件(四要素)」というもので、次の4つになります。
①人員の削減について経営上の必要性があること。
②解雇を回避するための努力を尽くしたこと。
③解雇される者の選定について合理性があること。
④解雇の手続きについて相当性があること。
整理解雇を行う会社の状況や規模も様々であるため、この四要件が厳格に適用されなければ「解雇は無効である」とは必ずしもなりませんが、現実的にはこの要件に沿う形で進めていくことになります。
当事務所が対応した例では、業績不振により会社の中核部門を閉鎖しなければならず、整理解雇に踏み切ったというものがあります。
役員報酬や社員の給与を減額したりコストカットに努めたものの業績は上向かず、また、中小企業であるため人員を他の部門へ配転させるようなこともできず、経営者は決断せざるを得ませんでした。
会社説明会を行うとともに、退職金の上乗せ支給を実施するなどこの企業規模で可能な限りの対応をしたこともあり、大きなトラブルは起こらずに乗り切ることができたのです。
それとは対照的に、会社が無くなることを1週間前に突然社員に発表した会社があり、その後会社と社員でトラブルが発生したことは言うまでもありません。
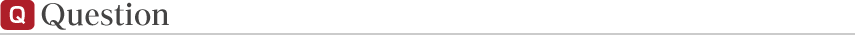
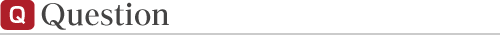
試用期間中の社員の言動に問題があり、解雇したいと考えています。試用期間中であれば、会社は自由に解雇しても大丈夫なのでしょうか?
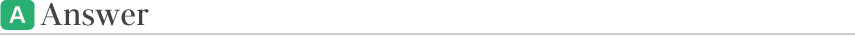
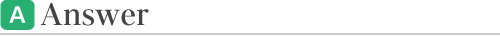
試用期間とは勤務態度や能力、協調性など自社への適性を見極めるための期間であり、本採用となった場合に比べれば解約権の行使が認められやすい傾向にあります。
それでも解雇であることには何ら変わりがなく、社員の言動がどのようなものかは分かりませんが、労働契約法第16条(Q32参照)に留意した上での慎重な対応が求められます。これまで再三申し上げてきましたとおり、就業規則や労働条件通知書を改めて整備したり、能力不足や勤怠不良社員に対する注意・指導・教育の記録を残しておきましょう。
なお、労働基準法では、解雇予告や解雇予告手当なしで解雇できるのは「試用期間中の者」であり、かつ、「採用後14日以内」であることと定められており、14日を超えてから解雇する場合は、解雇予告や解雇予告手当が必要になります。
もし、採用後14日以内であっても、就業規則や労働契約等において試用期間に関する事項が定められていない場合は、解雇予告及び解雇予告手当の支払い義務が生じますので注意して下さい。
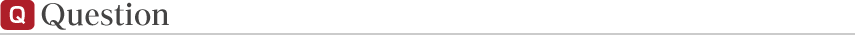
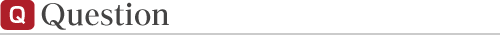
法的に問題のない手順を踏んで、リストラを進めるという先生のお話は頭では理解できます。
しかし、この手順を踏んでいるうちに、このままでは会社が倒産に追い込まれてしまいます。合法的かつ、速やかにリストラを進める方法はないでしょうか。
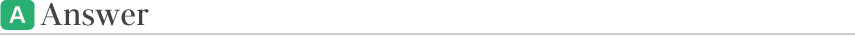
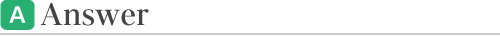
整理解雇について説明したとおり、その実施には厳しい制約があるため、ある程度時間をかけ、慎重に進めていかなければなりません。
そうは言っても倒産しては元も子もないので、リストラによるコストカットは喫緊の課題であろうと思います。
そうであるならば、「退職勧奨」か「希望退職制度」を検討することになるでしょう。
似たような制度に「早期退職優遇制度」がありますが、これは業績の良し悪しに関係なく行われる(若返りを図るなど人事政策的に行われる)こともあり、退職金についても相応の額が上積みされて支給されるのが通常です。
ある外資系の会社では決算で大幅な黒字が見込まれるときに組織を活性化させるため、早期退職優遇制度を行っていたりします。
退職勧奨や希望退職制度を実施するメリットは、社員が退職の勧奨に同意したり、希望退職制度に応募するのであれば、最終的には合意解約となるので整理解雇と比較しても紛争発生の可能性が低くなることです。
もし、希望退職制度への応募者が少ない場合は、引き続き退職勧奨が行われます。
もっとも、早期退職優遇制度ほどではないにせよ、希望退職の応募者にも一定の退職条件を提示するので、それが難しいような企業規模が小さい会社であれば、希望退職制度を経ずにいきなり整理解雇とすることにも合理性があると言えるでしょう。
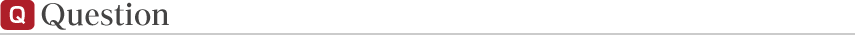
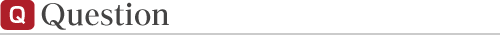
今まで技術職だった社員を営業職に配置転換することは、訴訟に発展した時、事実上、退職を迫ったことになるのでしょうか?
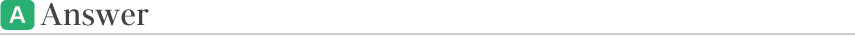
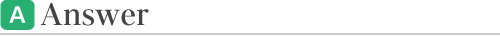
雇用契約等により職種が限定されている場合、配置転換は本人の同意がなければ実施できません。
そのような職種の限定がないのであれば、配置転換は可能です。
もっとも就業規則に、「会社は、業務上必要ある場合に、配置換えや転勤を命ずることがある。」というような規定を明記しておかなければなりません。この条項により本人の同意なく配置転換をすることができるようになるのです。
以上から使用者の「配転命令権」はかなり広く認められていると言えるでしょう。
ただし、大企業で問題になっている追い出し部屋のような極端な環境をつくり、パワハラによって退職を迫るような言動を行ったりすると、「職種の変更は退職に追い込むための措置」と捉えられ、いわゆる人事異動が配転命令権の濫用として無効となる可能性があります。
裁判になれば損害賠償請求も認められるかも知れません。
過去の判例でも、次のような場合は配転命令権の濫用であるとしています(東亜ペイント事件=最二小判昭61・7・14)。
①業務上の必要性がない場合
②不当な動機や目的による場合
③通常甘受すべき程度を著しく超える不利益であるもの
これらから、例えば家族が重い病気を抱えているにもかかわらず、転居を伴う(その結果、別居となる)配転を行ったり、最初から退職させることを目的として配置転換をしたことが明らかであるような場合は、無効とされる可能性が高いでしょう。
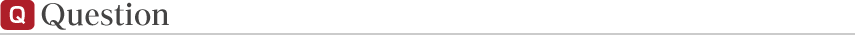
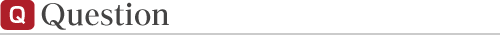
事業拡大により、創業当初は本社だけだったこの会社も、各地に支店ができるようになりました。本社しかなかった当時からいる社員を、新しくできた他の支店へ転勤させることはできるでしょうか?
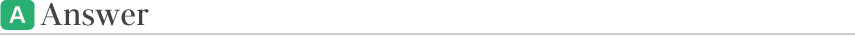
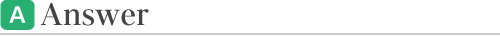
雇用契約書や就業規則の内容、採用の経緯(例えば現地採用であることが求人募集に記載されていたような場合)等により、勤務地限定の合意があることが明らかであれば、本人の同意のない配置転換はできません。
しかし、そのような合意もなく、就業規則にも転勤に関する条項が明記されているのであれば、社員は会社の配転命令に従わなければなりません。
「採用時の労働条件通知書には、就業の場所として○○支店(東京都○○区××町△ー□)と記載してあるので、転勤はさせられないはずだ!」と主張してくる方がいますが、それは当初の就業場所を明記しただけであって、勤務地が限定されていたという解釈には無理があります。
過去の裁判例でも多くの場合、否定されています。
就業規則が万全な状態であれば心配はないと思いますが、それでも無用なトラブルを防止したいのであれば、社員に労働条件通知書を交付する際、「事業が拡大すれば、将来的な転勤の可能性もある。」というような説明を加えることです。
さらに慎重かつ万全を期すのであれば、労働条件通知書に追記するのが良いでしょう。
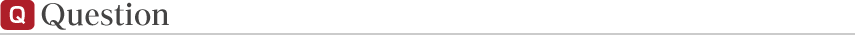
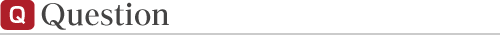
当社では、自己都合により退職する社員に対し、必ずしも退職届の提出を求めていませんでした。トラブルが起きたこともなかったので、できれば今までどおりの運用をしたいと思っています。問題ないでしょうか?
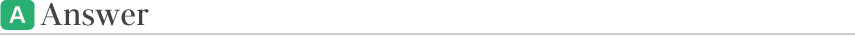
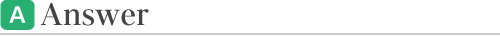
中小企業ではいまだにそのような運用をしているケースも珍しくありませんが、直ちにその運用を改め、退職届を取得するようにして下さい。
退職時のよくある労務トラブルに雇用保険の離職票(離職証明書)に関するものがあります。具体的には、会社側は「自己都合退職」として処理したものの、後日、退職者が離職票をハローワークへ持参し失業給付の手続きをしようとする際、本当は「会社都合退職」であると主張する場合が典型的な例です。この場合、ハローワークから事実確認の電話が会社に入りますが、処理に間違いがなければ「離職票に記載のとおりです。」と回答することになります。
別のケースでは、このようなこともありました。ある日「退職する」と口頭で言ってきた社員がいたので、会社は退職処理の準備を行いました。後日、その社員に「退職に関する諸手続きについて説明をしたい」と伝えたところ、「退職するなんて言っていない」と一言。
これらのケースからも明らかなとおり、退職届は絶対に提出してもらわなければなりません。書面として残りますし、退職日や退職事由(通常は、「一身上の都合」になるでしょう)が明確になりますから。会社の勧奨により退職する場合も同様の対応が必要です。
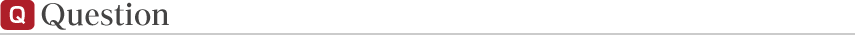
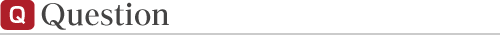
退職する社員から「残っている有給をすべて消化してから退職したい」との申し出がありました。これは認めざるをえないのでしょうか?
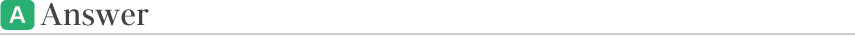
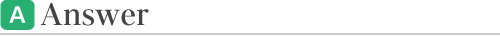
これもご相談を受けることが多いのですが、結論から言いますと、このようなケースでは認めるしかありません。
しかしながら付与された有給(年次有給休暇)については、2年の消滅時効が認められていますから(昭和23・12・15基発第501号)、就業規則で有給の付与日数を「労働基準法どおり」と規定している会社だと、退職時に最大で40日の有給が残っている社員がいる場合があります。
ということは、40日の有給をすべて消化して退職するのであれば、約2ヵ月近くもの期間、実際には勤務していないのに、その分の給与を支払わなくてはなりません。あわせて、会社はこの間の社会保険料等についても負担する義務があります。
そこで実務では、残っている有給を退職時に買い上げるという方法を取ることがあります。有給の買い上げは原則としてできませんが、退職時に買い上げることについては違法とされていないからです。
ただし、有給を買い上げるのであれば、次のような点に注意をして進めて下さい。
①有給の買い上げを社員に無理にすすめることはできないので、同意を得ること。
②買い上げ金額の単価について特に制限はないため、会社が任意に決定することができる。
もっとも、普段から社員が積極的に有給を取得できるような環境(半日有給や時間単位の有給制度を導入したり、有給の取得率目標を設定したり、管理職から率先して取得するようにする等)を整えることが、経営者の重要な責務であろうかと思います。

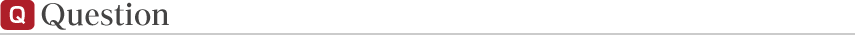
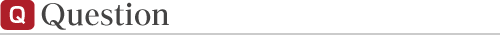
長年、貢献してくれた社員が親の介護のため退職することになりました。「すぐに失業保険が下りるので、退職理由を会社都合にしてもらえないか」との相談を受けたのですが、認めても良いでしょうか?
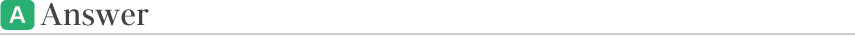
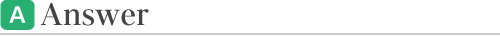
違法行為であり、会社が罰せられる可能性もあるため認めてはいけません。
厚生労働省の発行している冊子にも「事業主の方が離職理由について虚偽の記載を行った場合、偽りその他不正の行為をしたものとして、そのような虚偽の離職理由に基づき不正に受給した者と連帯して不正受給金の返還・納付命令(3倍返し)の対象となるとともに、詐欺罪等として刑罰に処せられる場合があります。」とハッキリ明記されています。
「貢献度が高かったから」「よく頑張ってくれたから」というような経営者の思いだけで社員の要望に応じても、会社のメリットは何ひとつありません。
また、御社がもし、現在公的な助成金を受けている、あるいは今後受けようかと検討しているのに会社都合による退職者が出てしまうと、助成金を返還しなければならなくなったり、当面の間、新規の申請ができなくなったりすることもありますので注意が必要です。
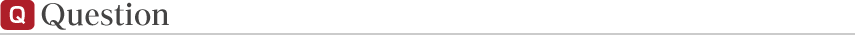
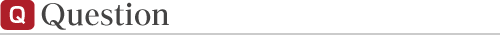
入社したばかりの社員が突然、無断欠勤するようになり扱いに困っています。お恥ずかしい話ですが、年に数名、このような無断欠勤をする社員が出てしまいます。この場合、どのような対応をするのが一般的でしょうか?
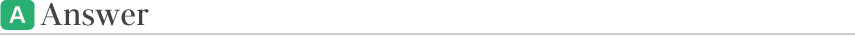
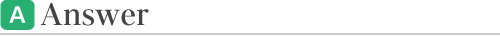
通常、無断欠勤は就業規則の懲戒事由として規定していると思います。譴責・戒告や減給等、どのような処分を下すかは就業規則の規定に沿って実施することになりますが、もし、無断欠勤が初めてだったような場合は懲戒処分とはせず、単に口頭での注意のみにとどめることもあるようです。
ただ、正当な理由がなく、「数回無断欠勤したときは……」のように1回程度では懲戒処分としない規定でもないのであれば、口頭注意ではなく、懲戒処分とするべきです。無断欠勤が断続的、あるいは連続的に行われると経営者は解雇という選択を視野に入れるようになりますが、それまでの過程で譴責等の処分や注意をしていない場合がよくあります。
これでは解雇をしても無効とされる可能性が高くなります。一番やってはいけないのは何ら対応をせず、放置するということなのです。
解雇する場合、原則として解雇予告や解雇予告手当の支払が必要となりますが、「労働者の責に帰すべき事由」であって、労働基準監督署の認定を受けた場合には、その適用が除外されます。
「労働者の責に帰すべき事由」の具体的なものとして、通達では例えば次のような基準が挙げられています。この通達や裁判例からも明らかなように、出勤の督促や注意はその都度必ず行うとともに、譴責等の処分を段階的に行っていくようにして下さい。
①「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。」
②「出勤不良又は出欠常ならず、数回に亘って注意を受けても改めない場合。」
(昭23・11・11基発1637号、昭31・3・1基発第111号)
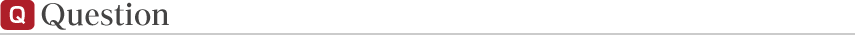
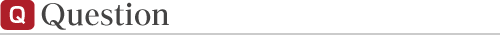
店舗スタッフが突然、退職したいという書き置きを残して出勤しなくなりました。店舗の鍵と制服を返却してもらっていないため困っています。どのように対処すべきでしょうか?
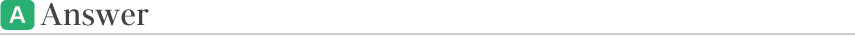
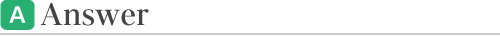
飲食業や美容業のように店舗を構え、複数の社員やアルバイトが店舗の鍵をもっている業態では、このような問題がよく発生しています。社長や店長は当然連絡を取ろうと試みるのですが、全く連絡が取れなくなります。
状況によっては事故や事件に巻き込まれた可能性も考えなければなりませんが、突然出勤して来なくなる場合は「もうこの店(会社)では働きたくない」というものがほとんどです。
会社側としては退職するのは一向に構わないが、退職日を確定させ退職処理もしたいし、それ以上に店舗の鍵を速やかに返却してもらいたいと思っています。
そこで、「携帯電話に連絡する」「メールをする」等の対応をしても連絡が取れないならば、留守電メッセージや郵便物を通して、「○月○日までにご連絡いただけない場合、防犯上の問題から警察に連絡することもありえます。
また、仕方なく店舗の鍵を全て交換するようになれば、身元保証人等を通じて交換にかかった実費を請求することもあります。速やかに返却してほしい」と伝えると、よほどのことがない限り返却してきます。
鍵のような返却する物が特になく、行方不明になっていて連絡がつかないような場合は解雇を検討することになりますが、解雇は会社が解雇をするという意思表示が相手方に伝わらなければなりませんから、簡易裁判所に対し公示送達という手続きを取ることになります。
しかし、手続きが煩雑で時間もかかるため、実務上では解雇ではなく、就業規則の退職事由「会社に連絡がなく、○日を経過しても、なお所在が不明な場合」という条項を適用することになるでしょう。
「○日を経過しても」の○日がどの程度であれば妥当かと言えば、30~50日程度でしょう。
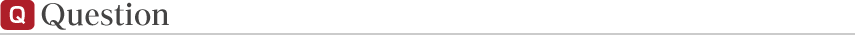
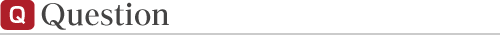
弊社の就業規則では、定年年齢は60歳と定められています。最近、定年間近の社員から、「法律で65歳まで退職年齢が延長されたはずだ。まだまだ働き続けたい」との申し出がありました。これは認めるべきでしょうか?
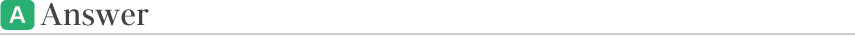
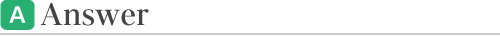
これまで定年制のある会社では、高年齢者雇用安定法により「定年の引上げ」「継続雇用制度」「定年制の廃止」のいずれかの措置を講じなければならず、多くの会社が継続雇用制度の一つである「再雇用制度」を採用してきました。
したがって、定年年齢が就業規則で60歳と規定されていても、何らかの措置を取っていなければならないため、就業規則や労使協定の内容を改めてご確認下さい。もし何も対応してきた形跡がないのであれば、至急、改善措置を講じて下さい。
貴社と異なり3つの選択肢の中からいずれかの措置を講じてきた会社で継続雇用制度を採用している場合であっても、平成25年4月1日施行の改正法により、次の例外を除き原則として希望者全員を65歳まで雇用確保しなければならなくなりました。
①解雇事由に該当する場合
②退職事由(年齢以外のものであること)に該当する場合
③経過措置(平成37年3月31日までの間)に該当する場合
①及び②に該当する場合は継続雇用する必要はありません。③は老齢厚生年金の報酬比例部分の受給が可能となる年齢の者は、これまでどおり労使協定で定めた再雇用の基準により判断できるということです。
なお、「再雇用の基準」としては「直近3年間の人事考課の結果がB評価以上の者」「直近の出勤率が80%以上の者」「定年退職後も引き続き勤務を希望する者」のような例が挙げられます。
中小企業や定年到達者が当面出そうもない若い会社は、改正高年齢者雇用安定法への対応どころかこういう法律があったこと自体知らないということが多く、将来的なリスクを背負ったまま企業経営をしていると言えるでしょう。
再雇用制度を採用している会社であっても、雇用保険の高年齢雇用継続給付等を知ってか知らずか全く活用せず、再雇用後も定年前と同額あるいは同程度の賃金を支払っている場合があり、余計なコストを負担しているのを非常にもったいなく感じます。