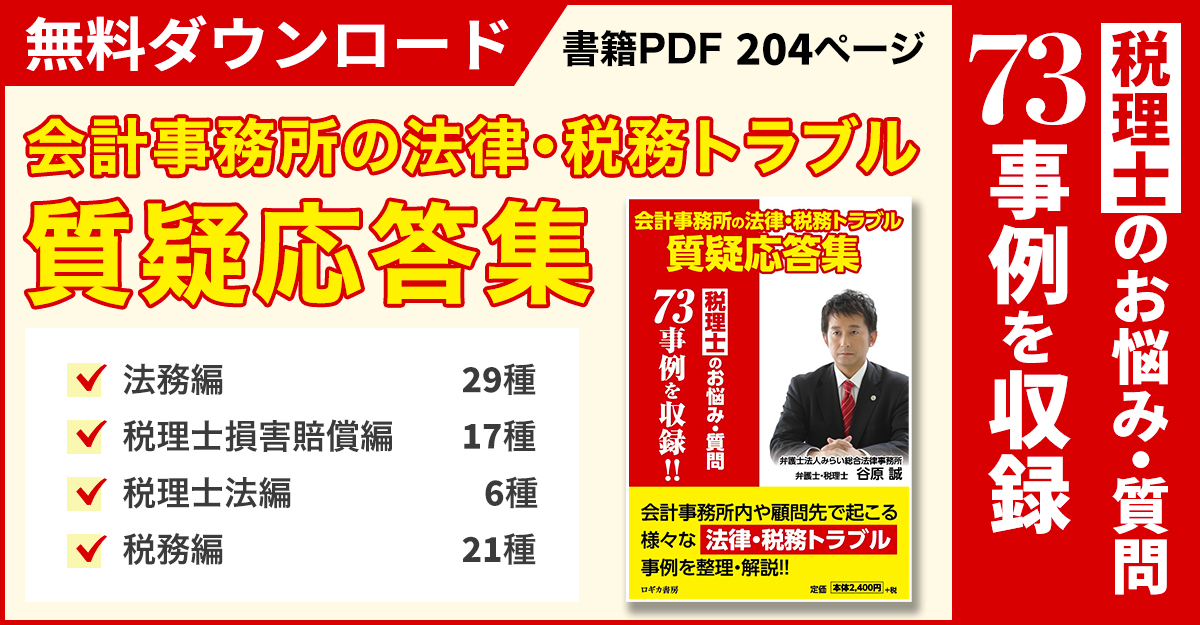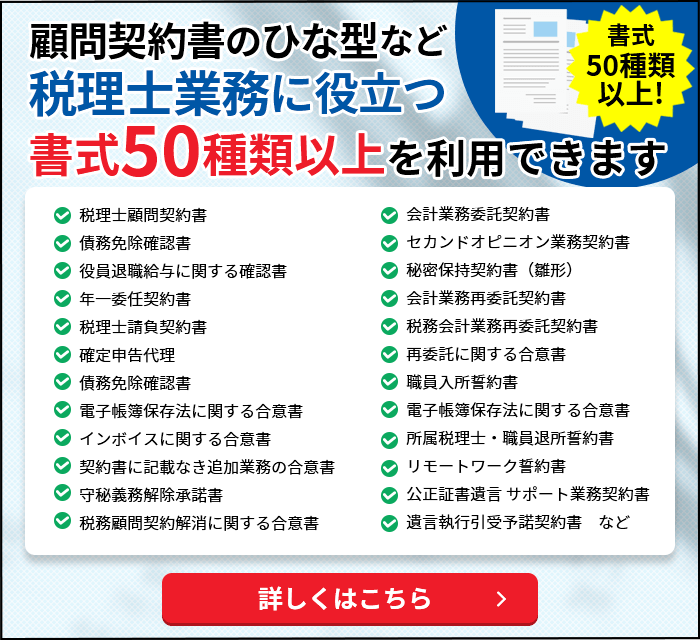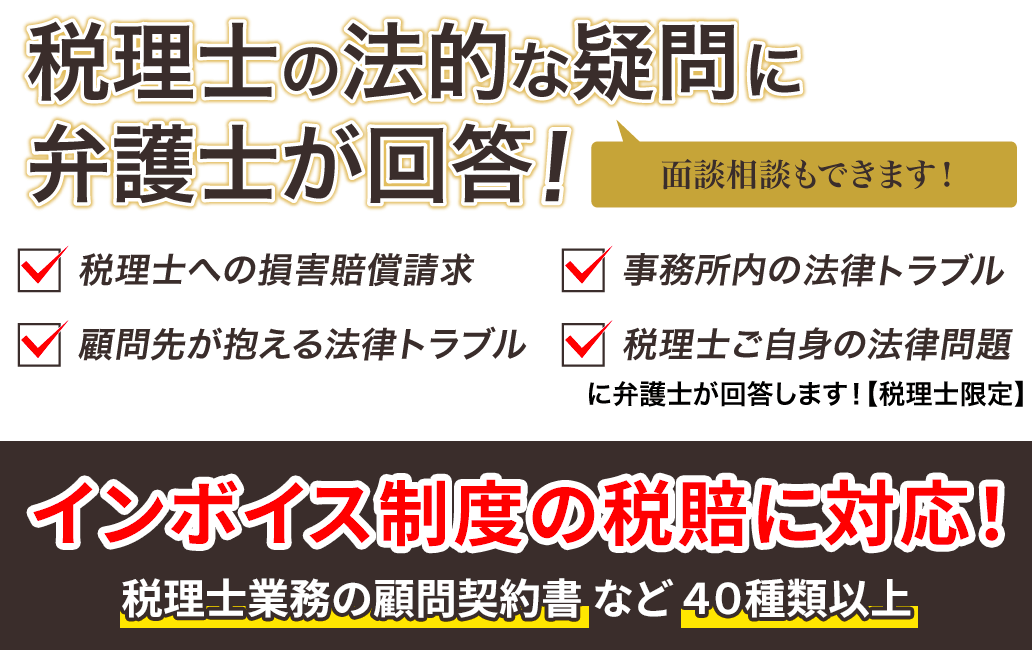税理士の先生より「協業組合の自己株式の取得の可否」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
協業組合は自己株式を取得できますか。
できない場合は、既存組合員が買わざるを得ないのでしようか。
回答
協業組合は、「中小企業団体の組織に関する法律」(以下、「法」といいます)に規定する協業組合であることを前提として検討します。
また、協業組合は株式を発行しませんので、自己株取得ではなく、「協業組合が組合員の有する持分を取得することができるか」というご質問として理解したいと思います。
同法には、自己持分の取得に関する条項はありません。
また、法 5 条14の 4 項は、協同組合法17条 2 項から 4 項を準用しています。
協同組合法171条 2 項は、「組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。」とされています。
協業組合は、「組合員」ではありませんので、持分を譲り受けるには、加入しなければなりませんが、協業組合は、加入し、組合員になることはできません。
したがって、・・・
この記事の全文については、税理士を守る会に入会すると読むことができます。