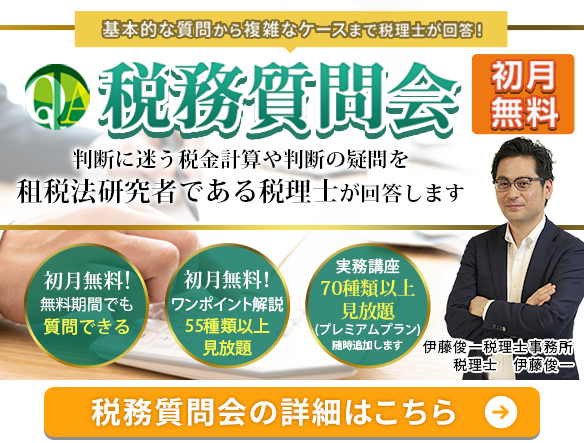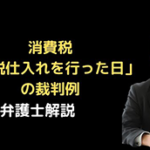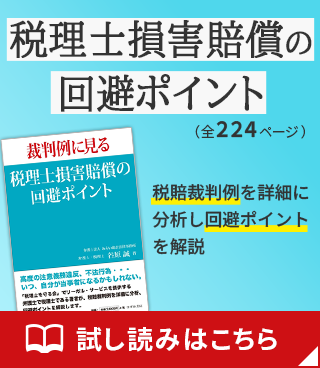A法人はサービス業を営む同族会社で、資本金は3,000万円です。
株主構成は社長aが84%、aの母が16%を所有しています。
相続税の類似業種比準価額区分では「大会社」に該当しますが、相続税評価による純資産価額(第5表)はマイナス20億円となっています。
会計上も15億円の債務超過であり、法人税別表7の繰越欠損金は13億円です。
金融機関からの借入24億円はリスケジュール債務ではありません。
コロナ規制解除後、売上はコロナ前の18億円規模に回復し、利益も約5,000万円を計上できる見込みです。
今後、aの叔母Bから5億円の資金援助を受けることを検討しています。
① 当初は、叔母Bによる無議決権・配当優先株式の引受けによる増資を予定していましたが、A法人が債務超過であるため、配当ができないことを弁護士から指摘されました。
債務超過は、
・相続税評価上のマイナス20億円の解消には約10年
・会計上のマイナス10億円の解消には約5年
を要する見込みですが、確実ではありません。
そこで弁護士より、最初の5年間は無配当とし、6年目以降に5年分を補うような高配当の無議決権優先株式を発行してはどうかという提案を受けました。
ただし、6年目以降も債務超過が解消されていない可能性があり、配当不能リスクが残ります。
また、5億円増資後も相続税評価額がマイナスのままであれば、株主間の「みなし贈与」問題は生じないと考えています。
出資者Bも個人であるため、寄付金課税の対象にもならないと思われますが、この点に課税上の問題はあるでしょうか。
② さらに、個人Bが1株10円・5,000万株の無議決権種類株式を引き受けた場合、課税上の問題は生じるでしょうか。
③ 上記のように増資したのち、期末までに5億円の無償減資を行った場合、税務上の問題は生じないと考えてよいでしょうか。