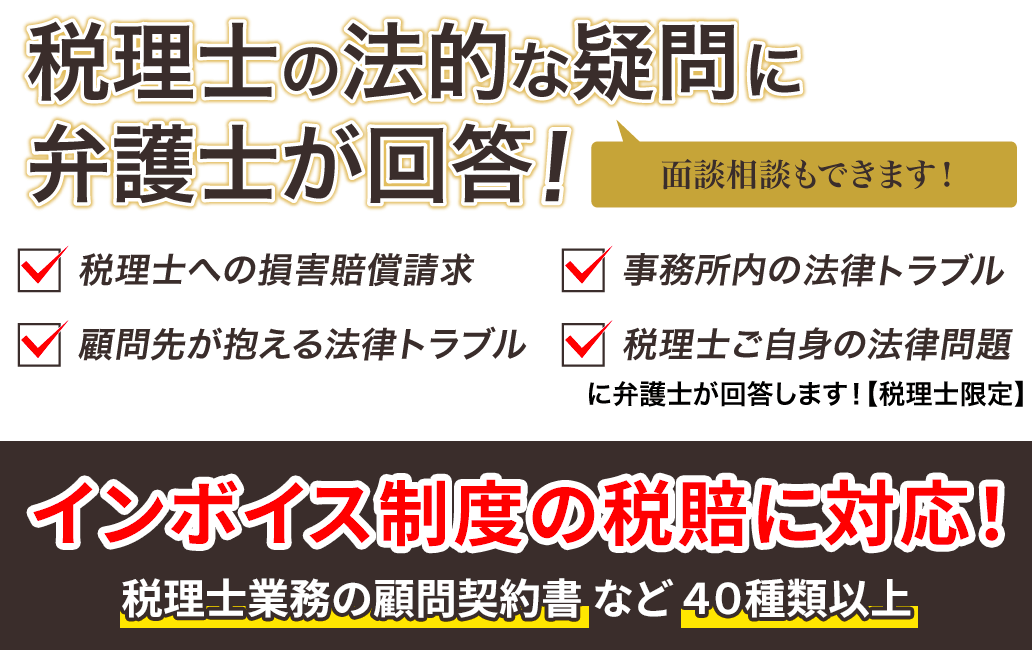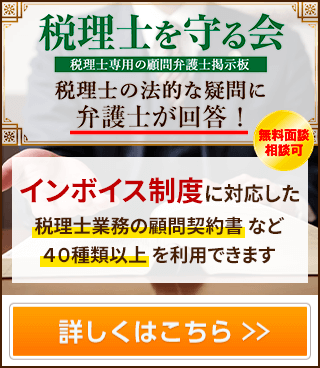執筆:弁護士・税理士 谷原誠
今回のテーマは、税理士に対する損害賠償について、その賠償額の上限規定についてです。
【損害賠償の制限条項】
税理士が依頼者に対して損害賠償債務を負担する場合に、「その賠償金を払いますが、いくらにしてください」というように、損害賠償額の上限規定を行う際に、その契約条項が有効となるのかどうかについて、まず考えていきます。
よく、「有効か、無効か」という話がありますが、少なくとも法人や事業者と税理士との関係は対等な当事者関係ということになるので、原則として有効というように考えていただいて結構かと思います。
例えば、次のような条項の例はどうでしょうか。
「乙が甲に対し、故意又は過失による損害賠償債務を負担する時は、その賠償額の上限は、甲が乙に対して支払った当該行為があった年の年間報酬額を上限とする。」
これは、必ずしも年間報酬額を上限としなくても、年間保証額の2年分でも良いですし、「金100万円を上限とする」というような書き方でも良いです。
ただし、あまりに金額が低いと無効になりやすいので、払えるような金額の少し高めぐらいで設定するほうが有効になりやすい、ということになります。
【法律で無効となる条項について】
先ほど、「原則として有効」といいましたが、当然、無効となる場合があります。
まず、法律で無効となる場合は、消費者契約法です。
消費者契約法が適用されるのは、事業者と消費者が契約する場合です。
この法律の中では、税理士は事業者とされるので、消費者と契約する場合にはこの法律の適用があります。
消費者とは、相続税の相続人や贈与税の受贈者、個人で事業をやっていない人の確定申告を行う場合などです。
適用にならないのは、法人や個人事業者などで、その場合にはこの法律はもう関係ないということになります。
消費者契約法第8条では、次のような条項を規定すると無効になります。
①債務不履行又は不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
「条項例」
甲は、乙に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求をしないものとする。
例えば、上記のように、「一切賠償しません」というような条項は、それを書いた瞬間に無効になるということです。
②債務不履行又は不法行為で故意又は重過失で消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
「条項例」
乙が甲に対し、故意又は重過失による債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債務を負担する時は、その賠償額の上限は、年間顧問料を上限とする。
上限を定めるような場合は一部免除になるのですが、どのような場合かというと、故意又は重過失の場合です。
ということは反対から見ると、軽過失の場合には上限を定めていい、という話になります。
従って、法人の場合には故意・重過失を含めて良いのですが、消費者や、相続税や贈与税の事案の場合には、故意と重過失をその賠償の免除のところから外しておかないといけないということになります。
つまり、契約書を作り分けないといけないということです。
さらに、例えば次のような条項は無効となります。
「税理士が過失のあることを認めた場合に限り、税理士は損害賠償責任を負うものとします。」
つまりこれは、「過失があるかどうかを決めるのは税理士です」ということになるので、このような条項は無効になるということです。
また、決定権限になる場合も同様に無効となります。
「税理士が損害賠償責任を負う場合、その額の上限は10万円とする。ただし、税理士に故意又は重過失があると認めた時は、全額を賠償する。」
ここでも、故意や過失があるかどうかを決めるのは税理士である、という決定権限を認めることになるので無効になるということです。
これらが、法律で損害賠償の制限条項が無効になる場合です。
【損害賠償の制限条項が無効とされた判例について】
次に、判例を見ていきます。
裁判所が勝手に無効にする場合です。
ここでは、システム開発契約に関しての損害賠償の判例を紹介します。
税理士の契約書で、損害賠償の上限情報が解釈された事例が見当たらないので、準委任契約とされるシステム開発契約の判例を探ってみました。
システム開発契約では、間違いがあると損害額が莫大になりやすいので多くの場合、契約書に損害賠償額の上限条項が定められています。
従って、システム開発契約に関して賠償額の上限条項が争われた事例が結構あるため、参考になると思います。
「東京地裁平成26年1月23日判決(判例時報2221号71頁)」
(事例)
乙が委任業務に関連して、乙又は乙の技術者の故意又は過失により、甲若しくは甲の顧客又はその他の第三者に損害を及ぼした時は、乙はその損害について、甲若しくは甲の顧客又はその他の第三者に対し賠償の責を負うものとする。(1項)前項の場合、乙は個別契約に定める契約金額の範囲内において損害賠償を支払うものとする。(2項)
(裁判所の判断)
権利・法益侵害の結果について故意を有する場合や重過失がある場合(その結果について予見が可能かつ容易であるといった故意に準ずる場合)にまで同条項によって被告の損害賠償義務の範囲が制限されるとすることは、著しく衡平を害するものであって、当事者の通常の意思に合致しないというべき。したがって、被告に故意又は重過失がある場合には、この規定は適用されない。
契約書には書いてあるのに、裁判所が勝手に「故意・重過失の場合には、この条項が適用されない」という解釈によって排除してしまったということです。
裁判所の判断ではこういうことがあるので、損害賠償額の上限規定は有効なのですが、100%完全ではないということに注意をしていただきたいと思います。
ただ、この判例のロジックは、例えば次のように文言を変えることによって回避することができると思います。
「判例に対応する変更例」
乙が甲に対し、故意また過失(重過失を含む)による債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償債務を負担する時は、その賠償額の上限は、甲が乙に対して支払った当該行為があった年の年間報酬を上限とする。
契約書で「重過失を含む」と書いてしまえば、当事者双方が重過失の場合もこの条項を適用するということを合意した、ということになるので、先ほどの判例のようなロジックは使えないということになるのではないかと思います。
【損害賠償の制限条項を設ける時の注意事項】
最後に、損害賠償の制限条項を設ける時の注意事項についてまとめておきます。
(1)法人税等事業者との委任契約書と相続税等消費者との委任契約書では、有効となる範囲が異なるので、契約書は別々に作る必要がある。
(2)特に相続税等消費者との委任契約では、消費者契約法で無効になる場合があるので、これを注意して書き分け、無効にならないように規定する。
(3)損害賠償の制限条項を無効とした判決がシステム開発契約等であるので、こうした判決にも留意して条項の文言を考え、規定する。
今回は、契約書において損害賠償額の上限を規定することによって、 税理士がそれ以上の損害賠償請求を受けないようにする方法について解説をしました。
この方法も利用して、損害賠償請求をなるべく受けないように、普段の業務を行っていただきたいと思います。