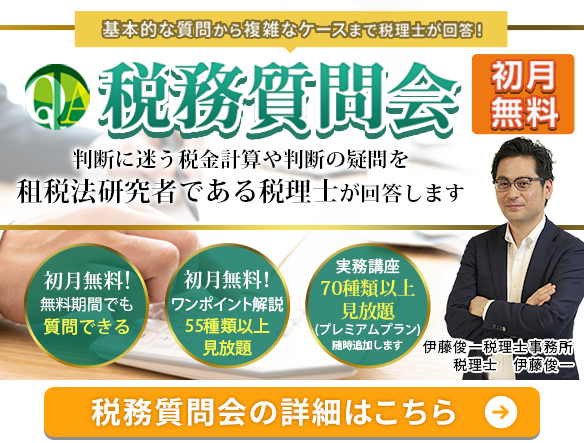現在、個人医院が所在する土地について、
等価交換方式による分譲マンション建設を検討しています。
まだ計画段階ではありますが、税務上の特例に関する私の認識が正しいかどうか確認させてください。
<背景>
土地は、医院長である次男B、経営に関与する長女C、医師である長男Dが、それぞれ1/3ずつ共有しています。
元々は母親Aの所有でしたが、令和3年の相続により3人が共有名義となりました。
この土地には個人医院の建物と、親族が株主のMS法人が建築した建物があります。
MS法人の建物は昭和61年築で、帳簿価額は約1億3,000万円です。
個人医院およびMS法人からは、年間合計で約700万円超の地代が支払われています。
ただし、医院が借りている部分(年間240万円分)については、事業主Bが自己に対して地代を支払う形になるため、実際には授受が行われていません。
以前はAの存命中に年間360万円の支払いが行われていました。
<計画内容>
Bは70代で後継者がいないため、3年後を目処に医院を閉院し、土地をマンション敷地として活用する予定です。
不動産会社からは「等価交換マンション事業」の提案を受けており、3名とも土地譲渡に合意しています。
等価交換マンション事業とは、土地所有者が土地を提供し、デベロッパーが建築したマンションの一部(区分所有権+敷地権)を持分に応じて取得する仕組みです。
この場合、税務上考えられる特例としては、
①固定資産の交換の特例(所法58条)
②立体買換えの特例(措法37の5)
③特定事業用資産の買換特例(措法37③)
の3つが想定されます。
それぞれについて、私なりに以下のように整理しました。
<1.固定資産の交換の特例(所法58条)>
医院建物を取り壊してデベロッパーに土地を引き渡す形になるため、
「土地 → 土地+建物」への交換に該当します。
そのため、同一区分内の交換に限られる適用要件を満たさず、適用は難しいと考えています。
<2.立体買換えの特例(措法37の5)>
①特定民間再開発事業地区内における特例は、都道府県知事の認定が必要な都市再開発案件に限られます。
本件はまだ計画初期段階で、そのような認定の予定はなく、現時点では適用可能性は低いと思われます。
②既成市街地等における中高層共同住宅の特例についても、三重県津市は措置法上の対象区域外のため、こちらも該当しません。
<3.特定事業用資産の買換特例(措法37③)>
この特例は、国内にある事業用資産を10年以上保有し、それを譲渡して新たな事業用資産に買い換える場合に適用されます。
以前は措法37④でしたが、現在は③に整理されています。
Bは医業を営んでおり、C・Dも相応の地代を受け取っていることから、一定の事業用性が認められると考えられます。
ただし、適用を受けるには、買換え後に取得するマンションの持分面積が300㎡以上である必要があります。
また、賃貸経営などの不動産事業として利用することが前提であり、自宅やセカンドハウスとして使用した場合は適用不可となります。
以上のような整理で、各特例の適用可否を判断しています。
この理解でおおむね正しいでしょうか。
また、実務上の留意点や追加で検討すべき事項があればご教示ください。