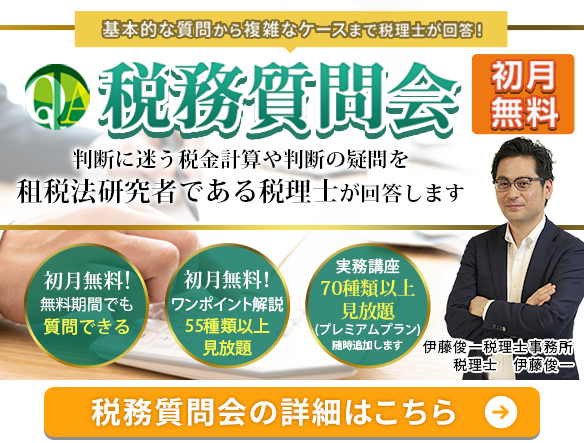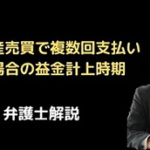クライアントであるA社に税務調査が入り、3年前に実施した親会社との事業譲渡取引が問題視されています。
A社は親会社P社の100%子会社です。
P社の経営者であり100%株主であるY氏は、別に経営する法人にVC等の投資家を受け入れたことにより、株主間契約の都合上、Y氏関連法人であるP社では資産管理業務以外を行うことができなくなりました。 そこで、株主間契約の制約を受けないA社(社長はY氏とは別人物)に、P社のメイン事業を譲渡しました。
この事業には独立系の大口取引先が存在し、その取引が売上の中心です。毎年の入札を通過しなければ契約を継続できない仕組みになっています。
譲渡時、P社とA社の契約内容は、当初1,500万円の支払と、この大口取引先の契約が継続する限り、P社の借入金相当額をA社が負担するというものでした。P社はこの事業を失うと金融機関への返済が困難になる状況でした。
第3条(譲渡価額)
本件事業譲渡価格は金15,000,000円(消費税抜)および「契約目録」に記載された契約が継続している期間に限り、P社が2020年8月1日(以下「事業譲渡日」)に金融機関より借入を行っている負債に対する返済金額相当額の合計とする。
A社では譲渡時に1,500万円を支払い、営業権として計上し償却しています(P社側では売上計上)。その後、P社とA社間で借入金相当額の受払が継続しています。
ところが調査では、「実際の譲渡対価は1,500万円に加え、譲渡時のP社借入残高1.5億円を含めた約1.65億円だ」と当局が指摘しました。 第三者との取引なら安すぎるし、このように金額が確定しない契約は通常締結しないと主張しています。契約条文の「借入負債に対して」という文言から、その時点の負債全額を対象と見なしているようです。
さらに、この調査ではA社だけでなくP社も調査対象とされ、今後はP社の机上調査が実施される見込みです。両社は同じ場所に登記され、同じ法人部門で管理されているためです。
しかし実際には、P社の借入金全額が譲渡事業に使われたわけではありません。 P社は太陽光パネル、不動産、リゾート会員権など他の資産や売上も保有しています。社長の感覚でも、毎年入札があるため、実際の負担は借入金翌期返済分の3,000万円程度を1,500万円に加えた4,000~4,500万円が妥当だと考えています。次年度以降の入札結果は契約時点では不確定でした(結果的には継続しています)。
今回、この当局の評価に反論するため、以下の主張を検討しています。
1)借入金の使用用途を区分し、譲渡対価は1.65億円ではなく、もっと低い金額が妥当であると主張する。
2)譲渡事業部門のPLを作成し、M&Aで一般的に用いられる「営業利益の2~3年分」という手法で評価額を主張する。
このような状況において、当局への反論として有効な方法はあるでしょうか。