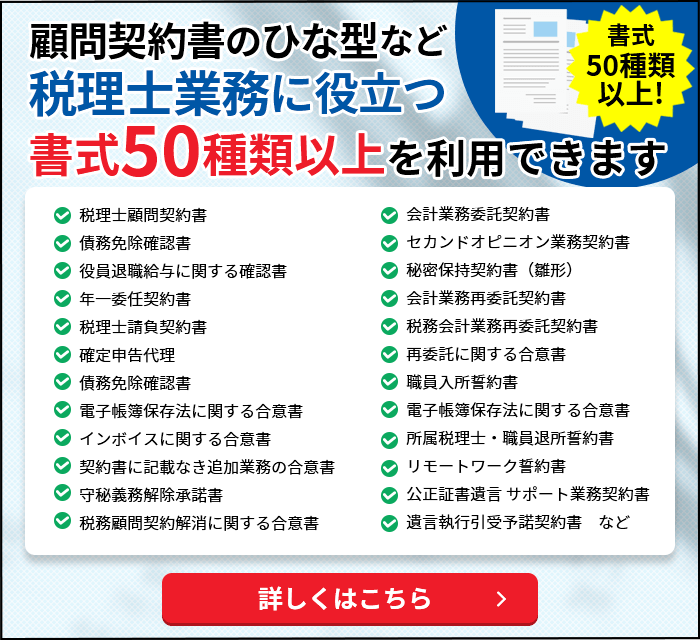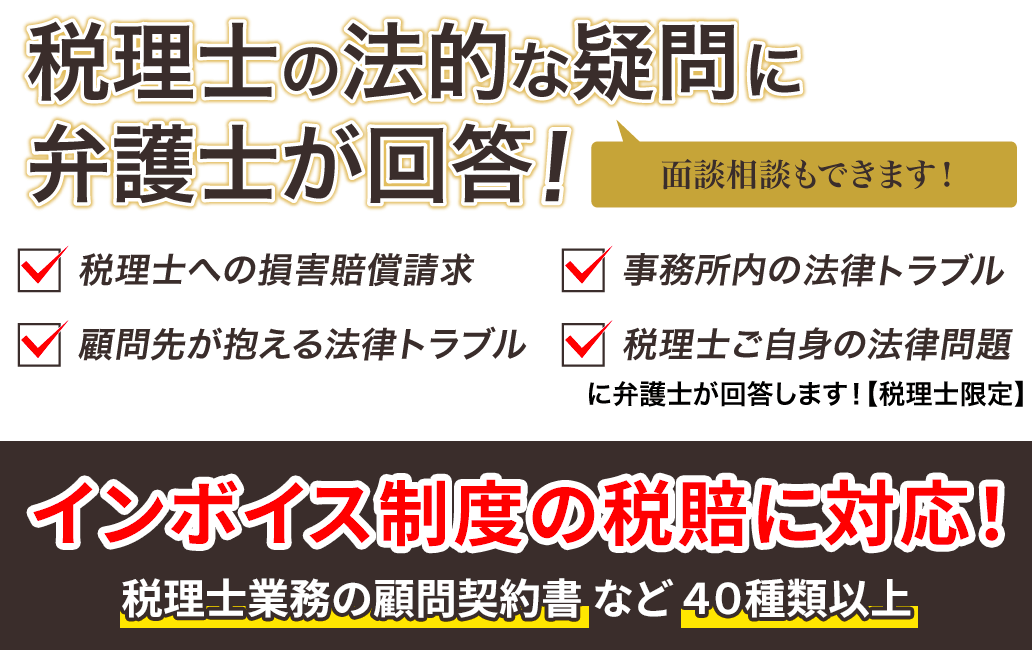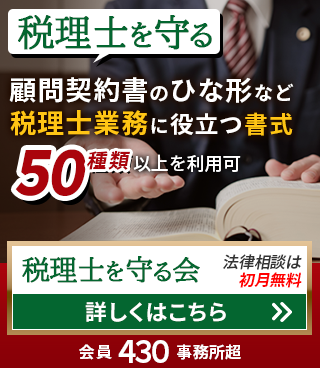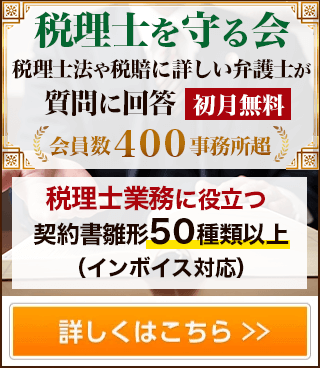執筆:弁護士・税理士 谷原誠
新型コロナウイルス感染症による被害が長期化している。
この間、感染を回避するために、税理士会各支部などの会合や研修が中止になり、WEBによる実施などの工夫が行われている。
会計事務所の働き方についても、在宅勤務を導入する事務所も増えた。さらに、顧問先等への訪問をせず、WEB面談などへの切り替えも進んでいる。
さらには、ようやく行政手続のデジタル化が進み出しており、税務行政についても例外ではなく、改正電子取引情報保存制度の施行など、税理士の業務に与える影響も大きい。
そこで、この記事では、デジタル時代における会計事務所経営のリスクについて検討するが、紙面の都合上、以下の3点のリスクに絞って検討をしてみたい。
fa-check-circle-o非対面による税賠リスク
fa-check-circle-o行政のデジタル化による助言義務
fa-check-circle-o税理士及び職員の在宅勤務
1 非対面による税賠リスク
従前、顧問先に訪問して、会計帳簿の内容を確認し、必要に応じてインタビューし、原始資料の現物確認をしていたところ、新型コロナウイルス感染症の感染を回避するため、訪問を中止し、WEB面談に切り替えたとする。
この場合の税賠リスクについて検討する。
(1)現物不確認のリスク
顧問先に訪問しての業務の場合には、会計帳簿等に不明点あるいは疑問を持つ点があれば、ただちに原始資料を確認し、あるいは関係者にインタビューして疑問を解消することが可能である。
しかし、非対面によるWEB面談の場合、それらを確認することに困難を伴う場合がある。
このような場合に、原始資料を確認せずに業務を遂行した場合に過誤が生じることが考えられる。この場合、税理士に原始資料などを確認する注意義務があるのに、それを怠った、として、損害賠償請求をされる可能性がある。
そこで、このような事態を回避するためには、
・税理士において原始資料を確認する業務まで業務範囲に含めて、一括して資料を送付してもらう方法
・会計帳簿の作成義務は顧客が負担し、税理士は、会計帳簿の正確性や原始資料の確認義務を負わない方法
が考えられる。
契約書に明記が必要である。
(2)確認書面の署名押印リスク
複数の税務処理が可能である場合や税務判断が難しく、後日の税務調査による否認の可能性がある税務処理を行う場合には、顧客にその旨説明した上で、顧客に損害が発生した場合でも、税理士には損害賠償請求などをしない(債務免除)旨の確認書面を徴求する場合がある。
対面の場合には、書面の必要性を説明した上で、その場で署名押印を得ることができる。
しかし、非対面の場合には、WEB会議で必要性について説明しても、書面や別途メールや郵送でやり取りをすることになり、署名押印をしてくれなかったり、漏れがでてしまったり、ということが想定される。
そのようなことがないよう、確認書面を先行して提出してもらうことを条件に税務書類を交付する、など工夫を要するところである。
(3)信頼関係低下リスク
顧客との信頼関係を高めるには、できる限り頻繁に対面により会うことが効果的である。
非対面になると、その分信頼関係を築くのが難しくなる。税理士が注意義務違反をして顧客に損害が生じた場合、信頼関係がしっかりできていれば、税理士による真摯な謝罪により税賠に発展しないことも多い。
しかし、信頼関係が築けていない場合には、損害賠償請求をするについて心理的な抵抗が少ないため、税賠に発展しやすくなると推測される。
2 行政のデジタル化による助言義務
行政のデジタル化を受け、令和3年度税制改正により、税務関係書類における押印義務について見直しを行うこととされた。
また、令和4年1月1日以降に施行される改正電子取引情報保存制度により、保存方法をデジタル化する顧客が増えることが予想される。
帳簿の保存についてはタイムスタンプなどの要件が定められており、当該保存要件を満たさない場合は、法律に定められた保存をしていない、ということになり、青色申告取消等の不利益がある。
そこで、税理士としては、改正電子取引情報保存制度の要件を満たす保存方法を顧客に助言し、当該助言をしたことを証拠として残しておく必要がある。
助言を漏らした場合、及び助言したことを立証できない場合には、税賠に発展する可能性があるので、留意したい。
3 税理士及び職員の在宅勤務におけるリスク
(1)複数事務所
税理士法40条3項は、「税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。」と規定している。
そして、税理士法基本通達40-1は、「法第40条に規定する「事務所」とは、継続的に税理士業務を執行する場所をいい、継続的に税理士業務を執行する場所であるかどうかは、外部に対する表示の有無、設備の状況、使用人の有無等の客観的事実によって判定するものとする。」と規定している。
判定のポイントは、(1)外部に対する表示の有無、(2)設備の状況、(3)使用人の有無等「客観的事実」によることとなる。
この規定の趣旨は、
(一)税理士の業務活動の本拠としてこれを1箇所に限定することが法律関係を明確にする上で便宜であること、
(二)個人の監督能力を超えて業務の範囲を拡大することを事務所の面から規制し、これにより税理士以外の者が税理士業務を営むことを防止すること、
とされている(「新税理士法五訂版」日本税理士会連合会編、170頁)。
この観点から考えると、税理士が在宅勤務を行い、又は職員に在宅勤務を実施させる場合には、次の検討が必要となる。
(一)職員に対し、税理士の管理・監督が及ぶための方策
(二)自宅で顧客と面談しないこと
(三)自宅の電話を連絡先として顧客と電話連絡などをしないこと
(四)自宅で税理士業務を行っていることを外部に表示しないこと
(五)自宅に設置した器具備品を償却資産として計上しないこと
顧客等から見て、自宅も事務所だと見られないようにすること、職員等に対する管理・監督を機能させること、などが重要となると思われる。
(2)守秘義務
税理士法38条は、「税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。」と規定している。
そして、税理士法基本通達38-2は、「法第38条に規定する『税理士業務に関して知り得た秘密』とは、税理士業務を行うに当たって、依頼人の陳述又は自己の判断によって知り得た事実で、一般に知られていない事項及び当該事実の関係者が他言を禁じた事項をいうものとする。」とされている。
税理士が扱う情報は、個人又は法人の収入、支出、税額などの情報であるが、これらは、全て一般に知られていない情報であり、守秘義務の対象となる情報がほとんどであると言える。
税理士が守秘義務に違反した場合には、損害賠償義務が発生し、懲戒処分の対象となり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性がある(税理士法59条)。
また、守秘義務は、資格を有する税理士にだけあるものではない。税理士法54条は、「税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。」とされており、これに違反した場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑が科せられることとされており(税理士法59条)、税理士と同等の責任を負担する。
在宅勤務は、外部と遮断された会計事務所の外で業務を行うものであり、家族その他の第三者が出入りすることから、それらの者に秘密が漏洩するリスクが存することになる。
(3)使用人の監督
税理士法41条の2は、「税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。」と規定している。
当該規定に違反した場合には、懲戒処分の対象となる。その場合の懲戒処分の考え方について、「財務省告示第104号」は、次のように定めている。
「税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者・・・が不正行為を行った場合における、使用者に対する懲戒処分は、次に掲げるところによるものとする。
(1)使用人等の不正行為を使用者税理士等が認識していたときは、当該使用者税理士等がその不正行為を行ったものとして懲戒処分をする。
(2)使用人等の不正行為を使用者税理士等が認識していなかったときは、内部規律や内部管理体制に不備があること等の事由により、認識できなかったことについて当該使用者税理士等に相当の責任があると認められる場合には、当該使用者税理士等が過失によりその不正行為を行ったものとして懲戒処分をする。
なお、上記に該当しないときでも、使用人等が不正行為を行ったことについて使用者税理士等の監督が適切でなかったと認められる場合には、当該使用者税理士等が法第41条の2(使用人等に対する監督義務)の規定に違反したものとして懲戒処分をする。」
職員が事務所内で勤務をする場合に比較して、在宅で勤務する場合には、どうしても税理士の管理監督の程度が弱まることは避けられない。
したがって、職員が守秘義務違反などの税理士法違反を犯さないよう、事務所勤務の場合以上の対策を行うことが要請される。
具体的には、職員に在宅勤務を行わせる場合に、次の措置が必要となると考える。
(一)就業規則、服務規律、業務マニュアル、リモートワーク誓約書等の整備
(二)相談、連絡、報告の徹底と証拠化
(三)守秘義務その他の税理士法、関係法令などの職員研修
以上