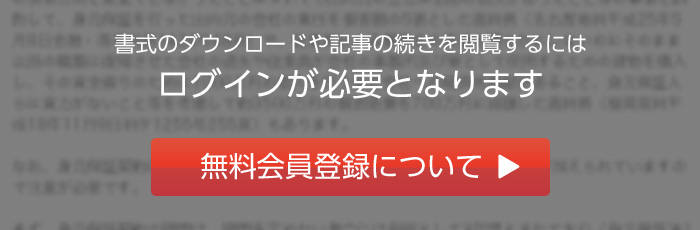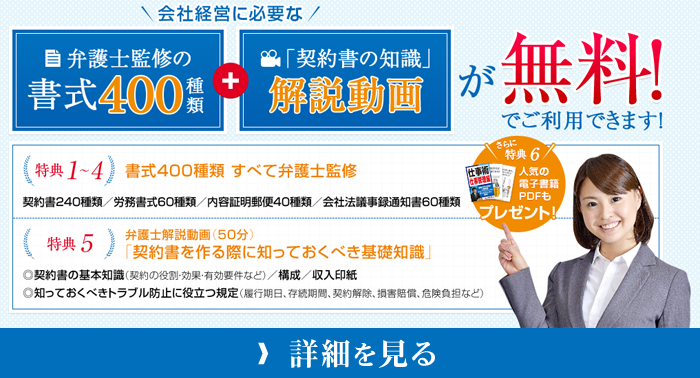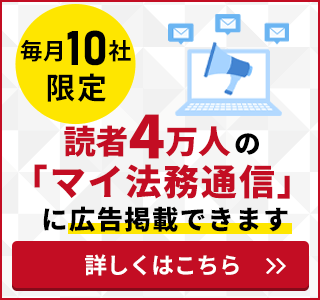現行民法のルール
「意思表示」とは、法律上の効果が発生することを望んでいるという意思を外部にわかるように表示することです。
わかりやすい例でいうと、契約の申込みや承諾が意思表示にあたります。
民法では、お互いの意思が合致したときに契約が成立すると定められている契約類型が多く、諾成契約と呼ばれています。
諾成契約には、売買契約、贈与契約、賃貸借契約などがあります。
意思表示は通常、真意に従ってするものです。
真意と表示が食い違っている場合に問題が生じます。
意思表示をした本人が真意と表示の不一致に気づいていないことを錯誤といいます。
現行民法は、法律行為の要素に錯誤があった場合には、その意思表示は無効であるとしています。
意思表示が契約の承諾である場合、契約は成立しないことになります。
「法律行為の要素に錯誤があった」というのは難しい表現ですが、錯誤がなければ意思表示をしなかっただろうといえる場合であり、かつ、意思表示をした本人にかぎらず一般の人から見てもそのような意思表示をしなかっただろうといえる場合を指します。
誰かにだまされて意思表示をした場合には、真意と表示が食い違っているとはいえませんが、意思の形成過程に欠陥があります。
これを詐欺といいます。
詐欺による意思表示は無効ではありませんが、取り消すことができるとされています。
変更点
(1)錯誤の効力を無効から取消しに変更
現行民法では、法律行為の要素に錯誤があった場合には、その意思表示が無効であるとしていました。
無効であれば初めから効力が生じないことになるので、誰でも無効を主張することができるのが一般的です。
しかし、錯誤による無効は意思表示をした人を保護するためのものなので、一般的な無効とは異なります。
裁判所の判例では、意思表示をした人が無効を主張しない場合には、その他の人は無効を主張できないとしています。
また、現行民法は意思表示をした人に重大な過失があるときは本人は無効を主張できないと定めていますが、その場合にはその他の人も無効を主張できないことになっています。
このように、錯誤による無効は一般的な無効とは異なり、むしろ取消しに近いと考えられていました。
改正民法は、錯誤の効力を無効とするのではなく、取消しができることとしました。
錯誤があった場合、法律行為の目的と取引上の社会通念から判断して重要なものといえる場合にのみ取消しをすることができます。
今回の改正は国民にとってわかりやすい民法にするという目的があるため、要素の錯誤という難しい表現を噛み砕いた表現に変更しています。
取消しができるということは、取り消さないかぎり有効ということであり、錯誤があったことに気づいてから追認をすることによって完全に有効にすることもできます。
はっきりと追認するという意思表示をした場合はもちろん、錯誤があったことを知りながら、契約から生じる債務を実際に行った場合には追認したものとみなされ、それ以降取り消すことができなくなります。
また、錯誤があったことに気づいてから5年が経過した場合にも取り消すことができなくなります。
錯誤の効力が無効であった現行民法の下では、基本的に追認することはできず、無効を主張できる期間に制限はありませんでした。
錯誤の効力が変更されたことによって、これまでとは取扱いが大きく異なることになります。
(2)動機の錯誤を明文化
現行民法における錯誤とは、表示の錯誤や内容の錯誤を指し、動機の錯誤は含まれません。
表示の錯誤とは言い間違いや書き間違いのことであり、内容の錯誤とは意思表示の内容に思い違いがあることです。
動機の錯誤とは、法律行為をする気になった理由に思い違いがあることで、動機の錯誤は民法上の錯誤ではないため、基本的には無効となりません。
判例では、例外的に、動機が表示されて相手方に伝わり、意思表示の内容になったといえる場合には錯誤による無効を主張することができるとしています。
実際の契約の場面では、表示の錯誤や内容の錯誤よりも動機の錯誤が生じることが多いです。
それにもかかわらず、民法に動機の錯誤についての規定がないことが問題とされていました。
改正民法は、法律行為の基礎とした事情についての認識が誤っていた場合、つまり動機の錯誤も錯誤のひとつとして認めました。
改正前は動機が表示されて意思表示の内容になった場合のみ無効を主張できるということでしたが、改正後はそれに対応させて、その事情が法律行為の基礎となったことが表示された場合のみ取消しができるとしています。
動機の錯誤については、判例によって確立されていた考え方を明文化したものであるため、改正によって特に変わることはありません。
(3)第三者による詐欺について相手方が善意有過失でも取消しができることを明文化
現行民法では、相手方の詐欺によって意思表示をした場合には意思表示を取り消すことができるとしていますが、契約の当事者ではない第三者の詐欺によって意思表示をした場合には、相手方がそのことを知っていたときにかぎって取り消すことができるとしています。
つまり、相手方が過失により知らなかった場合でも、意思表示をした人は第三者の詐欺による意思表示を取り消すことができないということです。
しかし、詐欺による意思表示をした人を保護する必要があるため、相手方が詐欺の事実を知らなかったことに過失があるときは取り消すことができるという考え方が一般的です。
改正民法では、この一般的な考え方を明文化しました。
相手方が詐欺の事実を知っていたか、過失により知らなかったときは意思表示を取り消すことができるとしたのです。
この改正により、第三者による詐欺について意思表示を取り消すことができないのは、相手方が詐欺の事実を過失なく知らなかった場合のみということになります。
(4)詐欺による意思表示の取消しを善意有過失の第三者に対抗できることを明文化
ここでいう第三者は、(3)で出てきた第三者とは意味が異なります。
(3)の第三者は詐欺を行った人を指し、契約の当事者ではないという意味で第三者としています。
それに対して、ここでの第三者とは、詐欺による意思表示にもとづいて成立した契約から生じた債権を譲り受けた人など、詐欺による意思表示の取消しをする前に法律関係に入ってきた人のことです。
意思表示の取消しがあると契約はさかのぼって無効となりますが、第三者が法律関係に入ってきた後に詐欺による意思表示の取消しがあった場合には、第三者に不利益が生じます。
そこで、第三者を保護するために、現行民法は詐欺による意思表示の取消しは善意の第三者に対抗できないと定めていました。
改正民法は、保護される第三者を善意無過失の第三者に限定することによって、詐欺による意思表示をした人に有利な規定に変更しています。
現行民法の下でも、詐欺による意思表示をした人を保護する必要性が高いため、善意無過失の第三者にのみ対抗できないという考え方が一般的でした。
そのため、この改正により実質的な変更はないものと考えられます。
契約書への影響
(1)錯誤の効力を契約書に記載することはないため、契約書への影響はありません。
(2)動機の錯誤に関する取扱いを契約書に記載することはないため、契約書への影響はありません。
(3)第三者による詐欺があった場合の意思表示の取消しについて契約書に記載することはないため、契約書への影響はありません。
(4)詐欺による意思表示の取消しを対抗できる第三者について契約書に記載することはないため、契約書への影響はありません。
いつから適用になるか
改正民法は、2020年4月1日に施行されます。
この日を施行日といいます。
施行日よりも前にした意思表示には現行民法の規定が適用され、施行日以後にした意思表示には改正民法の規定が適用されます。