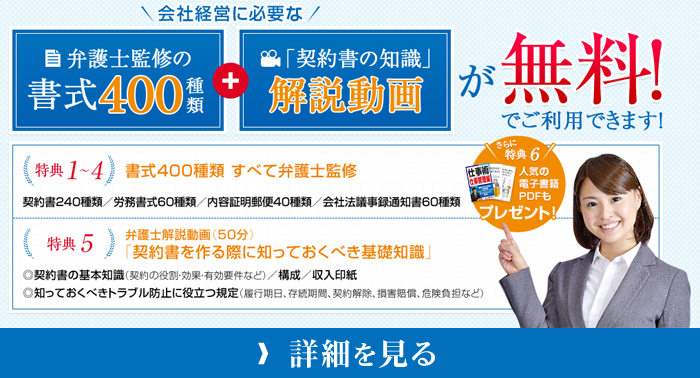
契約書書式の雛型テンプレート一覧はこちら
書式・記事一覧サイトマップ
- 会社法務書式
- 定款 取締役会非設置会社
- 定款 合同会社
- 定款 取締役会・会計参与設置会社
- 定款 取締役会・監査役会設置会社
- 取締役会議事録 取締役報酬の決定
- 取締役会議事録 社債発行
- 取締役会議事録 職務代行者の順位決定
- 取締役会議事録 代表取締役の選定
- 定款 取締役会・監査役(業務制限)会社
- 取締役会議事録 支配人の選解任
- 取締役会議事録 重要な組織の設置等
- 株主総会議案 第三者割当による募集株式の発行
- 株主総会議案 株主提案の場合
- 取締役会議事録 中間配当
- 監査役会議事録 常勤監査役選任
- 監査役会議事録 監査役会規則改定
- 取締役会議事録 会社・取締役間の訴えの会社代表者
- 取締役会議事録 重要な財産の処分
- 取締役会議事録 多額の借財
- 監査役会議事録 会計監査人選任への同意
- 監査役会議事録 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実の取締役の報告
- 監査役会議事録 議長・招集権者選任
- 監査役会議事録 常勤監査役解職
- 監査役会議事録 報酬決定
- 監査役会議事録 会計監査人の報酬への同意
- 監査役会議事録 退職慰労金決定
- 監査役会議事録 取締役の責任減免・責任限定契約への同意
- 監査役会議事録 監査役選任議案への同意
- 監査役会議事録 会計監査人解任
- 監査役会議事録 提訴請求
- 取締役会決議省略の監査役同意書
- 書面決議による取締役会議事録
- 報告省略の取締役会議事録
- 監査役会議事録 監査報告作成
- 報告省略の監査役会議事録
- 取締役会議事録 株主総会招集
- 取締役会議事録 株式の譲渡承認
- 取締役会議事録 利益相反取引(承認)
- 取締役会議事録 利益相反取引(報告)
- 取締役会議事録 競業取引(承認)
- 取締役会議事録 競業取引(報告)
- 取締役会議事録 第三者割当増資
- 取締役会決議省略の取締役同意書
- 株主総会提案書兼通知書
- 株主総会目的事項同意書
- 書面決議による株主総会議事録
- 書面報告による株主総会議事録
- 取締役会招集通知
- 株主総会議案 計算書類承認
- 株主総会議案 剰余金の処分
- 株主総会議案 定款の変更
- 株主総会議案 取締役選任
- 株主総会議案 監査役選任
- 株主総会議案 補欠監査役選任
- 株主総会議案 役員報酬改定
- 株主総会議事録のひな形
- 取締役会規則
- 監査役会規則
- 株主総会招集通知
- 定款
- 取締役会
- 定款
- 株主総会
- 株主総会
- 監査役会
- 内容証明郵便
- 不正行為のあった従業員の懲戒解雇通知
- 遺産分割協議の申し入れ
- 商品の欠陥を理由とする契約解除
- 敷金返還請求
- 無断譲渡・転貸を理由とする賃貸借契約解除
- 特許権侵害に基づく警告書
- 期間満了後の土地使用継続に対する異議
- 過払金返還請求
- 婚約破棄を理由に結納金返還請求
- 協議離婚の申し入れ
- 有期雇用従業員に対する雇止通知
- 売買目的物の引渡請求
- 賃金返還請求(返済期限の定めがない場合)
- 借地契約期間満了前の借主の更新請求
- 暴行による負傷の治療費・慰謝料の請求
- 類似商号に対する警告書
- 委任事務処理の状況報告の要求
- 普通解雇の通知
- 浮気相手に不貞行為を理由とする損害賠償請求
- 養育費の支払請求
- 婚約破棄
- 委任契約の解約通知書
- 遺留分減殺請求
- 商標権侵害に基づく警告書
- 著作権侵害に基づく警告書
- 貸金返還請求
- 貸金返還請求(相続人に)
- 商品売買代金請求
- 請負代金請求
- 請負契約の納期遅延を理由に契約解除
- 賃料増額請求
- 賃料不払いによる賃貸借契約解除
- マンション管理組合による滞納管理費請求
- 原状回復費用請求
- 購入した不動産の引渡し及び解除予告
- 無断増改築工事の停止請求
- 期間の定めのない賃貸借契約で賃貸人から解約予告通知
- 賃貸借契約の更新拒絶通知
- 賃貸借契約の賃借人からの解約予告通知
- 滞納賃料請求
- 賃料減額請求
- クーリングオフ
- 不動産の修繕
- 不動産売買
- 不動産関連
- 交通事故
- 人事労務
- 会社法
- 債務不履行請求
- 債権債務に関する契約
- 商品売買
- 委任契約
- 慰謝料
- 知的財産権に関する契約
- 解雇
- 請負に関する契約
- 賃貸借契約
- 過払金返還
- 金銭の貸借契約
- 労働SOSトピック
- 労務書式
- 解雇理由証明書(就業規則なし)
- 同意書(年少者)
- 通勤交通費申請書
- 給与辞令
- 健康保険資格取得証明書
- 雇用管理情報利用同意書
- 口座振込依頼書
- 時間外労働・休日労働に関する協定届
- 身元保証更新書
- 身元保証人変更届
- 出向辞令
- 転籍辞令
- 休職願
- 退職に関する覚書
- 退職勧奨通知書
- 不採用通知
- 辞令
- 退職勧奨同意書
- 始末書
- 退職願
- 転籍同意書
- 休職命令書
- 退職証明書(全ての事項を記載する場合)
- 解雇通知書
- 解雇予告通知書
- 解雇予告除外認定申請書
- 解雇制限除外認定申請書
- 解雇理由証明書(就業規則あり)
- 懲戒処分通知書
- 復職願
- 解雇予告手当受領書
- 社会保険等資格喪失証明書
- 秘密保持誓約書
- 退職時の誓約書雛形
- 退職証明書
- 出向契約書
- 労働者派遣基本契約書
- 身元保証書(差し入れ型)
- 内定承諾書
- 入社誓約書
- 雇用契約書(就業規則あり)
- 雇用契約書(就業規則なし)の雛形
- 労働条件通知書兼同意書
- 身元保証契約書
- 採用内定通知書
- 休業
- 労働時間
- 懲戒・休職
- 採用・雇用
- 派遣
- 給与・交通費・保険
- 解雇
- 退職・出向
- 契約書書式
- 秘密保持契約書(双方開示)
- 動産賃貸借契約書
- 定期借地権付建物売買契約
- 建物譲渡特約付借地権契約書
- 建物賃貸借権売買契約書
- 建物賃貸借予約契約書
- 建物賃貸借契約書(取り壊し予定建物)
- 建物賃貸借契約書(会社と取締役間の賃貸借)
- 医療用ガス供給設備の保守点検業務委託契約書
- 運行委託契約書
- 駅レンタカー業務委託契約書
- 覚書(食堂経営委託契約書に付随)
- 業務代行委託契約書(土地家屋月賦販売の勧誘等)
- 経営委託契約書(経営委任契約を本質とする場合)
- 機械売却委任契約書
- 食堂委託契約書(従業員食堂)
- 食堂経営委託契約書
- 劇場経営委任契約書
- 建物賃貸借ならびに建物の管理経営業務委託契約書
- 物流センター利用約款
- 定期用船契約の期間延長に関する協定書
- 船舶使用承諾書(傭船契約書(木造かつお・まぐろ船)第4条の承諾書)
- 寝具類洗濯業務委託契約書
- 傭船契約書
- 傭船契約書(木造かつお・まぐろ船)
- 店頭看板契約書
- 建物賃貸借契約合意解約書
- 自動車賃貸借契約書
- 標準倉庫寄託約款(甲)
- 有価証券保管契約書
- 標準倉庫寄託約款(乙)
- 標準トランクルームサービス約款
- 有限責任事業組合契約書
- 仮登記担保設定契約書(停止条件付)
- 相殺契約書(相殺後の残債務を免除する場合)
- 更改契約書(債権者の交替)
- 離縁協議書
- 遺言書(遺言執行者として弁護士を指定する場合)
- 金銭借用証書(一括払い・連保版)
- 金銭借用証書(分割払い版)
- 金銭借用証書(ボーナス払い併用版)
- 金銭消費貸借契約(連帯保証人なし・一括弁済)
- 金銭借用証書(一括払い版)
- 金銭消費貸借契約(借主が連帯債務者)
- 限定付金銭消費貸借契約書
- 和解契約書(金銭消費貸借)
- 利率変更契約
- 金銭消費貸借契約(連帯保証人なし・分括弁済)
- 債権贈与契約書
- 根抵当権確定合意書
- 根抵当権極度額変更承諾書
- 金銭消費貸借契約(連帯保証人なし・ボーナス併用版)
- 弁済期限変更契約
- 転抵当権設定契約書
- 根抵当権一部譲渡契約書
- 根抵当権一部譲渡承諾書
- 根抵当権確定期日変更契約書
- 根抵当権極度額変更契約書
- 保証人変更契約
- 物上保証契約書
- 根抵当権被担保債権の範囲変更契約書
- 金銭消費貸借契約
- 保証契約書
- 遺産分割協議書
- 不動産死因贈与契約
- 負担付土地建物贈与契約
- 金銭消費貸借抵当権設定契約書
- 根抵当権設定契約書
- 抵当権設定契約書
- 土地建物贈与契約
- 抵当権放棄契約書
- 立木抵当権設定契約書
- 動産贈与契約書
- 準消費貸借(土地代金)
- 準消費貸借契約(商品代金)
- 譲渡担保契約書(動産)
- 譲渡担保契約書(不動産)
- 転質契約書
- 動産質権設定契約書
- 遺言書
- 仮登記担保設定契約書
- 相殺契約書
- 更改契約書
- 協議離婚書
- 夫婦財産契約
- 組合契約書
- 示談書(交通事故)
- 示談書(騒音被害)
- 示談書(損害賠償請求)の雛形・文例
- 寄託契約書
- 消費寄託契約
- 倉庫寄託契約書
- 建築下請契約書
- 建物サブリース契約書
- 貸室賃貸借契約
- 借家権譲渡契約書
- 借地契約更新契約書
- 借地権譲渡契約書
- 借地条件変更契約書
- 土地転貸借契約書の雛形
- 解約合意書(土地賃貸借)
- 定期借地権設定契約書
- 建物使用貸借契約書
- 建物賃貸借契約書(店舗使用)
- 建物賃貸借契約更新契約書
- 解約合意書(建物賃貸借)の雛形
- 定期建物賃貸借契約書
- 土地使用貸借契約書
- 土地賃貸借契約書(建物所有目的の場合)
- 土地賃貸借契約書(一時的な使用の場合)
- 標準宅配便運送約款
- 物流センター使用契約書
- 調査委託契約書
- 標準貨物自動車運送約款
- 機械製造契約書
- 市場店舗経営委託契約書
- 指定品製作契約書
- 清掃委託契約書
- 施設(医療機関)の清掃業務委託契約書
- ミシン販売委任契約書
- 一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款
- 経常建設共同企業体協定書(甲)
- 経常建設共同企業体協定書(甲)第8条に基づく協定書
- 経常建設共同企業体協定書(乙)
- コンサルティング契約
- サービスの提供に関する契約
- ビジネスに関する契約書
- 不動産の売買契約
- 交換に関する契約
- 任意後見に関する契約
- 使用契約
- 使用貸借契約
- 信託契約
- 入場に関する契約
- 共同経営
- 利用に関する契約
- 労働災害
- 動産の売買契約
- 受託契約
- 和解に関する契約
- 商品・物品・製品の売買
- 商品券等に関する契約
- 土地に関する契約
- 委任契約
- 寄託契約
- 工事契約
- 年少者との契約
- 抵当権に関する契約
- 担保・保証に関する契約
- 更新に関する契約
- 清掃に関する契約
- 相殺に関する契約
- 相続・贈与関係の書式
- 看板の仕様に関する契約
- 示談書
- 組合契約
- 経営に関する契約
- 結婚・離婚に関する契約
- 船舶に関する契約
- 製造に関する契約
- 調査に関する契約
- 請負契約
- 賃貸借契約
- 賃貸借契約(借地・借家)
- 賃貸借契約(動産)
- 賃貸借契約(商品)
- 賃貸借契約(土地)
- 賃貸借契約(建物)
- 質権に関する契約
- 運送に関する契約
- 金銭の貸借契約
- 情報
- 相続登記義務化による相続手続きへの影響と注意点
- 不動産管理会社はインボイス制度にどう対応すべき?
- 土地の用途変更による税負担の影響と相続時の注意点
- 土地の地目変更による相続税評価額への影響
- 合同会社の役員に子供を選任するメリット・デメリット
- 飲食店のまかないは経費になるか?判断基準と留意点を解説
- 相続税評価における無道路地の範囲と減額補正の仕組み
- 相続税評価額が下がる土地の特徴と画地補正の種類
- 不動産相続に伴う税金の種類と負担。申告・納税のポイントを解説
- 二次相続で税負担が増える?小規模宅地等の特例の節税効果と影響
- 事業所得と雑所得の区分方法と判断基準のポイント
- 税務行政のDX導入による納税者のメリットと税務調査への影響
- 贈与者の死亡時における教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の取扱い
- DX導入で実現する税務コンプライアンスの強化
- 中小企業がDXを導入すべき理由と気を付けるべきポイント
- クラウド会計ソフトを活用した経理業務の自動化によるメリット
- 相続税の税務調査で指摘されやすい貸家建付地評価のポイント
- 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の適用要件および注意点
- 損金算入が認められる福利厚生費の範囲と否認されないためのポイント
- 税務上の売上割戻と仕入割戻の取扱いと誤りやすいポイント
- インボイス(適格請求書)の交付義務が免除されるケース
- 紙の書類をスキャナ保存するメリットと適用要件を解説
- 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円の特別控除の適用要件
- 法人が保有する暗号資産の税務上の取扱い
- 法人税法上の有価証券の評価差額と譲渡損益の取扱い
- 経費と損金の違い。法人税の計算で誤りやすいポイントを解説
- 電子帳簿保存法に基づいた電子取引データの保存方法を解説
- 帳簿書類の種類と役割。作成する際の注意点を解説
- 使用貸借の土地に対する相続税・贈与税の取扱い
- 公益法人等の法人税の課税所得の範囲と相違点を解説
- 居住用財産の買換え特例の適用要件および引き継ぐ取得価額の計算方法
- 税効果会計を適用する目的と効果、手続き方法を解説
- 減価償却資産の処理方法。財務会計と税務会計の相違点を解説
- 経理担当者が知っておくべき税務調査の事前対策のしかた
- 特定美術品に対する相続税の納税猶予制度の適用・免除要件
- 定期同額給与による役員報酬が損金不算入となる事例を解説
- 譲渡所得の2,000万円控除の特例の要件および申告手続き
- トラブル防止のために契約書のリーガルチェックが必要な理由
- 企業の経理担当者が知っておくべき税務申告の種類と申告・納期限
- 税務会計と財務会計の違い。法人税の申告手続きをする際の注意点
- 法人が納める主な税金と種類ごとの納付期限を解説
- 移転価格税制の仕組みと国税庁が実施している取組みを解説
- 相続税の納税猶予を適用している農地を貸し付けた場合の特例措置
- 固定資産の交換特例の要件と交換差金が生じる場合の注意点
- 税務調査を10年以上受けていない法人の特徴と対策する際の注意点
- 連年贈与が定期贈与とみなされるケースと対策方法を解説
- 低未利用土地等を譲渡した際の100万円特別控除の特例
- 少額減価償却資産を取得した際の損金算入と特例措置
- 親子間で行われる不動産の使用貸借に対する贈与認定
- 相続による事業承継が失敗する原因と対処法を解説
- 印紙税の納付義務が生じる場面と収入印紙の貼付漏れに対する罰則
- 滞納処分による財産差押えが実施されるまでの猶予期間
- 災害発生時における救済措置と法人税の取扱い
- 山林に対する相続税の納税猶予制度の適用要件・免除・確定事由を解説
- 農地を譲渡した際に800万円特別控除の特例制度を適用できるケース
- 消費税の非課税取引に該当する範囲と例外規定
- 中小企業が利用できる法人税の特別償却・特別税額控除の種類
- 源泉徴収が必要になる報酬・料金等の種類および納付時期を解説
- 遺留分侵害額請求が行われた際の相続税・贈与税の申告・更正手続き
- 役員・使用人が出向した際に支出する給与負担金の取扱い
- 土地の不合理分割に該当するケースと相続税評価額の計算方法
- 税務上の貸倒引当金の取扱いと損金算入する際の注意点
- 法人が借地権設定時に権利金の認定課税される条件と対処法
- 経営者が相続対策として検討すべき贈与税の配偶者控除の活用
- 国等に相続財産を寄附した場合における相続税の非課税特例の要件
- 生産緑地の相続税評価額の計算方法と相続後の選択肢
- MS法人の役割と医療法人との相違点を解説
- 低額譲渡の課税関係および法人と役員間で資産を売買する際の注意点
- 法人税におけるゴルフ会員権の取扱いと留意点
- 役員が死亡した際に支払われる退職金の相続税における取扱い
- 資力喪失者が資産を譲渡した際の所得税の非課税規定
- 相続登記義務化による相続手続きへの影響と注意点
- 固定資産の資本的支出と修繕費の違いと判定基準を解説
- 法人税の更正の請求。対象期間と手続き上の注意点を解説
- 令和6年度税制改正において創設・見直された法人関係の変更点
- 定額減税で給与支払者がやるべき源泉徴収等の事務処理を解説
- 人格のない社団等が遺贈を受けた際の相続税の取扱い
- 短期売買商品等の譲渡損益および時価評価損益の計算方法
- 保証債務の履行に伴う譲渡所得の特例制度を適用する際のポイント
- 税務調査の結果に納得できない場合に行う不服申立制度
- 法人が土地や建物などを交換した際の圧縮記帳の要件および注意点
- 税務上の交際費等と寄附金の違いと区分する際の注意点
- 合計所得金額・総所得金額・総所得金額等の違いと計算上の注意点
- 消費税の税抜経理方式と税込経理方式の特徴と相違点を解説
- 棚卸資産の評価方法の種類とそれぞれのメリット・デメリットを解説
- 特定資産の買換えによる圧縮記帳の特例制度の要件を解説
- 特定非常災害に伴う土地等の相続税評価額の計算方法を解説
- 貸付用の宅地等でも小規模宅地等の特例が適用できないケースを解説
- 節税目的の役員報酬引き上げが税負担増加の要因になるケース
- 令和5年度税制改正後の相続時精算課税制度の要件および注意点
- 中小企業の経営者が知っておくべき法人税の節税手法5選
- 法人税における減価償却資産の償却方法の原則と例外
- 山林所得の仕組みおよび計算方法。譲渡所得との区分のしかたを解説
- 居住用の宅地等でも小規模宅地等の特例が適用できないケースを解説
- 生前贈与の加算対象期間の見直しに伴う相続税対策の変更点
- 法人税における受贈益および債務免除益の取扱いと注意点
- 株式の譲渡損失の損益通算および繰越控除を適用する際の注意点
- 改正電子帳簿保存法に対応した電子取引データの保存方法
- 令和5年度税制改正で見直された電子帳簿保存法のポイントを解説
- 電子帳簿等保存制度の基礎知識。対象書類および保存方法を解説
- 適格分割の税制上のメリットと適用要件
- 適格合併の税制上のメリットと適用要件
- 所得税における役員退職金の取扱いと計算方法
- インボイス制度による売上1千万円以下の事業者への影響
- インボイス制度の開始時に免税事業者が取るべき対応
- インボイス(適格請求書)の記載事項とは?請求書サンプルあり
- インボイス制度の2割特例とは?負担軽減措置の適用対象と留意点
- インボイス制度による白色申告を行う個人事業者への影響
- インボイス制度が令和5年10月1日から始りました〜事前準備と登録完了までにかかる時間〜
- 法人税の収益計上時期の原則と例外。税務調査で指摘されやすいポイント
- 上場株式等の譲渡所得・配当所得に係る課税方式の統一による影響
- 定期金の権利に関する相続税評価額の計算方法を解説
- 適格現物分配の税制上のメリットと適用要件
- 適格現物出資の税制上のメリットと適用要件を解説
- 法人税の青色申告が取消しになるケースと再申請のしかた
- 法人税の青色申告のメリット・デメリットおよび手続き上の注意点
- 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例と適用対象になる条件
- 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の適用要件と手続き上の注意点
- 適格株式移転の税制上の利点と適用要件を解説
- 適格株式交換の適用要件と税制上のメリットを解説
- 法人税の外国税額控除の概要と対象になる外国法人税の範囲
- インボイス制度が施行した後も免税事業者と取引する際の注意点
- DX投資促進税制の適用要件と手続きの流れ
- 相続税の法人版事業承継税制の一般措置と特例措置の違い
- クロスボーダーの組織再編成に伴う税制上の注意点
- 株式交付制度および株式対価M&Aを促進するための措置の概要解説
- 法人税で損金計上できる海外渡航費の範囲と注意点
- 損金算入が可能な租税公課の種類と計上時期の注意点
- 贈与税の納税義務者の種類と相続税の納税税務者の範囲との違い
- 税務調査で指摘されやすい小規模宅地等の特例のポイント
- 減価償却費の取扱いは法人と個人事業主で異なる
- 遺産分割のしかたの違いによる相続税・譲渡所得税への影響
- 経営者が不動産投資を行う税制上のメリット・デメリット
- 相続税・贈与税の新しいマンション評価方法と改正に伴う影響
- 税理士でも間違えやすい相続税の制度・適用要件
- 財産分与に対する税金と離婚後に贈与税が課されるケース
- 事業承継のために組織再編成を行うメリット・デメリット
- 組織再編するために持株会社を設立するメリット・デメリット
- 無対価組織再編成の種類と課税上の注意点
- 欠損金の繰越控除制度と繰戻還付制度のメリット・デメリットを解説
- 法人税の欠損金繰越控除制度の適用要件と利用する際の注意点
- 市街地山林の評価方法と宅地転用が見込めない場合の例外規定
- 不動産譲渡所得の計算において取得費がわからないときの対処法
- 非適格合併等により移転を受ける資産・負債に対する調整勘定の取扱い
- 親族に対して役員報酬を支払う際に注意すべきポイント
- 税務上の寄附と贈与の取扱いは個人と法人で異なる
- 借地権の返還に伴う個人・法人の立場における課税関係の違い
- 平成21年及び平成22年に取得した不動産を譲渡する際の注意点
- 適格組織再編で特定資産譲渡等損失の損金算入が制限されるケース
- 税務調査で節税目的の組織再編が否認されるケースと事例を紹介
- 円滑な事業承継のために相続税の納税資金は確保しなければならない
- 個人版事業承継税制を適用すべきケースと避けるべきケース
- 立体買換特例の対象となる不動産の種類と適用時の注意点
- インボイス制度対応の契約書を作成する際の留意点
- 組織再編税制の概要と適格組織再編に該当するための要件を解説
- マンション評価の見直しによるタワマン節税への影響
- 競馬の払戻金に対する課税の判例と国税当局の対応方針
- 個人の事業用資産の買換え特例の要件と適用後の注意点
- 業績連動給与を損金算入するための要件および注意点
- 事前確定届出給与の手続きをしても役員報酬が損金不算入となるケース
- 法人と会社役員の間で不動産を賃貸借する際の税務上の注意点
- 譲渡代金が回収不能となった際に適用できる所得税の特例制度を解説
- 国外居住親族に係る扶養控除等を適用する際に提出・提示すべき書類
- 農地の相続税納税猶予制度の確定・免除要件を解説
- 個人に対する負担付贈与の課税関係と不動産の評価方法を解説
- 「通常の地代」と「相当の地代」の違いと借地権評価における注意点
- 過大役員給与の判定基準と損金不算入にならないためのポイント
- 相続税の納税義務者の種類と課税対象財産の所在場所の判定方法
- 売却前に対策すべき。不動産譲渡所得の効果的な節税方法5選
- BCP(事業継続計画)とは。策定目的と運用する際のポイントを解説
- 国税庁の令和3事務年度の調査実績および法人調査の重点項目
- 優劣はあるのか?税務調査を担当する部署の種類と特徴を解説
- 相続税のタワマン節税の効果と国税当局が規制する可能性を解説
- 医師が医療法人化する税制上のメリットと設立する際の注意点
- 所得税の非課税所得に該当する種類と課税・非課税の判断基準
- 税務調査の対象になりやすいフリーランスの特徴と対処法を解説
- 加算税の軽減・加重措置の種類と適用されるケースを解説
- 税理士第33条の2「書面添付制度」の効果と利用すべきケース
- 貸付事業用宅地等(小規模宅地等の特例)の3年縛りの条件と例外規定
- マイホームの売却損失が発生した際に適用できる譲渡所得の特例制度
- 金融庁と国税庁の連携強化による影響と節税目的の保険商品への規制
- 法人が企業版ふるさと納税を利用するメリット・デメリット
- 令和4年10月実施のリモート調査の概要と対象となる納税者の範囲
- 年末調整の対象者と適用可能な所得控除・税額控除の種類を解説
- 配当所得における大口株主の範囲と令和4年度税制改正による変更点
- 税理士が作成した申告書は税務調査を受けにくい理由
- 相続税を計算する際の財産評価のしかたと評価単位を解説
- インボイス登録は必要なのか?申請しない場合のデメリットを解説
- 相続税で特定の評価会社に該当する非上場株式の種類
- 厚生年金保険の加入条件と役員に対する社会保険の取扱い
- 役員報酬の選択肢。株式報酬の効果と支給する株式の種類
- 【令和4年度税制改正】住宅ローン控除の要件・控除額の変更点を解説
- 自己株式を取得・消却・処分した際の税務上の取扱い
- 役員退職給与の節税効果と税金対策を講じる際の注意点
- 新株予約権を付与する際に法人・役員の立場で注意すべきポイント
- 税制適格・非適格ストックオプションの課税関係と制度上の相違点
- 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)が適用できないケースとは
- 医療法人の出資と非上場株式の評価方法が異なる点を解説
- 個人事業主の税金負担が重い理由と対処法
- 法人税・消費税の税務調査を受けやすい業種・ケースを解説
- 医療法人の種類と相続税における取扱いおよび評価上の注意点
- MS法人の活用によるメリットおよび設立する際の注意点
- 国外転出時課税制度の概要。対象者および対象資産の範囲を解説
- 事業承継は法人と個人事業主のどちらの方が行いやすいのか
- 消費税の申告において簡易課税制度を利用するメリット・デメリット
- インボイス制度の税務・実務における影響と施行以前にやるべき対策
- 事業規模が同じなら法人の方が個人事業主より節税できる
- 事業は法人と個人事業主のどちらで立ち上げるべきなのか
- 株式会社を設立する際の流れと登記申請手続きにかかる費用
- 免税事業者はインボイス制度のために消費税課税事業者の届出が必要
- 消費税課税事業者届出書の書き方および提出時に注意すべきポイント
- 消費税課税事業者が関係する届出書の種類および提出時期を解説!
- 繰延税金資産の回収可能性を判断する基準および手順
- タックスプランニングの必要性。個人事業主が知っておくべき税金知識
- 事業承継する際に相続税のタックスプランニングが必要になる理由
- 企業のグローバルタックスプランニングの基礎知識
- 企業がタックスプランニングに取り組むべき理由
- 税務調査で社長貸付を指摘されるケースと否認されないための対策
- 社長借入金のメリット・デメリット及び税務上の取扱いと注意点
- 創業融資の審査に落ちる6つの原因とやるべき対策
- 創業融資を受ける前に把握しておくべき利用条件・審査のポイント
- 創業融資で資金調達するメリット・デメリットを種類ごとに解説
- 事業再構築補助金の事業計画書で必ず記載すべき事項と注意点
- 事業計画書の記載事項と作成時に注意すべきポイント
- 事業計画書を会社創業時点で作成しなければいけない理由
- 会社をたたむ検討するタイミングと事業廃止する際の注意点
- 相続税対策で非上場株式評価額を引き下げるために知っておくべき事項
- 税務調査で質問応答記録書の作成を求められた際の対処法
- 令和4年から適用される電子帳簿保存法の変更点【令和3年度税制改正】
- 電子帳簿保存法とは。制度の概要と税制改正による変更点
- みなし配当に該当するケースおよび特例制度を解説【基礎知識編】
- 法人から個人事業主へ「個人成り」する際に知っておくべき注意点
- 消費税の「みなし譲渡」に該当するケースと廃業する際の注意点
- 税務調査を受ける際の対応方法とやってはいけない行動・発言
- 消費税の実務で押さえておきたいポイントを解説(基本編)
- 借地権の相続税評価額の計算方法を種類別に解説
- 「みなし譲渡」として所得税の課税対象となる3つのケース
- 小規模宅地等の特例を適用する際に知っておくべきポイント
- 税務調査の流れと事前にやるべき調査対策のポイント
- 節税の必須対策!役員退職金を損金計上するための要件と金額基準
- 役員給与を損金計上するための基本的な要件と注意点
- 税理士でも見落しやすい「みなし贈与」に該当するケース
- 民事信託の基礎知識。制度の特徴と活用すべきケースを解説
- 時価と税務評価額の違い。適正株価を計算しなければいけない理由
- 税金対策は専門家に。金融機関から提案される節税手段が危ない理由
- 税務調査で節税策が否認されるケースと指摘されないための対策
- 事業承継のために株価を合法的に引き下げる方法
- 節税策の先取りは将来の税務リスクとなる可能性があるので要注意
- 会社経営者が相続時に直面する問題点と生前にやるべき対策
- 接待交際費に該当しない飲食費の範囲と金額基準を解説
- 税理士が記帳代行会社を設立する場合は税理士法違反に注意すること
- 外注費と給与の判断基準。税務調査で指摘されないための対策方法
- 役員報酬を増減した際の定期同額給与判定と税務調査における論点
- 消費税の納税義務と課税事業者を選択する場合の注意点
- 小規模企業共済は活用すべき?知っておきたいメリット・デメリット
- 貸倒損失を計上するための要件と税務調査で指摘されやすいポイント
- 税務調査で役員退職金が否認されるケースと役員賞与認定による影響
- 仕訳の考え方
- 納税証明書について
- 事業承継・引継ぎ補助金について
- 相続税の納税猶予の種類と各制度の猶予・免除規定を解説
- 相続税の納付方法の種類と延納・物納制度のポイント解説
- 相続税がかかる財産とは?課税対象になるのは相続財産だけではない
- 非上場株式・上場株式の評価方法(相続税評価額の算出方法)を解説
- 仮想通貨(暗号資産)取引の所得区分と損益の計算方法
- 借地権の所得税・法人税・相続税・消費税における取り扱いについて
- 消費税のインボイス制度 ~電子インボイスとは~
- 中小企業の貸倒引当金を考える
- 限定承認による相続税とみなし譲渡による準確定申告の必要性
- 相続発生日と相続の開始があったことを知った日が異なるケースとは?
- 相続税対策で土地活用するなら貸付けしないと節税効果は半減
- 会社の解散実務について
- 5G導入促進税制について
- 2021年4月より実施される消費税の総額表示義務付けの制度内容と注意点
- 特定路線価・個別評価を設定する対象地域と申請方法
- 路線価地域の宅地を評価する際の調整率と利用区分に応じた補正計算を解説
- 法人の地方税について
- 確定申告における注意点~個人事業主が誤りやすい事例について~
- 被相続人が老人ホームに入所した際の小規模宅地等の特例適用について
- 宅地に類似する雑種地の相続税評価額の計算方法
- 不動産を活用した相続税の節税効果と考慮すべきリスク
- 設備投資をした場合の使いやすい制度とは?
- 国庫補助金を受けた場合の圧縮記帳とは?
- 相続財産を遺贈寄附した場合の課税関係と節税方法
- 不動産を公益法人等に寄附した場合の譲渡所得の非課税特例を解説
- 相続税における土地の地目と評価額の計算方法
- 手書きで青色決算書を作るときの注意
- 収益認識に関する会計基準と法人税法の関係
- 株式譲渡所得・配当所得の確定申告と住民税の申告不要制度解説
- 財産債務調書の提出要件と税務調査への影響
- 相続税で配偶者の税額軽減が適用できない3つのケース
- 税金の滞納処分について
- 新型コロナウイルス感染症対応-法人税関連まとめ
- 無償返還の届出書を提出した土地の相続税評価額の注意点
- 譲渡所得の3,000万円特別控除を適用する際に注意すべきポイント
- 相続税の税務調査で名義預金認定されないための対策
- 労働生産性について
- 資産除去債務とは
- 結婚・子育て資金の非課税制度の対象となる費用の範囲
- 教育資金の非課税制度の概要と適用する際の注意点
- 相続税の2割加算の対象になる人・ならない人の判別方法
- 個人事業主は寄付金を必要経費にできるのか?
- 家賃収入・給付金の会計処理違い(個人事業主と法人)
- 譲渡所得の空き家特例を適用する際に注意すべきポイント
- 譲渡所得の契約日と引渡日を利用した節税方法!
- 相続税の申告で漏れやすい財産と確認すべきポイント
- クラウドファンディングの税金について
- 青色申告特別控除額の改正について
- 譲渡所得の取得費に加算できる相続・贈与時の諸費用について
- 二次相続で相続税の未成年者控除・障害者控除を適用する際の注意点
- 路線価は時価の8割程度。路線価を使用する税金と計算上の注意点
- 中小企業における交際費で注意すべき点
- 確定申告における発生主義と現金主義
- 相続税の対象外!非課税財産の種類と注意点について
- 国外財産調書制度の内容と令和2年度の税制改正による変更点
- みなし譲渡所得の対象となるケースと対策方法を解説
- 固定資産の減価償却費とは?
- 個人住民税のしくみについて
- 配偶者居住権の相続税評価の仕組みと計算方法について
- 地積規模の大きな宅地の評価の解説。広大地評価に変わる新たな土地評価方法
- 相続税対策のやりすぎに注意。制度内容を理解しないと節税効果は薄い
- 利益が出ているのに法人税をゼロにする方法
- これだけは知っておきたい!相続税で節税効果の高い特例制度
- インボイス制度と個人事業主
- 令和5年から始まるインボイス制度について
- 企業版ふるさと納税とは
- 個人事業主のクルマの経費について
- 法人は贈与税の対象外?法人・個人間で贈与する際の税金の取り扱い
- 年間の法人税の税務調査件数と申告漏れの指摘割合について
- 同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者とは?
- 所得税額調整控除(令和2年度からの源泉徴収にかかる改正)
- 「タワマン節税」を実行する前に!これだけは知っておきたい注意ポイント
- 不動産の売却益の税金を圧縮する方法は?マイホーム売却時の3000万円控除など解説
- ターニングポイントを迎えた「ふるさと納税」。高額な返礼品に加えて一時所得の問題も
- 貧乏経営者がやりがちな節税対策の根本的な間違いとは?
- 税務調査で真っ先に調べられる「計上のズレ」には要注意
- 家族間で借りたお金が贈与税の対象になるケースとは?
- 税務調査におけるペナルティ=重加算税について解説
- 税務調査で問題になる経理の電子化における注意ポイントとは?
- 固定資産税の特例措置に代わる新制度について
- 事業承継が円滑にできる!税制改正による特例措置とは?
- 書類や帳簿のスキャナ保存制度とは?
- 消費税の軽減税率の対象範囲・経過措置・補助金について
- 確定拠出年金の税法上の取り扱いと注意点とは?
- 法人成りのメリットとデメリット
- 国税犯則取締法の改正で何が変わったのか?改正点を解説
- 会計事務所における使用人(会計事務所職員)の監督義務とは?
- 民泊の税務と確定申告の注意点とは?
- 仮想通貨の仕組みや所得課税、税務調査について
- 税制改正による医療費控除の手続きの簡略化について
- 税理士の名義貸しとなる行為とは?
- 法定調書が税務調査で争点になりやすい理由とは?
- なぜ経費に計上した修繕費は税務調査で争点になりやすいのか?
- 税務調査で争点になる分掌変更と役員退職金の経費計上について
- 高額特定資産を取得した場合の特例制度について
- 法人が消費税の還付を受けるための救済制度とは?
- 個人事業主の消費税の節税スキームについて
- 消費税が還付される仕組みと条件とは?
- 消費税の簡易課税制度とみなし仕入れ率とは?
- 所得拡大促進税制
- 税務調査で社長が考える以上に貸借対照表が重視される理由
- 税務調査の結果は税理士の力量でまったく違ってくる!?
- 税務調査における脱税に対する税務署の対応とは?
- なぜ顧問税理士を代えると税務調査の対象になりやすいのか?
- 税務調査における買掛金の時効の取り扱いとは?
- 税務調査における債権の時効の取り扱いとは?
- 税務調査で役員退職金が否認されないためのポイントとは?
- 税務調査で役員退職金が問題となる場合とは?
- 口約束でも契約は成立するの?
- 税務調査で棚卸資産の消費税の取り扱いが問題になるケースとは?
- 税務調査で棚卸資産が問題になるケースとは?
- 隣人トラブル!ベランダ喫煙への法的対処法とは?
- なぜ税務調査で短期前払費用が争点となるのか?
- やってはいけない道路上での禁止行為とは?「道路法」「道路交通法76条」解説
- 税務調査で問題になりやすい短期前払費用の注意点とは?
- 働く能力があるのにホームレスになると逮捕される!?
- 非弁行為とは?弁護士じゃないのに法律業務をすると逮捕される!?
- 廃墟探検や心霊スポットの肝試しは犯罪になる!?
- 税務調査で問題となる固定資産の使用の定義とは?
- 中学校教師の夫が妻に暴力をふるって逮捕!?
- 税務調査でチェックされる固定資産経費処理の注意点とは?
- 上司からの土下座強要・暴言はパワハラ?それとも犯罪?
- 人間をポイ捨て!?タクシー運転手が犯した罪とは?
- 資金繰りが悪化!会社が破産!経営者の法的責任とは?
- ネットでコンサートのチケットを転売すると犯罪!?
- 詐害行為と詐害行為取消権とは?自宅を妻に贈与したら債権者から訴えらる!?
- 年末調整の必要資料と注意点とは?
- 児童に対する性犯罪~「知らなかった」では済まされない知識を解説~
- 事後強盗とは?盗みをした挙句に相手を暴行・脅迫する罪を解説
- 軽犯罪法・住居侵入罪・迷惑防止条例を解説~パパラッチによる隠し撮りは犯罪か?~
- 決算賞与の支給における税法上の注意ポイントとは?
- 子供が柔道の時間に大怪我…慰謝料請求はどうする?
- 決算賞与が経費と認められる5つの要件とは?
- ウソを広めると逮捕される?オオカミ少年は犯罪者!?
- 拾ったお金は誰のもの?ネコババしたら犯罪!?
- 資格試験で9人が書類送検!カンニングは犯罪か!?
- 法的責任は誰に?上級生が下級生にビル飛び降りを強要!
- 税務調査官が脱税チェックで行う隠ぺい仮装行為とは?
- 「ポケモンGO」で“ずるいこと”すると逮捕される!
- 会社の経費で飲食すると書類送検!?
- 「ポケモンGO」で刑務所にGO!?全国で犯罪が多発中!
- 抜くと傷害罪、切ると暴行罪になるもの何だぁ?
- 条例で義務化!自転車保険に加入しないと運転NG!?
- 期限後申告に対する税務署の対応とは?
- 債務整理を頼むなら弁護士?それとも司法書士?
- 税金の申告期限を守らない時のペナルティとは?
- 火をつけたのに放火じゃない!?では何の罪?
- 川遊びで幼稚園児が事故死…誰の責任?何の罪?
- 自転車を担いで逃げる男を発見!一体、何の罪?
- 企業に広がる朝型勤務の思わぬ落とし穴を検証!
- 税務調査における外注費支払いの注意点とは?
- 賃貸トラブル!家賃滞納者への追い出し行為は犯罪?
- 源泉税の計算と納付における注意点とは?
- 法律から考える!自動運転車の問題点と未来像
- 携帯電話やスマホの“ながら運転”は法律違反!?
- 金がない?忙しい?悪質な交通違反逃れは許されるのか?
- 半年間で3000件!?わいせつな迷惑電話は犯罪か?
- 赤字の会社にも税務調査は入るのか?
- じつは怖い存在…労働基準監督官の仕事と権限とは?
- 赤字会社でも負担するべき税金の種類とは?
- ゲーム仲間を脅迫した男女が強要罪で逮捕!?
- 身近に潜む危険性…マイナンバー法で初の逮捕者が!
- 認知症高齢者の電車死亡事故…賠償責任は誰にある?
- 法人税法を利用した役員報酬のインセンティブ制度とは?
- ご用心!チョコレートをあげただけで法律違反!?
- 役員報酬の決め方と注意点とは?
- 隣家の失火で我が家が燃えた!一体、誰の責任?
- つきまとい行為は軽犯罪法違反!?
- 検証!自動運転車実用化への法的問題点とは?
- 税務における青色申告のメリットとは?
- 飲酒運転の車に乗せてもらった女子大生は犯罪者!?
- 部下に違法残業をさせると上司も会社も書類送検!?
- 信号無視、一時不停止…自転車の危険行為は犯罪!?
- 格安バスツアー事故で15人死亡の大惨事
- 秘密の暴露が不正アクセス禁止法違反に!?
- 高齢者による交通事故・危険運転が増加中!?
- 刀剣女子は要注意!日本刀の模造刀所持は犯罪!?
- 無断でツイッターに写真投稿すると犯罪!?
- 仰天!自宅前の道路を塞いだ夫婦が逮捕!?
- マンションから物を投げ落とすと逮捕される!?
- 隣人トラブルも解決!?“ごみ屋敷”が強制撤去に!
- 女性のフェイスブックに無断侵入した男が逮捕!?
- 理由なく人の住居や店に居座り続けると犯罪!?
- 子供がいじめにあったとき親は何をすべきか?
- 危険運転で16歳少年が未熟運転致死罪に!?
- 社員に過労運転させた社長が償う“罪と罰”とは?
- 高額賠償金発生!自転車事故にどう対応する?
- 酒に酔って自転車に乗ると車の免許が免停になる!?
- 要注意!ネットでの“性的脅迫”にどう対処する?
- 相続トラブルを防ぐ!公正証書遺言のメリットとは?
- 学校で起きた人間ピラミッドの事故は誰の責任?
- 要注意!スポーツで賭けをすると逮捕される!?
- てんかん・認知症…持病がある人は車の運転禁止!?
- やってはいけない!高速道路での違反行為とは?
- 大迷惑な“ごみ屋敷問題”にはどう対処する?
- 客への弁償代を社員の給料から天引きする会社は違法!?
- 従業員の労働災害(ケガや死亡事故)を隠すと犯罪!?
- 候補者も有権者も要注意!選挙での金品授受は犯罪!?
- 学校で起きた子供の重傷事故は誰の責任?
- 妻のスマホに仕込んだ遠隔操作アプリで夫が逮捕!?
- 待機時間とは?休憩か労働か?勤務中の“待機時間”は給料なし!?
- 女子大生が自転車のひき逃げで書類送検!?
- 危険!汚い!「空き家」を放置すると法律違反?
- いたずら?嫌がらせ?ウソの注文は犯罪になる!?
- お酒を飲んで自転車に乗ると…犯罪!?
- 社員を危険にさらす会社は損害賠償請求される!?
- 家族4人死亡事故で危険運転致死傷罪は成立する!?
- 逮捕!?自分の子供を連れ帰った父親の罪とは?
- 自動車運転中に携帯電話を使うと逮捕される!?
- 年上の女性が好きすぎて逮捕された男は何罪?
- タダより高いものはない!?給料不払いで書類送検?
- バレなければ平気?経営者が陥る脱税の罪と罠
- 残業代を払わない会社には2倍の“おしおき”が!
- 職場のいじめ=パワハラと教育的指導の違いとは?
- どこまでやるとセクハラ…最高裁が下した判決とは?
- 転職先への手土産は他社の企業秘密情報!?
- 他人を傷つけるネットの書き込みは犯罪になる!?
- 会社の営業秘密を漏らすと…逮捕されちゃう!?
- 男子諸君は要注意!スカートめくりが犯罪になる!?
- ポストに入れると犯罪になるものなぁ~んだ?
- マジすか?Twitterのリツイートが犯罪になる!?
- モラハラは犯罪になる!?言葉の暴力とモラハラの関係を解説
- パワハラ自殺で会社に高額賠償金支払い命令!?
- 犯罪!?お釣りを多くもらっただけなのに…
- 検証!交通事故は増えている?減っている?
- 役員宛のメールを自分に転送した社員の罪と罰
- 本人に代わって財産管理をしてくれる法制度とは?
- 未払い残業代は倍返しで会社に請求される!?
- 父が認知症に…どうする?遺産相続問題
- LINEのアカウント乗っ取りは何罪?
- 兄弟間の相続での不公平感はどう解決する?
- 飼っていたカメが空を飛んだ!?で書類送検?
- 夫の遺産を相続できない妻がいるって本当?
- スマホで写真撮っただけなのに…逮捕!?
- 故意か?過失か?危険ドラッグの事故は厳罰!?
- どうやって分ける?兄弟間の不動産相続問題
- 警察官の自転車検査を拒否したら…逮捕!?
- 病気の人は自動車の運転をしてはいけない!?
- ひき逃げ事故、バレなきゃOKは通用しない!?
- 罪に罪を重ねる…「無免許運転による加重」とは?
- 通行禁止道路で起こした事故は刑が重くなる!?
- 相続人としてもらえるはずの相続財産がもらえない場合の請求方法とは?
- 遺言書を変更するのに必要な手続きとは?
- 企業の隠れ倒産…その時、経営者はどうする?
- 相続税を現金で納付できない場合の対応法とは?
- 飲酒運転の「逃げ得」は許されない!?
- 飲酒運転の死傷事故は最高刑20年の懲役!?
- 故人の所得税の確定申告の仕方とは?
- ペットを捨てると犯罪?拾っても犯罪?
- 手を握っただけで逮捕されるって本当!?
- 生命保険金を相続した場合の相続税の取り扱い方とは?
- 検証!いくらかかる?鉄道事故の損害賠償金
- いたずらでは済まない!悪ノリ投稿は犯罪になる?
- 財産分割で話がまとまらなかった場合の相続税の申告方法とは?
- 被害者が軽傷でも「ひき逃げ」なら懲役15年!?
- 女性に年齢を聞かないと逮捕される!?
- 相続人の種類とその相続分の割合とは?
- 従業員への給料不払いは犯罪になる!?
- 贈与税の概要と計算方法とは?
- SNSでのストーカーはどこまですると犯罪か?
- 自動車が線路を走ったら犯罪になる!?
- 万が一に備える!自筆証書遺言の書き方とは?
- 突然の職務質問…拒否するとどうなる?
- 相続税の計算方法とは?
- 愛犬が起こしたトラブルは飼い主の責任になる!?
- 殺人や放火も起きる!?隣人トラブルにどう対処するか?
- 相続税における土地の評価方法とは?
- 違法な探偵業者を取り締まる法整備を考える
- 遺産を分割する場合の方法・手続きとは?
- 他人のメールを盗み見るのは犯罪か?不正アクセス行為を解説
- 相続財産の種類とその調べ方、金額の評価の仕方とは?
- 走行中の車からのポイ捨ては犯罪になる!?
- 亡くなった父の遺言書には、どのような手続きが必要か?
- いきすぎたDVの代償は高額賠償金!?暴行罪・傷害罪を解説
- 相続関係をわかりやすく管理するにはどのようにまとめて整理すればいいのか?
- 未成年者の飲酒・喫煙で罰せられるのは誰?
- 個人が亡くなったときの手続き、届け出はどのようにすればいいのか?
- 「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」は何が違う?
- ストレス発散もやりすぎれば犯罪になる!?
- 盗撮を禁止するのは法律?それとも条例?
- 職場のいじめ・嫌がらせは犯罪になるか?パワハラを解説
- 放置プレイも度が過ぎれば犯罪になる!?保護責任者遺棄罪を弁護士が解説
- 無免許・飲酒運転の助手席に乗っただけで犯罪になる!?道路交通法を解説
- いたずらでも他人の物を壊したら罪になる? 器物損壊罪を弁護士が解説
- 車で人を死亡させたのになぜ100万円で許されるのか!?
- 時速40キロでも危険運転致死傷罪になる!?
- 自動車のひき逃げで殺人罪になる!?
- 8割以上がブラック企業!?あなたの会社は大丈夫?
- くつを投げただけで犯罪になる!?弁護士が威力業務妨害を解説
- リベンジポルノは犯罪になる!?
- 子供が起こした事故の高額賠償金、あなたは支払えますか?
- 迷惑チラシのポスティングを取り締まることはできるの?軽犯罪法・住宅侵入罪との関係を解説
- 自転車のトラブル急増中!ブレーキなし自転車で全国初逮捕
- 個人情報の暴露は犯罪になる!?不正競争防止法を解説
- 暴力団は自動車保険に入れない!被害者はどうする?
- 事件のあった部屋の家主に告知義務はあるのか?
- 愛犬が隣人を咬んで、損害賠償金が1,725万円!?
- 育児休業と介護休業を従業員に与える際の条件とは?
- 「酔っていて覚えていない…」は通用する?有名人の飲酒暴行事件が多発中
- 無免許でも運転技術があれば罪が軽くなる!?─亀岡暴走事故の刑が確定
- “倍返し”には、犯罪が成立するのか?
- 土下座の強要は犯罪になるのか?
- 不動産
- 親子や夫婦の共有名義。後悔しないためにしておくべきことは?
- 不動産の共有名義はトラブルの宝庫。それでも共有するの?
- 共有名義にするとなぜ、住宅ローン控除の枠が広がる?
- 共有名義にした方が良い人 共有名義の意味がない人
- 不動産登記簿謄本はどのように見ればいいのか?
- 相続した土地の相続税路線価の割り出し方と、その際の注意点とは?
- 相続した土地の相続税路線価の調べ方とは?
- 建築基準法上の接道要件とセットバックとはどういうものか?
- 都市計画法上の用途地域とはどういうものか?
- 相続税計算における土地の相続税路線価と実勢価格との関係とは?
- 不動産売買等での公正価値とは? また大損をしない公正価値の概算方法とは?
- 不動産を購入する際の注意点とは?
- 法務情報
- 法律相談Q&A
- 事業譲渡とは?事業譲渡の目的・メリット・事業譲渡契約書を解説
- 債権放棄による貸し倒れが税務調査で争点になりやすい理由とは?
- 契約書の基本知識
- M&A(企業買収)
- 会社分割の目的とメリットとは?
- 会社合併のメリットとデメリットとは?
- 株式交換・株式移転は何のために行うのか?
- 第三者割当増資は、いつ、どのように実施するべきか?
- M&Aにおける事業譲渡のメリットとデメリットとは?
- M&Aにおける会社の株式と経営の関係とは?
- M&Aはなぜ行われるのか?メリット・デメリットとは?
- M&Aを成功させるポイントとは?
- M&Aの実施後、売り手企業と買い手企業ともに注意すべきポイントとは?
- 敵対的M&Aや望まないM&Aを仕掛けられてしまった場合の防衛手法とは?
- 買い手が注意すべきM&Aのポイントとは?
- 会社の売り手としてM&Aを選択する理由と注意するべきポイントとは?
- M&Aにおいて「のれん」という用語の意味は?
- M&Aでは企業の買収価格はどのように決定されるのか?
- M&AにおけるDDとは、どのようなもの?
- M&Aのスケジュール(企業買収の手順)はどんな流れ?
- M&A(企業買収)にはどんな手法(種類)があるの?
- M&Aの意味・目的・メリット・デメリットは何ですか?
- 不正会計
- 減損回避のために行なわれた不正会計処理事例
- IPOのための不正売上計上事例
- 協力会社と共謀して接待交際費等を捻出した不正会計事例
- 海外子会社で起きた循環取引を使った不正会計事例
- 代表者のコンプライアンス違反による不正会計事例を解説
- 経理責任者による横領事件の手口を解説
- 内部告発から発覚した不正売上事例について
- 子会社で起きた資金流出に関する不正会計事例
- 社長と社外取締役が絡んだインサイダー取引による不正事例
- 予算必達のプレッシャーから起きた原価付替え不正取引事例
- 一社員が行なった商品転売による不正取引事例
- 支払いスケジュールを無視した不適切な売上取引事例
- 請求書基準を用いた不正な前倒し売上事例
- 実在しない商品による資金循環取引不正事例
- 会計監査の確認状で暴かれた未請求売上による不正事例
- 従業員個人が行なった不正事例と会社が注意すべきポイントとは?
- 内部監査のスケジュールを利用した不正会計の事例
- 上場企業における単独犯による個人的な不正会計事例を解説
- 現場主導で行なわれた在庫の前倒し計上・増加による不正会計事例
- 会社の費用の繰延計上による不正の手口とは?
- 売上の平準化のための前倒し計上の手口とは?
- 循環取引による不正会計とは?
- 交際費や福利厚生費の捻出のための不正取引事例
- 完成工事売上における不正計上の手口とは?
- 売上の計上のタイミングを使った不正会計とは?
- 粉飾決算の手口~売上の前倒し計上による不正取引とは?~
- 権利の売買による売上確保のための不正取引とは?
- 補助金取得のための不正会計とは?
- 上場後に生じた疑義ある売上取引
- 現金着服による不正の手口とは?
- 在庫水増しによる不正会計の手口とは?
- 棚卸における不正の手口とは?
- 経理責任者による不正出金の仕組みとは?
- 業界の慣習を利用した不正行為とは?
- 売上の粉飾を使った不正会計②:押し込み販売とは?
- 売上の粉飾決算を使った不正会計とは?
- 企業の「のれん」を使った不正会計とは?
- 損失飛ばしによる不正会計の手口とは?
- 現金や預金を使った不正の防止策とは?
- 工事進行基準を使った不正会計とは?
- 売掛金を分散させる不正会計とは?
- 売掛金で行われる不正会計とは?
- 棚卸資産(在庫)と資金繰り悪化の仕組みとは?
- 棚卸資産(在庫)を使った不正会計③:有償支給取引
- 棚卸資産(在庫)を使った不正会計②: 循環取引
- 棚卸資産(在庫)を使った不正会計①
- 不正会計の手法にはどのようなものがあるのか?
- 企業会計
- M&Aにおける簿外債務のリスクとその種類とは?
- 借入金のレバレッジ効果とそのリスクとは?
- なぜキャッシュ・フロー計算書では減価償却費をプラスするのか?
- 黒字倒産を見逃さないための決算書のポイント
- 事業計画書を作成する際の重要なポイントとは?
- 借入金のリ・スケジュール(リスケ)は可能か?
- 企業のセグメント情報から何がわかるのか?
- 原価計算をする目的は何なのか?
- 資金調達手段の種類と注意すべきポイントとは?
- 管理会計は何のために用いる会計なのか?
- 税務会計の目的と役割とは? 税務と会計の違いとは?
- ファイナンスの実務で意識すべき重要ポイントとは?
- 「会計」と「ファイナンス」の違いとは?
- 会社の利益と付加価値の関係とは?
- 貢献利益を知ることで何がわかるのか?
- 何のために損益分岐点を分析するのか?
- 会社の予算の効果的な活用法とは?
- 会社の予算はなぜ必要なのか?
- 埋没原価の意味とは? 経営上での取り扱い方とは?
- 機会損失とはどういう意味?ビジネスにおける機会損失を解説
- 財務分析で使われる「ROA」と「ROE」は何を表す指標なのか?
- 資金繰り表とキャッシュ・フロー計算書の違いとは?
- 損益計算書で会社の収益性を見るためのポイントとは?
- 損益計算書のチェックポイントとは?
- 不良債権や不良在庫の見破り方とは?
- 会社の安全性を知るための決算書上のポイントとは?
- 貸借対照表(バランスシート)のどこを見れば経営の安定性がわかるのか?
- 貸借対照表の重要ポイントとその正しい見方とは?
- 決算書の正しい分析の仕方とは?
- 赤字店舗の閉鎖や人員削減をすると赤字が増えるのはなぜか?
- 会社のコスト削減方法とは?
- 会社の費用を減らすには、どうすればいいのか?
- 売上が不振の際に行う値引きは経営戦略として正しいか?
- 安定した売上を上げる方法とは?
- 売上を増やすための新サービス、その展開方法や顧客獲得戦略とは?
- 会社が売り上げを増やすために重要な指標とは?
- 会社が利益を出すには何を、どうしたらいいのでしょうか?
- 会社にとっての適正な会計処理と正しい決算書の重要性とは?
- 決算書をみる時に意識すべきこと、注意すべきポイントとは?
- 決算書を見る時の視点やポイントとは?
- 企業会計について最低限、意識して学ぶべきこととは?
- 会社経営における会計知識の必要性とは?
- 労働問題
- 着服金額が僅少でも解雇有効となった裁判
- 熱中症対策義務化について
- 退職者から給与の支払日を指定された場合
- すべての事業場がストレスチェック義務化へ
- 初任給の急な引き上げが困難な場合
- カスハラ指針の内容とは
- セクハラ被害者の二次被害について
- いわゆる「自爆営業」はパワハラなのか
- 新卒の入社予定者に配属先を確約することについて
- 育休から復職の際、有給消化して退職することは可能なのか
- 「同僚と給与の話をしたら減給」は可能なのか
- 異業種進出の場合、事業場として就業規則の作成等が必要となるのか
- 終業時間後の残業を個人事業として行わせることについて
- 発達障害を理由とした雇止めはできるのか
- 休憩時間が労働時間とみなされる場合とは
- 労基署はハラスメント相談に乗ってくれない
- 育休を延長する場合の手続き厳格化について
- フリーランス新法とは②
- フリーランス新法とは①
- 適切な自宅待機命令の長さとは
- 配置転換が無効となるケース(最高裁)
- 「労働条件明示のルール」変更について
- 「自己研鑽」は労働時間に含まれないのか
- 飲食をともにした後にお礼メールを送り、その後セクハラと訴えたら認められるのか
- カスハラを受けた社員は労災の対象となるのか
- 業務委託契約を結ぶ者に労災は適用されるか
- 入社した社員の提出書類に虚偽があった場合、解雇可能か
- 深夜業務の多い社員には健康診断を年2回実施する必要があるのか
- 忘年会が労働時間にカウントされる?
- 「106万円の壁」対応でなぜ配偶者手当の見直しが必要なのか
- 就業規則違反の内容と懲戒処分の重さが均衡でない場合のリスク
- 懲戒処分を行わない場合のリスク
- 職場のトイレの使用制限を違法とした最高裁判決
- 定年再雇用の賃金に関する最高裁判決
- ハラスメントに時効はあるのか
- アウティングとは
- 退職願を提出しない社員への対処法とは?
- 契約社員に試用期間を設けることはできるか?
- 障害者雇用率の引上げ等について
- 障害者の雇用状況に改善が見られない場合の社名公表について
- 前払退職金制度のメリット・デメリット
- 無期転換ルールの改正予定について
- 裁量労働制の改正予定について
- エアコンの使用禁止は認められるのか
- 割増賃金と割増賃金の算定基礎となる賃金について
- 賃金支払い5原則について(2023年4月解禁のデジタル給与の支払いに向けて)
- 従業員の産休、育休について
- 【メンタルヘルス】復職後に確認すべきこと
- 【メンタルヘルス】復職の際に確認すべきこと
- 【メンタルヘルス】休職中に確認すべきこと
- 【メンタルヘルス】休職発令の前に確認すべきこと
- 労働者を雇用する際の労働条件の明示事項について
- 試用期間と試用期間中の社会保険について
- 2022年10月からの社会保険の加入対象者の拡大について
- 債権差押命令が届いた場合の対応
- 企業型確定拠出年金の制度や仕組み、法律について
- 労基署から労働条件に関する調査の実施という通知が来た
- 退職時に引継ぎをしない社員に賠償を求めることができるか
- 休職中に労働者を解雇することはできるのか
- 2022年10月1日職業安定法改正のポイント1
- 2022年10月1日職業安定法改正のポイント2
- 2022年7月8日女性活躍推進法改正について
- 2022年10月からの社会保険料免除要件の改正
- 2023年4月からの中小企業に対する割増賃金の引上げについて
- 男女間の賃金格差の開示が義務化
- 転勤制度廃止によるメリット・デメリット
- 2022年10月からの社会保険の拡大適用について
- 2022年4月からの女性活躍推進法改正について
- 給与から税や保険料以外のものを控除する場合
- 育児休業中に賞与を支給する場合
- 36協定の届出先は登記上の住所と実態のある住所のどちらを管轄する労基署か
- 法改正による私傷病休職や退職者について留意すべき事項
- マルチジョブホルダーの適用者が出た場合
- 通勤における合理的な経路及び方法とは
- 退職証明書の交付を求められた場合
- 求人募集において記載が認められない内容にはどのようなものがあるか
- 求人募集において労働条件はどこまで記載しなければならないか
- パートタイマーの所定労働日数が週により異なる場合の有給は
- 出張の定義とは
- 身だしなみはどこまで求めることができるのか
- テレワーク勤務者に禁煙を求めることができるのか
- テレワークにおける中抜け等について
- テレワークの際の情報セキュリティ対応について
- テレワーク中に負傷等した場合の取扱い
- テレワーク下におけるメンタルヘルスの問題
- 通勤手当と交通費の違い
- ワクチン休暇を導入する際の留意点
- 労働契約法の5年ルールに関する訴訟について
- 育休から復職後に出向等させたらマタハラとなるのか?
- 障害者雇用率の変更
- 中途採用比率の公表義務化
- 押印が省略される書式について
- 36協定の書式変更について
- LGBT社員が受ける「SOGIハラ」とは? その問題点は?
- テレワークにおける「リモハラ」で注意するべきポイントとは?
- 子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得において一部社員を対象から除外する場合の注意点(育児・介護休業法施行規則等の改正)
- 子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得に関する留意点(育児・介護休業法施行規則等の改正)
- 非正規社員への賞与の不支給は合理的判断か?(最高裁判決)
- 非正規社員に対する退職金の不支給は是か非か?(最高裁判決)
- 社員のメンタルヘルスに関する相談はどこにすればいいのか?
- フレックスタイム制適用者に営業会議への出席を命じることは可能か?
- 副業・兼業に関するガイドラインの改定内容(健康管理)を解説
- 副業・兼業に関するガイドラインの改定内容(労働時間管理)について
- 解雇予告後の社員の有給使用は認めるべきか?
- 社員がうつ病に罹患していなくても会社に慰謝料の賠償が命じられた裁判例
- フレックスタイム制で休日労働をした場合の割増賃金について
- 自転車通勤を認める場合の留意点とは?
- 早期退職優遇制度と希望退職制度の違いについて
- 会社が倒産した場合の未払賃金立替払制度とは?
- 妊娠中の女性社員が在宅勤務を希望する場合
- 雇用調整助成金の休業手当の算出方法
- 70歳就業が努力義務へ
- 退職する場合はいつでも2週間前でよい
- テレワークの種類と導入にあたり検討すべき事項とは?
- テレワーク導入で留意すべき労働時間管理
- 民法改正で身元保証書の内容をどう変更すればいいのか?
- 賛否両論!?男性の育児休業制度の仕組みとは?
- 副業している社員の労災認定に関する新制度の注意点とは?
- 未払残業代等の賃金請求権が3年になる!?企業が注意するべきポイントとは?
- 残業代の計算式を間違えるリスクとは?
- パワハラとモラハラの違いとは?
- パワハラに該当する例、該当しない例とは?
- 「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」の内容について
- 派遣労働者の「同一労働同一賃金」対応で「労使協定方式」を採用する際、「賃金の同等以上を確保する」ための比較方法とは?
- 派遣労働者の「同一労働同一賃金」対応で、「労使協定方式」を採用する際の退職手当の取扱いに関する注意点とは?
- 派遣労働者の「同一労働同一賃金」対応で「労使協定方式」を採用する際の通勤手当の取扱いでの注意点とは?
- 派遣労働者の「同一労働同一賃金」対応で「労使協定方式」を採用する際の賃金の決定方法での注意点とは?
- 派遣労働者の「同一労働同一賃金」対応における「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の違いとは?
- 派遣労働者の「同一労働同一賃金」への対応の注意ポイントとは?
- バイトテロへの効果的な対策とは?
- 役職定年制の新規導入における注意点とは?
- 就活に伴うOB訪問を受ける際の企業の留意事項とは?
- 退職代行会社から退職届が届いた場合の対応について
- 固定残業代の時間数が社員によって異なるのは違法か?
- アルバイトへの賞与不支給は違法か?
- 年次有給休暇管理簿に記載すべき事項とは?
- 年次有給休暇5日分を買い取れば会社は取得義務を果たすことになるのか?
- 36協定の起算日と給与計算期間がずれていた場合の問題点とは?
- 中途入社社員の残業単価の計算方法とは?
- 社員の給与の前借りは認めるべきか?
- 社員の有給休暇の前借りは認めるべきか?
- 会社でパワハラ相談を受けた場合の対応について
- 一般企業における近年の「パワハラ事件」まとめ
- パワハラに該当する具体的な行為とは?
- パワハラの法制化についての具体案や取組とは?
- 有給の消化順序と半日単位有給への変更について(働き方改革関連法案対応)
- 有給休暇の時効(取得期限)と付与される要件について(働き方改革関連法案対応)
- 働き方改革関連法案が規定する「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」の内容とは?
- 働き方改革関連法案における「不合理な待遇差をなくすための規定の整備」の内容とは?
- 割増賃金引上げ
- 残業時間の上限規制
- 働き方改革関連法案が定める「勤務間インターバル」の内容とは?
- 働き方改革関連法案で義務化される「労働時間の把握」に関する注意点とは?
- 働き方改革法案で義務化される年次有給休暇5日以上の取得に関する注意点とは?
- 働き方改革関連法案で経営者が注意するべきポイントとは?
- 競業避止義務契約を有効にするためのチェックポイントとは?
- 労働条件通知書に明示すべき事項とは?
- 1か月平均所定労働時間の正しい考え方と計算方法とは?
- 会社に人材を紹介した社員に対して紹介料を支払う際の注意点とは?
- インセンティブと賞与の違いとは?
- 会社の健康診断の費用は誰が負担するべきか?
- 従業員の労働時間の把握は企業の義務なのか?
- 退職者に賞与を支払う場合の注意点とは?
- 変形労働時間制の1か月単位と1年単位の違いと導入時の注意点
- 就業規則の絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項の違いとは?
- 非正規社員に扶養手当などを支給しないことは違法か?
- 労使協定等における従業員代表(過半数代表)に該当する要件とは?
- 年次有給休暇の買い上げにおける注意ポイントとは?
- パワハラを規制する法令がない理由とは?
- 働き方改革における高度プロフェッショナル制度の問題点とは?
- 会社が倒産…社員が利用できる未払賃金立替払制度とは?
- ハラスメントの発生が招く会社のリスクとは?
- 働き方改革における企画業務型裁量労働制の注意ポイントとは?
- 働き方改革におけるフレックスタイム制の見直しの問題点とは?
- 勤務地限定社員制度のメリットとデメリットとは?
- 高額報酬者に残業代の支払いは必要か?
- 契約社員との契約を更新しない場合の留意点とは?
- 週休3日制の導入で注意すべき点とは?
- 手続きを簡略化できる労基署への本社一括届出制度とは?
- 労働条件が求人内容と違うと苦情を申立てた従業員への対処法とは?
- 福利厚生を導入する際、就業規則に記載するべきか?
- 兼業を認める場合の注意点とは?
- 賞与の減額や不支給はどこまで認められるのか?
- 就業規則における昇給に関する規定の注意点とは?
- 短時間正社員制度を導入する際の注意点とは?
- 当月控除しきれない社員の減給の取扱い方法とは?
- 産業医の定期巡視の頻度に関する法改正の内容とは?
- 労働基準監督業務の民間活用で何が変わるのか?
- 労使協定における過半数代表者の任期に規定はあるのか?
- 在宅勤務制度を導入する際の注意点とは?
- 新卒社員に裁量労働制は適用できるか?
- 法定内残業にも割増賃金を支払うべきか?
- 深夜残業後の休暇は認められるか?
- 勤務間インターバル制度とは?
- プレミアムフライデーへの対応の注意点とは?
- 従業員手当を新たに支給する際の注意点とは?
- 同一労働同一賃金で待遇差が問題になる場合とは?
- 同一労働同一賃金とは?
- マタハラ防止措置が義務化!2017年から運用されるのマタハラ防止措置の指針とは?
- 改正育児・介護休業法のポイントとは?
- 提出日を守らない退職届は社員に返却できるか?
- 36協定の特別条項における残業時間の上限とは?
- 平成28年10月1日からの最低賃金引き上げで実務上留意すべき事項とは?
- 派遣社員にも裁量労働制を適用できるのか?
- 有給休暇に別途手当等を支給する必要はあるのか?
- 残業時間の計算は1分単位で行うべきなのか?
- 女性の取締役が産休に入る場合の手続きとは?
- 定年再雇用で今後留意すべきポイントとは?
- 振替休日が月をまたいだ場合の割増賃金計算の方法とは?
- 新たに改正された傷病手当金の計算方法とは?
- 固定残業代制度を有効にするための要件・ポイントとは?
- 「かとく」と労働基準監督署の違いとは?
- 労働者派遣事業の区別廃止で必要となる対応とは?
- 「改正特許法」施行で就業規則の見直しが必要?
- 「女性活躍推進法」施行で会社はどう対応するべきか?
- 労働基準監督署の「是正勧告書」の交付。これを無視するとどうなる?
- 遅刻したが、その分勤務した社員の給与カットは可能か?
- 減給処分をした社員の給与が最低賃金を下回っても問題はないのか?
- 育児休業中に転職しても給付金が支給される条件とは?
- 育児休業期間に就業した場合の給付金の取り扱いとは?
- 従業員の給料と最低賃金の比較方法とは?
- 従業員の長期休暇はどこまで認めるべきか
- 雇用保険が適用される労働者の範囲とは?
- 義務化されたストレスチェック制度の概要とは?
- 会社が選任する産業医の探し方、選び方とは?
- 「あっせん開始通知書」が届いた場合の対処法とは?
- 社員からの諸手当の申請には遡って対応するべきか?
- マイナンバーで会社がとるべき安全管理措置対応とは?
- マイナンバーへの対応で企業が留意するべきポイントとは?
- 社員の試用期間を延長する際に留意すべき点とは?
- パートから正社員に転換した場合の有給休暇の取扱いはどうする?
- 入社時健診の実施日と近い場合、定期健診は受けなくてもいいか?
- 有給休暇の半休取得者からの残業代請求にどう対応するか?
- 非常勤役員でも社会保険は適用されるのか?
- パートタイマーにも賞与を支払わなければいけないのか?
- うつ病で休職している社員の復職希望に対してどのように対応すればいいのか?
- 労働保険未加入時の従業員の労災事故では保険給付は行われないのか?
- 自己都合で退職する従業員を失業保険の給付で有利になるように解雇扱いにしても問題はないのか?
- 譴責処分(けん責処分)とは?譴責処分の意味・譴責処分通知書・事例を解説
- パートタイム労働者は社会保険に加入しなくてもいいのか?
- 就業規則に規定する懲戒処分にはどのような種類があるのか?
- 会社に社員がいなくなった場合、社会保険から脱退することはできるか?
- 必要書類の提出を拒否した採用内定者の内定を取り消すことはできるか?
- 会社帰りに負ったケガは労災になるのか?通勤労災とは?
- 採用内定者の履歴書に虚偽記載を見つけた場合、内定取り消しできるのか?
- 試用期間満了時に従業員を辞めさせたり、試用期間の延長をすることはできるか?
- 従業員の身元保証人にはどのような範囲で責任が問えるのか?
- 採用時に明示する労働条件は、どの程度、どのように明示したらいいのか?
- 求人票を出したあと会社側の都合で労働条件を変更できる?
- 退職者に仕事の引き継ぎをしてもらいたい場合の有給休暇の取扱いとは?
- 労働審判とはどのような制度なのか?会社として注意するべき点とは?
- 労働契約(労働条件)が異なる会社同士が合併する場合、 会社と従業員の労働契約はどうなる?
- 希望退職の募集をする際どのような注意点があるのか?
- うつ病の社員を解雇することはできるのか?
- 自己都合から会社都合への退職理由の変更にはどのような違いとリスクがあるのか?
- 労働組合のビラ配りや街宣活動にはどのように対処したらいいのか?
- 採用の内定取り消しができるのはどのような場合か?
- 従業員が仕事以外で逮捕・起訴された場合、懲戒処分することは可能か?
- 問題社員に対して会社は、けん責、減給、降格などの懲戒処分を自由に行うことができるか?
- 従業員がマイカーで営業に行く途中事故を起した場合は会社の責任か?
- 従業員の持ち帰り残業に割増賃金を支払う必要はあるのか?
- 工場が焼失した場合、従業員へ休業手当を支払う必要があるのか?
- 来年の新卒採用者から今までの初任給より金額を下げるには?
- 就業規則に金額を明記していない場合、退職金を支払う義務はあるのか?
- 定年を迎えた従業員に引き続き仕事をしてもらうにはどうすればよいか?
- 医療法務
- 医療税務
- 商標
- 国際税務
- 相続税
- 税務
- 組織再編税制
- 請求書
- 身近な法律解説
- 身近な法律解説(全文表示)
- 未分類
- 民法改正
- 寄託に関する見直し【民法改正のポイント】
- 請負に関する見直し【民法改正のポイント】
- 消費貸借に関する見直し【民法改正のポイント】
- 危険負担に関する見直し【民法改正のポイント】
- 契約の成立に関する見直し【民法改正のポイント】
- 契約に関する基本原則の明記【民法改正のポイント】
- 弁済に関する見直し(第三者弁済)【民法改正のポイント】
- 相殺禁止に関する見直し【民法改正のポイント】
- 債務引受に関する見直し【民法改正のポイント】
- 連帯債務に関する見直し【民法改正のポイント】
- 債務者の責任財産保全のための制度【民法改正のポイント】
- 原始的不能の場合の損害賠償規定の新設【民法改正のポイント】
- 契約解除の要件に関する見直し【民法改正のポイント】
- 債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化【民法改正のポイント】
- 代理に関する見直し【民法改正のポイント】
- 意思表示に関する見直し【民法改正のポイント】
- 意思能力制度の明文化【民法改正のポイント】
- 定型約款に関する規定の新設【民法改正のポイント】
- 債権譲渡に関する見直し【民法改正のポイント】
- 保証に関する見直し【民法改正のポイント】
- 法定利率に関する見直し【民法改正のポイント】
- 消滅時効に関する見直し【民法改正のポイント】
- 賃貸借に関する見直し【民法改正のポイント】
- 売主の瑕疵担保責任に関する見直し【民法改正のポイント】



