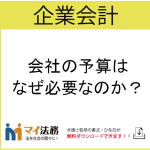相続等で取得した未利用となっている土地は、安い価格で売ることも難しく、処分費用がかかり譲渡所得も課税されることが未利用地を処分できない要因となっています。
国は空き家や未利用地の問題を解消する施策の一つとして、売却代金が低い土地等を譲渡した際に100万円を控除できる制度を時限的に設けていますので、今回は「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の概要
「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(措法第35条の3)」は、個人が低未利用土地等を譲渡した際に、特別控除として100万円を差し引くことができる制度です。
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡した土地等が対象で、都市計画区域内にある低未利用土地等を、一定の金額以下で売却した際に適用できます。
「低未利用土地等」とは、居住用や事業用、その他の用途に利用されていない土地または、利用程度がその周辺地域における同一の用途もしくは、これに類する用途に利用されている土地の利用程度に比べて、著しく劣っている土地や低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。
自宅や事業用の敷地として供している土地に対しては適用できませんが、未利用地を譲渡した際に適用できるのが本特例の特徴です。
低未利用土地特別控除の適用要件
低未利用土地特別控除の適用要件は、次の通りです。
<適用要件>
- ●売却した土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること
- ●売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超であること
- ●買手が特別関係者でないこと
- ●売却代金が低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下または、低未利用土地等が次に掲げる区域内にあるときは800万円以下であること
- ・市街化区域
- ・区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
- ・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域
(上記に掲げる区域を除く)
- ●売却後に低未利用土地等が利用されること
- ●特例適用する低未利用土地等と一筆であった土地から、前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年に本特例を適用していないこと
- ●売却した土地等について、固定資産の交換特例や収用等の場合の特別控除、事業用資産の買換特例など、他の譲渡所得の特例を適用していないこと
特別関係者には、親子や夫婦以外に、生計を一にする親族や内縁関係にある人、特殊な関係のある法人などが含まれます。
売却代金は原則500万円以下となりますが、市街化区域など一定の区域内にある低未利用土地等については、売却代金の上限が800万円に引き上がります。
低未利用土地特別控除を適用する際の譲渡対価の判定方法
低未利用土地控除を適用する際の売却代金は、実質的に低未利用土地や低未利用土地の上に存する権利の譲渡対価として支払われたものをいいます。
名義上は譲渡協力金や移転料等であったとしても、譲渡の対価として支払われた金額については、売却代金(譲渡の対価の額)に含まれるので注意してください。
また、譲渡対価の500万円または800万円を超えるかの判定は、次の事例に従って行います。
(事例)
共有の低未利用土地等を譲渡
(判定方法)
所有者ごとの譲渡対価により判定
(事例)
低未利用土地等と、低未利用土地等の譲渡とともにした低未利用土地の上にある資産の所有者が異なる
(判定方法)
低未利用土地等の譲渡対価により判定
(事例)
低未利用土地と低未利用土地の上に存する権利の所有者が異なる
(判定方法)
所有者ごとの譲渡対価により判定
(事例)
同一年中に特例を適用する低未利用土地等が2以上ある場合
(判定方法)
低未利用土地等ごとの譲渡対価により判定
低未利用土地特別控除の要件が異なる区域の土地等を譲渡した場合の判定方法
譲渡した一団の低未利用土地等が、売却代金500万円と800万円の要件の区域に所在する場合、それぞれの区域に所在する土地等の売却代金を面積按分するなど、合理的な方法により算定した価額で売却代金の判定を行います。
なお、面積による算定が困難な場合については、低未利用土地等の総面積の半分を超える区域に低未利用土地等が所在するとして、本特例を適用することが可能です。