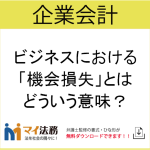帳簿や書類の保存など、経理の電子化における注意ポイントについて教えてください。
【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
業務の効率アップに取り組む経営者や自営業者の中には「経理の電子化」に注目している方も多いでしょう。
一方で、帳簿や領収書の電子保存は新しい仕組みのため勘違いしやすく、税務調査時に指摘される可能性もあります。
そこで今回は、経理の電子化における注意ポイントについて解説します。
会計帳簿を電子で作成して保存するメリットとは?
近年では、中小企業なら「勘定奉行」、自営業者なら「freee」のような会計システム/クラウド会計ソフトで決算に関わる帳簿・書類を管理するのが当たり前になってきました。
さらに最近では、クラウド会計ソフトで作成したデータや、電子機器でスキャンした領収書などをネットワーク上に保管しておく「電子保存」が広まっています。
電子保存のメリットとしては、デジタル化による「作業の効率化」、保管場所がいらない「省スペース化」などが挙げられます。
帳簿、請求書、領収書などはファイリングが必要のため、どうしてもある程度のスペースをとりますが、電子保存を行なうことで特に手狭なオフィスの会社や、自宅兼オフィスの自営業者は省スペース化を実現することができます。
電子保存は税務署への申請が必須
少し前まで、領収書の電子保存については「記載金額が3万円未満」という決まりがあったのですが、平成27年度の税制改正ですべての請求書・領収書が電子保存できるようになりました。
さらに電子保存のためには、本格的なスキャナーで読み込まなくてはならない決まりがありましたが、平成28年度の税制改正でスマートフォンでの読み込みも可能になりました。
ただし、電子保存については、税務署に予め申請しなければ認められません。
意外に知らない方も多いので注意が必要です。
まだ申請していない方、これから電子保管をしたい方は国税庁のサイトを参考にするとよいでしょう。
[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/10.htm
申請書類のpdfも用意されています。
電子保存は意外に要件が細かいため、まずは税理士に相談することをおすすめします。
帳簿・書類の保存期間は7年間
国税庁の規定では、法人は取引記録や取引のために自社で作成した書類、取引先から受け取った書類などを「7年間保存」する義務があります。
決算関係、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿類、領収書の保存期間も7年間となっています。
重要な書類はすべて「7年間保存しておけば間違いない」と覚えておくとよいでしょう。
ちなみに、