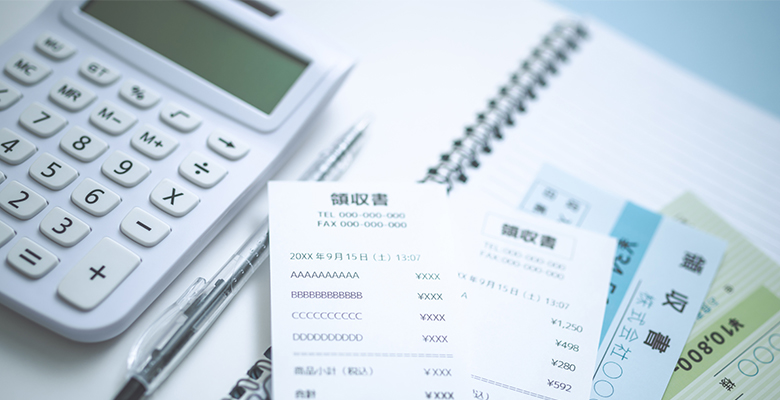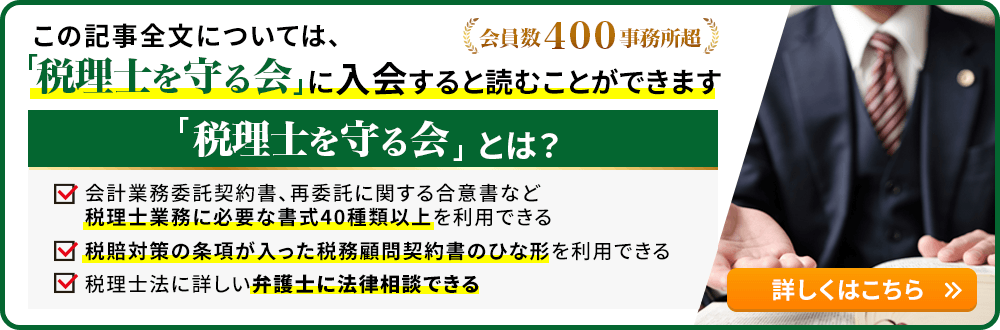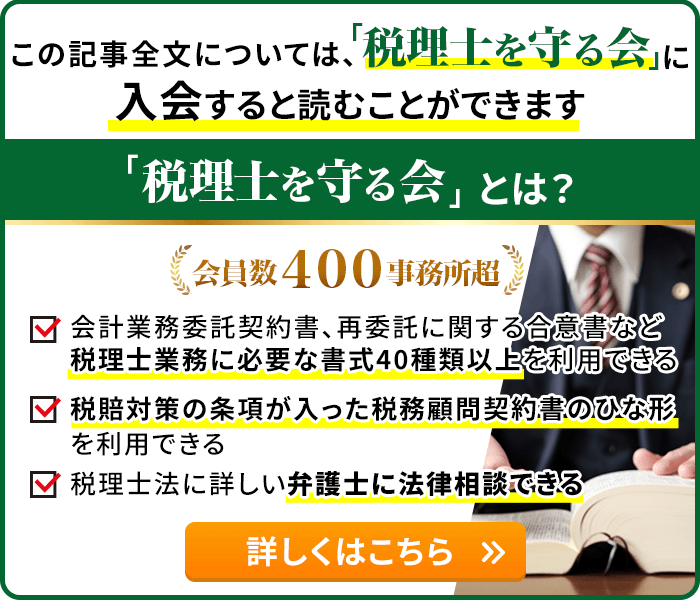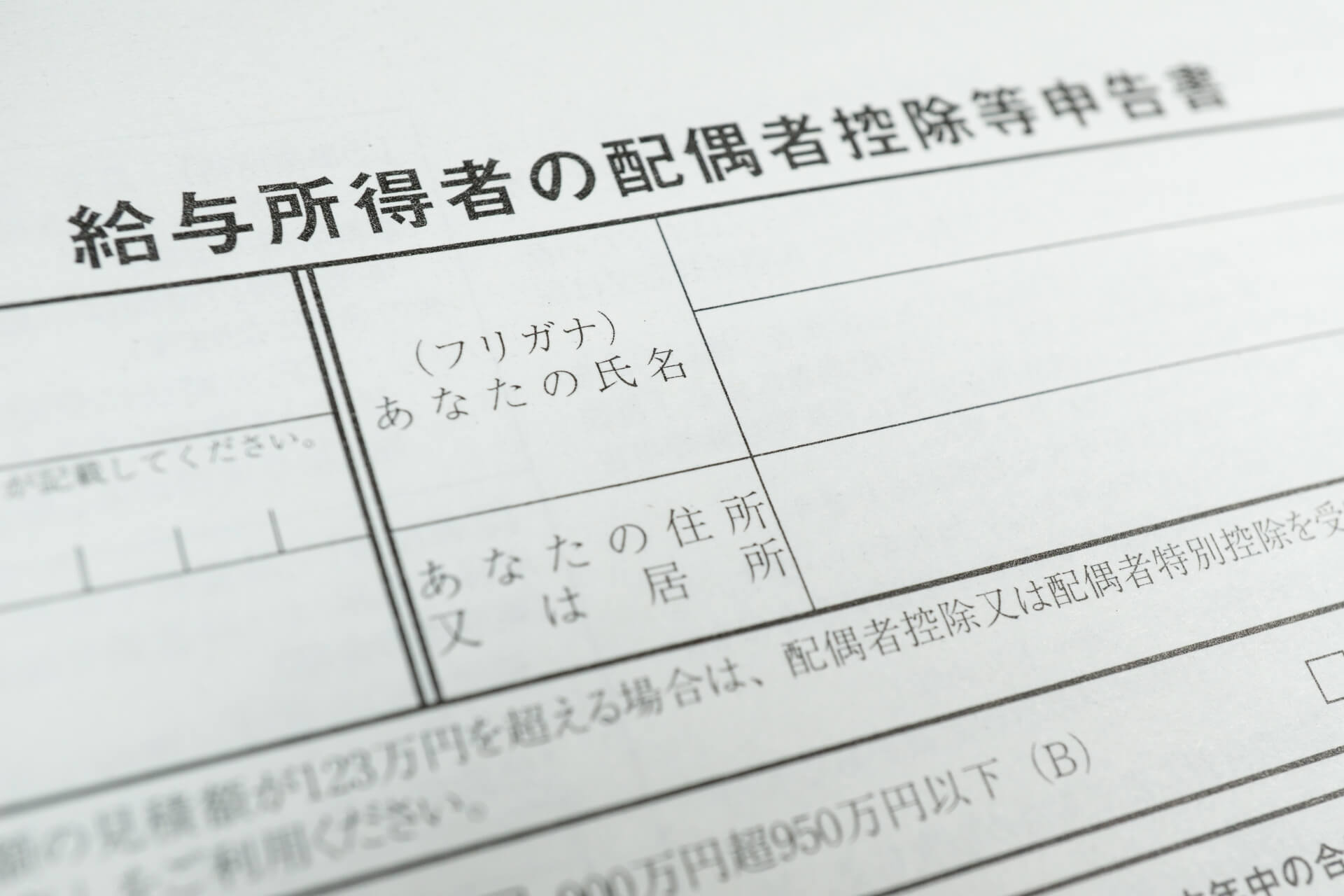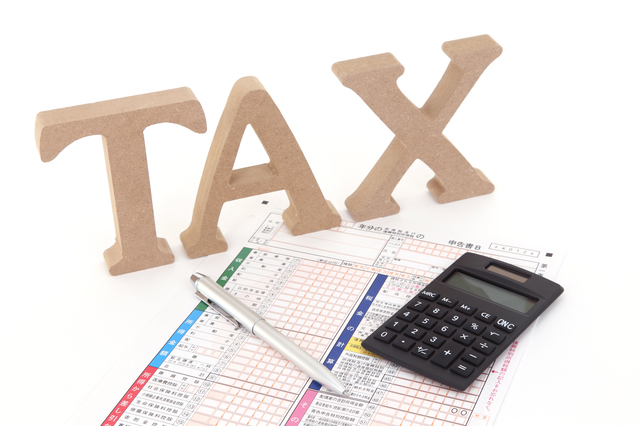税理士事務所は、税務申告業務の一環として記帳代行業務を受けることもありますが、会計法人(記帳代行会社)を設立し、記帳代行業務を別の法人で行う方法もあります。
ただ税理士事務所が会計法人を設立し記帳代行業務を行う場合、税理士ならではの問題点があるのでご注意ください。
目次
税理士法人が行える税務業務の範囲
税理士法人が行える業務は、税理士業務および、税理士法第2条第2項の業務その他これに準ずるものです。
税理士法第2条第2項の業務には、税理士業務に付随して行う財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行なども含まれるため、確定申告に関連した記帳代行を担うことも可能です。
また税理士法基本通達48の5-1では、税理士業務に付随しないで行う財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行などについても業務範囲内であると規定されています。
ただ税理士業務と関係のない範囲(不動産貸付業や飲食店経営など)まで、業務範囲を広げることはできません。
なお一般の記帳代行業務は税理士の独占業務に含まれないため、非税理士の会計法人でも記帳代行業務を行うことは法律上認められています。
税理士事務所が記帳代行会社を設立する際に起こりうること
顧客が記帳代行と税務業務の双方を依頼してきた場合、税理士事務所が顧客と一括契約する方法と、税理士事務所と記帳代行会社のそれぞれで契約する方法の2種類あります。
税理士が税理士業務と記帳代行業務を一括して受ける場合、税理士事務所は記帳業務を記帳代行会社へ外注することになりますが、外注が税理士法違反にならないよう気をつける必要があります。
また税理士事務所と記帳代行会社の双方で契約する場合、代行業者と税理士事務所とで直接記帳情報のやり取りをすると、守秘義務違反になる可能性にも注意しなければいけません。
税理士事務所から記帳代行会社へ外注する際の5つの注意点
税理士が顧客と一括契約を結んだ場合、税理士事務所は記帳代行会社と業務委託契約または外注契約を行います。
外注自体は問題ではありませんが、5つ注意しなければいけないポイントがあります。
【1】税理士の守秘義務規定に抵触する恐れ
税理士法第38条では守秘義務の規定があり、税理士業務に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはいけません。
税理士事務所が一括して税務業務を引き受けた場合、記帳代行会社に記帳業務を依頼することは税理士業務で知り得た顧客情報を外部に渡すことになるため、守秘義務違反に該当する可能性があります。
【2】税理士は複数の事務所を設置できない
税理士法第40条では、税理士は2つ以上の事務所を設けることはできないと規定されています。
記帳代行をするために設立した会計法人の社員が税理士事務所の業務を行う場合、複数の事務所を設けたものと認定される恐れがあります。
また税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けることはできません。
【3】従業員の管理監督問題
記帳代行会社へ委託した場合、記帳代行会社の従業員の管理監督問題が発生します。
記帳は多くの個人情報が含まれているため、・・・・・