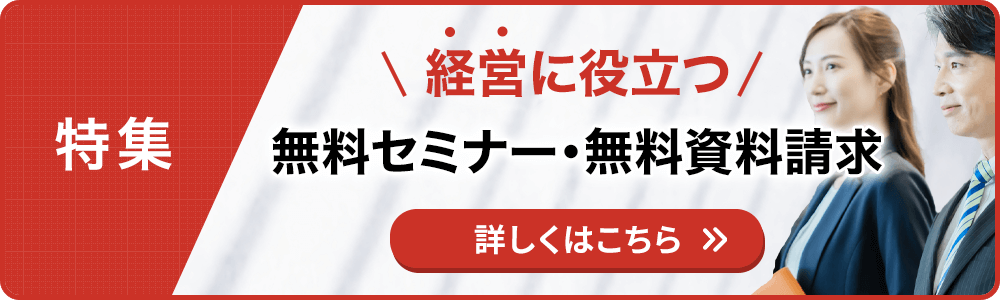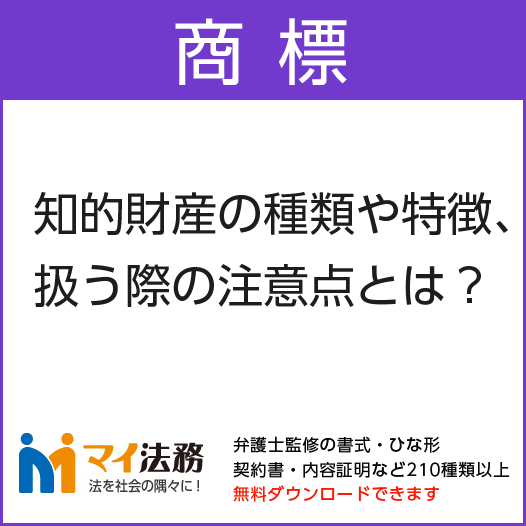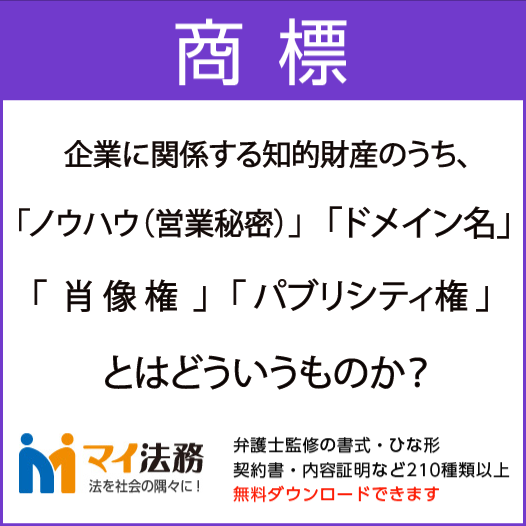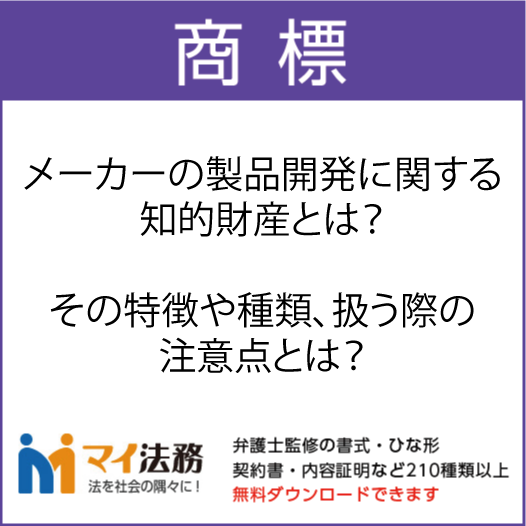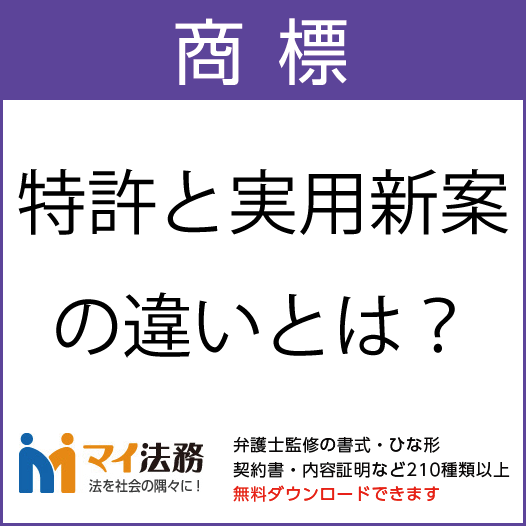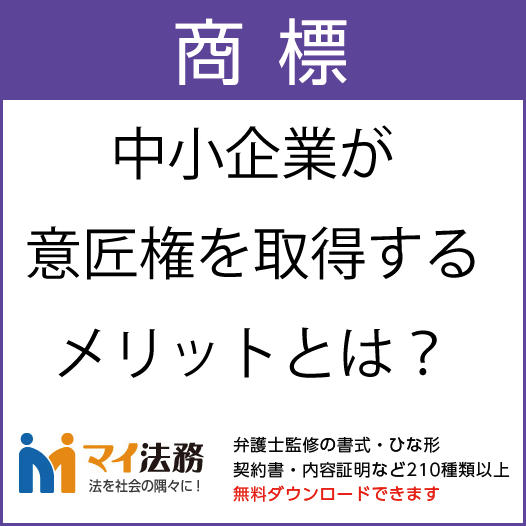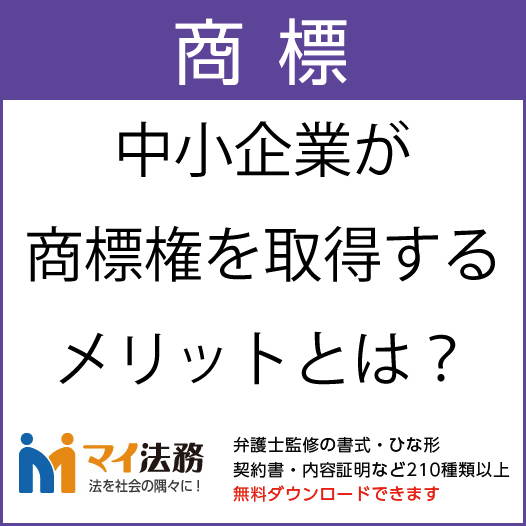中小企業は、どのような場合に特許権を取得するべきでしょうか?
【この記事の著者】 アイラス国際特許事務所 弁理士 高橋洋平
http://www.irus.jp
特許権を取得するメリットとデメリットを理解すれば、特許権を取得すべき場合が見えてきます。
特許権を取得するメリット
①「特許技術の独占実施権」
自社開発した特許技術を含む製品(特許製品)や製法(特許製法)を自社のみが独占的に販売又は使用等することができます。
その結果、需要者は、競合他社から自社特許製品と同等製品を購入することができず、他社との相見積等による価格競争から脱出できます。
②「自社製品の宣伝広告効果」
「特許製品」、「特許製法」、「特許○○○号」など「特許」が記載された宣伝広告は、その言葉から想起させる「優れた製品」というイメージから、競合品と比較して大きな顧客吸引力を得ることができます。
その結果、市場で同様の製品が流通していても、「特許」という言葉だけで需要者からの反応が大きく変わり、売上に貢献します。
③「自社製品の取引信頼性」
自社製品が特許権で保護されていれば、他社から特許権侵害による実施差止のリスクを減らすことができるので、販売元やOEM元との取引の際に、その相手方に大きな信頼感を与え、業務提携契約を優位に運べることができます。
特許権を取得するデメリット
①「費用がかかる」
日本国内での特許権取得には、50~80万円が必要です。
また、特許権の存続期間は、原則、最大で20年間ですので、特許料という維持年金を特許庁に毎年支払わなければなりません。
(1~3年間:約1万円、1~10年間:約25万円、1~20年間:約120万円)
そのため、特許を希望する技術を含む製品がこの費用をペイできない売上しかないのであれば、特許権を取得しないという選択肢もあります。
②「短期的使用でのコスト回収が困難」
特許権取得には、どんなに早くても出願日から半年間、一般的には年単位での期間を要します。そのため、自社製品が数か月~数年程度の計画的短命製品の場合、特許権取得前に自社製品の販売が終了してしまいます。
しかし、短期集中販売の場合、他社の模倣品に対して自社が