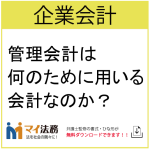企業活動を安定的に継続するには、予期せぬ資金不足への備えが欠かせません。
いざという時に資金が尽きる事態を避けるためにも、平時からの準備と具体的な対応を整えておくことが重要です。
本記事では、万が一の資金ショートに備えて、予備費の活用方法と実務的な資金調達手段について詳しく解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
緊急時に備える資金繰りの基本戦略
突発的な支出や収入減に直面した場合、事前の備えが資金繰りの明暗を分けます。
資金繰り悪化の主な原因と兆候
資金繰りが悪化する要因は、売上減少や売掛金の回収遅延など、複合的な要素が重なることによって生じます。
月次の入出金バランスが崩れるのみならず、突発的な設備投資や税金納付が重なることで、資金繰りが逼迫するケースも少なくありません。
もっとも、資金繰りが突然悪化するケースは稀であり、手元資金の継続的な減少や、支払猶予の依頼が増えるといった兆候が先行することが多いです。
こうした兆候が表面化する前段階での早期対応が、資金ショートの未然防止につながります。
中小企業が陥りやすい資金ショートのリスク
中小企業では、資金計画が不十分なまま業務を進めてしまう傾向があります。
季節変動に伴う収支の波や、売上への依存度が高い経営体質の場合、資金ショートに陥るリスクが高まりやすくなります。
さらに、大企業と比較して信用力が低いため、信用調査や融資交渉への準備不足が資金調達の遅れにつながる要因となることもあります。
予備費の重要性と企業内での備え方
企業経営において、突発的な支出への対応力は、事業を継続するうえで欠かせない要素です。
予備費の定義と使い方
予備費とは、予定外の支出や収入減に備えて、社内であらかじめ確保しておく資金のことをいいます。
災害や急な売上減少、設備故障などの不測の事態に対して、迅速かつ柔軟に対応するために活用されます。
また、予備費を運転資金とは分けて管理することで、予期せぬ支出にも柔軟に対応でき、経営を安定させることにつながります。
予備費の運用ルールと管理体制
予備費は単なる貯蓄ではなく、目的や使用条件を明確に定めたうえで管理する必要があります。
活用にあたっては、使用理由と金額の妥当性を社内で検証し、運用ルールを定期的に見直すことが求められます。
また、予備費の活用を前提とした経営には一定のリスクが伴うため、乱用を防ぐ管理体制や使用後の報告手続きも整備しておくことが重要です。
緊急資金調達手段と選定ポイント
企業は、資金ショートの兆候を捉えた段階で、迅速かつ適切な調達手段を選定する必要があります。
資金繰り悪化の連鎖を防ぐためにも、調達元ごとの条件の違いを理解しておくことが求められます。
社内資金の再配分と自己資金の見直し
緊急時には、まず社内で確保済みの自己資金や留保資金を再確認することが重要です。
不要な支出の圧縮や運転資金の再配置によって、一時的なキャッシュ不足に対応できる可能性があります。
資金の再配分によって社内で確保が可能となれば、外部調達への依存度を下げることができるため、まずは社内の状況を確認することが大切です。
金融機関からの短期融資
金融機関からの短期融資は、迅速性と信用力を兼ね備えた資金調達手段です。
事業計画や資金使途を明確に示すことで、審査の通過率を高めることができます。
一方で、融資の実行までには一定の時間を要するほか、審査を通過するためには事前準備が欠かせません。
そのため、資金調達の緊急度や事業の状況に応じて、他の手段との併用も視野に入れることが望ましいでしょう。
親族・取引先から支援を受ける
金融機関からの融資には一定の時間を要するため、即時性が求められる状況では、親族や信頼関係のある取引先からの支援も有力な選択肢となります。
ただし、口頭での確認だけでは後のトラブルにつながる恐れがあるため、借入契約書の作成や返済条件の明文化など、透明性のある対応が不可欠です。
政府系支援制度の活用
公的支援制度は、中小企業の資金調達を制度的に後押しする仕組みです。
状況に応じて、信用保証協会付き融資やセーフティネット保証制度などを活用し、資金調達することも可能です。
なお、各支援制度には適用条件が定められているため、事前に内容を把握したうえで活用の可否を検討する必要があります。
クラウドファンディング・ファクタリングの可能性
新たな資金調達手段として、クラウドファンディングや売掛債権のファクタリングが注目されています。
クラウドファンディングは、広範な支援者層に訴求して資金を調達できますし、売掛債権のファクタリングは、早期に資金調達できるメリットがあります。
ただし、いずれの手法も手数料や審査条件、資金調達までの期間などに違いがありますので、導入前には十分な比較と検討が必要です。