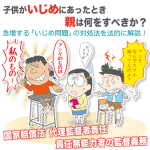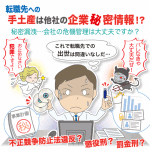中小企業では、役員との間で金銭の貸し借りが行われることがありますが、会計処理や税務対応を誤ると、損金否認や認定課税などのリスクにつながる可能性があります。
税務調査で指摘を受けないためには、契約内容や利息の設定、返済実態の管理を含めた適切な対応が欠かせません。
本記事では、役員貸付金・借入金に関する会計処理と税務上の注意点について、実務の視点からわかりやすく解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
役員貸付金・借入金の会計処理
役員との金銭の貸借は、企業の資金管理や財務諸表に影響を及ぼす取引です。
会計処理では、仕訳や利息の取扱いを正確に理解することが求められます。
貸付金・借入金の定義と仕訳処理
役員貸付金とは、会社が役員に対して資金を貸し付けたものであり、資産として「役員貸付金」勘定に計上されます。
一方、役員借入金は、役員から会社が資金を借り入れたもので、負債として「役員借入金」勘定に計上されます。
仕訳処理は、貸付時、返済時、利息発生時などの取引内容に応じて適切に行う必要があります。
特に期末残高の表示は財務諸表の信頼性に直結するため、正確な記録が不可欠です。
利息の認識と未収・未払利息の取扱い
役員との貸借取引において利息が発生する場合、会計上は発生主義に基づき、未収利息や未払利息を認識する必要があります。
たとえば、利息が計算期間に対応して発生しているものの、まだ役員から現金を受け取っていない場合には、未収利息として資産計上します。
一方、会社が役員に対して利息を支払う義務があるにもかかわらず、未払いである場合には、未払利息として負債計上します。
税務上の認定利息との整合性も考慮し、契約内容や実際の支払状況に基づいた適切な処理が求められます。
税務上における役員貸付金の注意点とリスク
役員との金銭取引は、税務署から脱税の疑いを持たれやすい領域です。
第三者との取引と同様に、契約内容、利率、返済実態などを明確にし、税務調査への備えを徹底することが求められます。
役員貸付金に対する税務調査
返済実績が乏しく、契約書や返済計画が存在しない場合、税務調査において実質的に給与や賞与の支払い(利益の流出)とみなされる可能性があります。
役員報酬は一定の条件を満たさなければ損金に算入できないため、貸付金の否認による影響は大きいです。
また、意図的に貸付金と装う行為は仮装や隠蔽行為と認定され、重加算税の対象となるため注意が必要です。
役報酬認定による所得税・源泉徴収の注意点
役員貸付金が報酬とみなされた場合、その報酬は役員の所得となります。
所得税の累進税率は法人税よりも高いため、追徴課税による役員個人の大幅な税負担が懸念されます。
また、法人に対しては、本来源泉徴収すべき税金を納めていなかったとして、不納付加算税の対象となる点にも注意が必要です。
役員貸付金の認定利息課税
役員貸付金に利息を設定していない、または利率が著しく低い場合、税務上は会社が受け取るべきであった利息相当額を収益として認識し、課税する「認定利息」という考え方があります。
これは、通常の取引であれば得られたはずの利益を会社が放棄したとみなされるためです。
認定利息は、税法で定められた利率(令和4年から令和7年は0.9%)などを基準に計算されるため、適正な利率を設定し、会計上も利息をきちんと計上することが求められます。
役員貸付・借入を行う際の社内管理のポイント
役員との金銭貸借は違法ではありませんが、税務上で指摘されやすい領域でもあります。
そのため、貸付・借入を行う場合には、税務調査に耐えうる運用を行うための社内管理体制の整備が不可欠です。
契約書・返済計画の整備と証憑管理
役員貸付金・借入金に関する契約書は、取引の正当性を示す基本資料です。
契約書には貸借金額、利率、返済期限、返済方法などを明記し、社内承認を得たうえで保管します。
加えて、返済計画表や実際の返済履歴、振込記録などの証憑を整備することで、税務調査時に取引の実態を客観的に証明できます。
これらの管理が不十分な場合、役員報酬として認定されるだけでなく、仮装や隠蔽行為と判断されるリスクも高まるため、十分な注意が必要です。