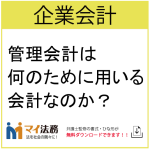土地の相続税評価額を算出する際には、画地補正が必要になる場合があります。
適用される補正の種類は土地の形状などによって異なり、補正計算を適切に行わなければ、正確な評価額は算出できないので注意してください。
本記事では、土地の相続税評価額の計算方法と、評価額が下がる補正の種類について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
相続税における土地の評価額の求め方
相続税における土地の評価方法は複数あり、土地が所在する地域によって用いる評価方法は異なります。
土地の評価方法は2種類
土地の相続税評価額の算出方法には、「路線価方式」と「倍率方式」があります。
相続財産の評価は、原則として時価で行われますが、納税者が相続税の申告書を作成する際に、すべての土地の時価を正確に把握するのは困難です。
そのため、国税庁は、相続税の申告の便宜および課税の公平を図る観点から、路線価方式または倍率方式によって算出した金額を相続税評価額にすると定めています。
<土地の評価方法の種類>
- 路線価方式
- 国税庁が定めた路線価に基づいて計算する方法。
- 評価対象地が接している路線価に、土地の面積を乗じて評価額を算出する。
- 倍率方式
- 固定資産税評価額に一定の評価倍率を乗じて計算する方法。
- 評価倍率は地域および地目ごとに設定されている。
路線価方式と倍率方式の違い
路線価方式は、国税庁が定めた路線価に土地の面積を乗じて相続税評価額を算出します。
土地が標準的な広さで、正方形または正方形に近い長方形の形状をしている場合、補正計算は不要です。
一方、形状が歪な土地や、標準的な土地と比べて極端に面積が広い・狭い土地は、価値が相対的に低下するため、土地の形状や道路の接面状況などを考慮した補正計算が必要になります。
倍率方式は、固定資産税評価額に評価倍率を乗じて相続税評価額を算出します。
評価倍率は、宅地・田・畑・山林など、地目ごとに定められており、路線価方式とは違い、基本的に補正計算は行いません。
ただし、雑種地に関しては評価倍率が定められていないため、個別に補正計算を行うことになります。
土地の補正計算の種類
路線価地域にある土地は形状等に応じて補正計算をすることになりますが、評価対象地が複数の道路に接している場合、相続税評価額が上がる可能性があります。
相続税評価額が下がる補正
土地の相続税評価額の主な減額補正は次の通りです。
土地の状況によっては、複数の減額補正が適用されるケースもありますし、適切な補正計算をするために、測量や土地の現地確認が必要になる場合もあります。
<減額補正の主な種類>
- 奥行価格補正
- 奥行が短い・長い土地に適用する補正
- 不整形地補正
- 形状が歪な土地に適用する補正
- 間口狭小補正
- 間口が狭い土地に適用する補正
- 奥行長大補正
- 間口に対して奥行が長い土地に適用する補正
- 規模格差補正
- 地積規模の大きな土地に適用する補正
- 無道路地補正
- 評価対象地が道路に接していない(接道義務を満たしていない土地を含む)場合に適用する補正
- がけ地補正
- 評価対象地にがけ地が含まれる場合に適用する補正
- 特別警戒区域補正
- 土砂災害特別警戒区域内に土地がある場合に適用する補正
- セットバック補正
- セットバックが必要な部分が含まれる土地に適用する補正
相続税評価額が上がる補正
土地の相続税評価額が増額される補正は、次の2種類です。
いずれも評価対象地が道路に二面以上接している場合に限り適用される補正であるため、評価対象地が道路に接しているのが一面のみの場合、「路線価×面積」で算出した評価額が最も高くなります。
<増額補正の種類>
- 側方路線影響加算
- 評価対象地の側面にも路線価が設定されて道路が接している場合に適用する補正
- 二方路線影響加算
- 評価対象地の裏面にも路線価が設定されて道路が接している場合に適用する補正