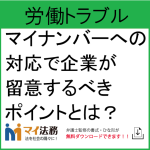動画解説はこちら
厚生労働省の研究班の調査(2013年)によると、65歳以上の高齢者のうち認知症の人は推計15%で約462万人。
さらに、発症の可能性のある400万人も含めると、4人に1人が認知症とその予備軍だということがわかりました。
また、警察庁の発表によると、2012年には認知症が原因で行方不明になったとの届け出が9607人分あり、そのうち231人は12年中に発見できず、13年に入ってから見つかったのは53人。死亡者は359人となっています。
認知症の症状には、記憶障害や見当識障害の他に徘徊があります。
介護をする人にとっては大変な問題です。
こうした認知症高齢者の徘徊による、ある痛ましい鉄道事故の損害賠償に関する判決が出されました。
事件はこうして起きた
「認知症で徘徊 JR東海事故 高裁も妻に賠償命令」(2014年4月25日 東京新聞)
2007年12月、愛知県大府市で徘徊症状がある認知症の男性(当時91)がJR東海の電車にはねられ死亡する事故が発生。
認知症で、要介護4の認定を受けていた男性は、妻と近所に住む長男の妻が少し目を離した隙に家を出て徘徊。
JRの駅構内に進入して電車にはねられたようです。
その後、同社が遺族に対して損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は、「見守りを怠った」などとして、男性の妻(91)に359万円の支払いを命じました。
この訴訟、昨年の一審判決では、妻と長男(61)にJR側の請求通り720万円の支払いを認定していましたが、二審では「JR側の駅利用客への監視が十分で、ホームのフェンス扉が施錠されていれば事故を防げたと推認される事情もある」、「妻は、男性の監督義務者の地位にあり行動把握の必要があった」とした上で、「男性が線路に入り込むことまで妻が具体的に予見するのは困難」として減額しました。
一審判決の後、介護関係者などからは、「認知症患者の閉じ込めになる」などの批判が続出。
さらに、二審の判決後、遺族側の代理人は、「高齢ながら、できる限り介護をしていた妻に責任があるとされたのは残念。不備があれば責任を問われることはあり得るのだろうが、家族が常に責任と隣り合わせになれば在宅介護は立ちゆかなくなってしまう」とのコメントを発表しました。
リーガルアイ
今回の判決、法律的に見ていくと、どのような判断だったのでしょうか?
報道からだけでは詳細は分かりませんが、「民法」第709条の「不法行為に基づく損害賠償請求」、あるいは「民法」第714条の「責任無能力者の監督義務者の責任」を適用したものと考えられます。
条文を見ながら解説していきます。
「民法」第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
「民法」第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
1.前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りで ない。
第714条では、自分の行為の是非善悪の判断ができない者(責任無能力者)を監督する法定の義務ある者の不法行為責任を定めています。
たとえば、今回の事故で亡くなった認知症老人に成年後見人がついていれば「法定の義務ある者」となりますが、そうでなければ、本件は第714条の問題ではなく、第709条の問題となります。
第709条では、認知症老人の監督は法律上当然に認められる監督義務ではなく、条理などにより認められる義務となります。
夫を放置しておくと、一人で外出徘徊し、今回のような事故を起こすことが予見できたのに、同居して生活の世話をしていた妻が、これを回避しなかった。
そのために、「過失」の責任を問われた、という判断になったと考えられます。
ちなみに、同様の事故では家族らが支払いに応じるなどして和解する事例が多く、訴訟に至るのは珍しいケースだということです。
ところで、よくいわれる都市伝説に、列車に飛び込み自殺をすると、数億円もの損害賠償請求が届くというものがあります。
国土交通省の発表によると、平成24年度に発生した鉄道事故は811件あり、そのうち死亡者数は295人。
この中には認知症の人以外に、自殺者も含まれているでしょう。
実際、事故が起きると、鉄道各社は通常、走らせるべき電車を走らせることができなくなったために被った損害、たとえば乗車券や定期券の払い戻し代、振替輸送の費用、乗客対応の人件費などを合わせた損害額を本人や家族側に請求します。
場合によっては、列車の運休による機会損失費、設備の修理費などが含まれることもあります。
今回の事故では、当初の請求額が720万円だったことから、これが地方都市での一応の目安にはなるでしょう。
しかし、大都市圏のように乗客数が多い場合は、賠償額が数千万円に跳ね上がることが予想されます。