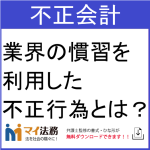狭い道路に面した土地の上に建物を建築する際、敷地の一部を道路に取られてしまいました。
こうした事態を回避することはできないのでしょうか?
【この記事の著者】 冨田会計・不動産鑑定株式会社 冨田建公認会計士・不動産鑑定士事務所
不動産鑑定士・公認会計士・税理士 冨田 建
ご質問の土地は「2項道路」といわれるもので、建築基準法では幅員4m未満の道路に面した敷地に建物等を建設する場合、道路との境界線を後退させて、幅員を4m分確保できるよう敷地の一部を提供しなければいけないことになっています。よって、回避はできないと考えたほうがよいでしょう。
以下に解説していきます。
建築基準法上の接道要件とは
都市計画区域内において建物の建築等を行う時は、建築基準法上において認められた道路に、間口から建物までが直径2mの大玉が転がるようなイメージで接していないと建築制限がかかってしまいます。
つまり、建築基準法上の道路に上記の条件で接している事が、建物の建築の前提となるのです。
この制度には、消防車や救急車などの緊急車両の走行に対する配慮や、日照・通風等の住環境への配慮を通じた良質な都市の形成という趣旨があると思われます。
なお、余程の過疎地でない限り、大抵の土地は都市計画区域に入っていると考えたほうがいいでしょう。
このため、通常の都市部において建物の建築等を行う際は、周囲に広場・公園等の十分なスペースがある場合に認められる「建築基準法43条但書」という例外規定が適用される場合を除き、建築基準法上の道路に接している事が原則となります。
セットバックとは
建築基準法上の道路とは、幅員が4m以上である事が原則で、この要件を満たさない土地には建物の建築は認められません。
ただ、昔からの経緯で、敷地の接している道路の幅員が4m未満という土地は全国のいたる所に存在するのも事実です。
これらの土地について、「幅員4m以上の道路に接していない」事を理由に建物の建築等を一律に認めないと、建物の建替等に制約がかかってしまい所有者は著しい不利益を被ってしまいます。
一方で、幅員4m未満の道路の継続を前提とした建物の建築等を認めると、いつまでたっても緊急車両や住環境に配慮した都市の形成ができないという事態が想定されます。
そのため、敷地の接している道路の幅員が4m未満であっても、敷地前面部分を後退させて幅員を4m分確保できるよう敷地の一部を提供する事を条件として、このような道路についても建物の建築等を認めることとされました。
このように、敷地の一部を道路として提供することをセットアップといいます。
ちなみに、このような道路は「建築基準法42条2項」に規定される道路のため、一般的に「2項道路」と通称されることが多いです。
不動産を購入する際の注意点
セットバックする場合、幅員4mはセットバック前の道路の中心線から両サイドに2mずつの提供が一般的です。しかし、反対側が線路や川等でセットバックできない場合や、既に反対側がセットバック済であった場合は、こちら側が「4m-現況幅員」分を全てセットバックすることになる点を注意してください。
もし、このような狭い道路に接している土地の購入や建物建築を検討している場合、