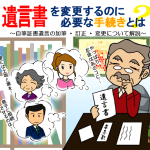動画解説はこちら
コンビニで買い物をして、帰ろうとしたところ逮捕されてしまったという事件が起きました。
日常生活の中に潜む犯罪の罠…
何気なくやってしまった、あなたのその行為、犯罪になるかもしれません!
事件はこうして起きた
「お釣り多くもらい詐欺容疑 消防士を逮捕、奈良」(2015年1月7日 共同通信)
奈良県橿原市のコンビニで、店員が誤って渡したお釣り約4万6千円を申告せずに受け取ったとして、消防士の男(43)が詐欺の疑いで逮捕されました。
事件が起きたのは、2014年12月。
報道によると、容疑者の男が携帯電話料金やたばこ代など約1万3千円の会計に1万5千円を支払った際、6万円を預かったと思い込んだアルバイト店員(16)が、お釣りとして約4万6千円を渡したところ、これを受け取ったということです。
店員は、「忙しくてパニックになり勘違いした」と話し、容疑者の男は、「酒に酔って覚えていない」と容疑を否認しているとのことです。
リーガルアイ
「お釣りを多くもらっただけで逮捕されるとは、おおげさじゃないか?」
「ミスをした店員にも罪があるんじゃないか?」
そんな声も聞こえてきそうですが、今回の容疑者の行為は犯罪になってしまいます。
では、条文から見ていきます。
「刑法」
第246条(詐欺)
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「詐欺罪」が認められ成立するには、その構成要件を満たしているかがポイントになります。
以下にまとめます。
「詐欺罪の構成要件」
〇相手方を錯誤に陥らせ、財物や財産上の利益を処分させるような行為をすること((欺罔行為や詐欺行為)
〇相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
〇錯誤に陥った相手方が財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
〇財物の占有または財産上の利益が行為者や第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
〇これら4つの間に因果関係が認められ、行為者に故意または不法領得の意思が認められること
ややこしくて難しいですが、簡単に言うと、詐欺罪が成立するには、「だまそうとする意思」が必要です。
つまり、「故意」が必要ということです。
たとえば、お釣りが多いことに気づかずに、家に帰ってから気づいた、というような場合には、「だまそうという意思」がないので、詐欺罪は成立しません。
では、今回のケースでは、なぜ詐欺罪に問われたのでしょうか。