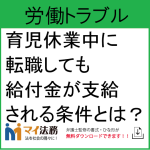個人事業主に対する税務調査は、所得税だけでなく消費税にも実施されますが、インボイス制度の導入により、消費税に対する税務調査が従来よりも厳しくなると考えられています。
本記事では、消費税の税務調査が強化される理由と、個人事業主が取るべき対策について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
インボイス制度が税務調査に与える影響
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を適正に行うための新たな制度で、令和5年(2023年)10月から開始されました。
仕入税額控除を適用するには、法定事項が記載された請求書等を適切に保存する必要があります。
しかし、適格請求書(インボイス)を発行できるのは適格請求書発行事業者に限られるため、登録をしていない事業者が交付した請求書等を保存していても、仕入税額控除を適用することはできません。
また、適格請求書発行事業者となるには登録申請が必要であり、登録申請を行うと免税事業者であっても消費税の課税事業者となります。
そのため、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録申請を行った場合、登録後は課税事業者として消費税の確定申告書を提出しなければなりません。
国税当局のインボイス制度に関する税務調査の方針
国税庁長官は令和5年9月、インボイス制度の税務調査について、大口・悪質な事例に限定して実施する意向を示しました。
軽微な記載ミスについては柔軟に対応する方針を示したことから、インボイス制度の取扱いのみを確認する目的で税務調査が実施される可能性は低いと考えられます。
一方で、仕入税額控除の適用要件はインボイス制度の導入によって変更されたため、仕入税額控除の適否を含めた消費税の申告内容を確認する目的で、税務調査が行われることは想定されます。
また、インボイス制度の導入により、新たに消費税の課税事業者となった個人事業主を中心に、無申告の取締りが強化される点にも注意が必要です。
個人事業主に対する消費税の税務調査のポイント
インボイス制度のみを対象とした税務調査が実施されるケースは限定的ですが、制度の導入により、適格請求書の発行や帳簿管理の適正性が厳しく問われるため、慎重な対応が求められます。
消費税の無申告は発見されやすくなった
消費税の課税事業者が申告をしていない場合、無申告者を対象とした税務調査が実施されます。
適格請求書発行事業者は、課税売上高に関わらず消費税の確定申告を行う必要があるため、これまで免税事業者として活動していた個人事業主が申告をしていなければ、税務調査で指摘される可能性があります。
インボイス制度導入後は、消費税の無申告が一定数発生すると見込まれます。
しかし、税務署は適格請求書発行事業者を管理しているため、登録情報をもとに消費税の申告の有無を把握できます。
そのため、消費税の無申告は従来よりも発見されやすくなっているので、十分な注意が必要です。
請求書等の管理と整合性がチェックされる
インボイス制度では、原則として取引ごとに適格請求書を発行しなければならないため、取引先に対して必要事項が記載された請求書が適切に発行されているかがチェックされます。
そして発行した適格請求書の写しは一定期間保存する必要があります。
また、保存している請求書等に必要な記載項目が欠けている場合には、仕入税額控除の適用対象外となる恐れがあるため、請求書等の交付を受けた時点で要件を満たしているかの確認が求められます。