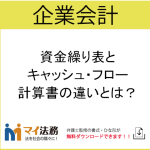法人の売却や再編を検討する場合には、事業譲渡または株式譲渡の選択肢があります。
それぞれの手法にはメリットとデメリットがあり、節税効果にも差が生じます。
本記事では、法人の事業譲渡と株式譲渡の税務上の違いと節税面での判断基準について体系的に解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
事業譲渡と株式譲渡の基本的な違い
法人の売却や再編において、事業譲渡と株式譲渡では法的構造や実務対応の面で大きく異なります。
法的構造と譲渡対象の違い
<事業譲渡の場合>
事業譲渡は、法人が保有する資産・負債・契約などの一部または全部を第三者に移転する行為です。
法人の事業単位の譲渡となるため、事業を手放した企業はその後も法人格として存続します。
<株式譲渡の場合>
株式譲渡は、法人の所有者である株主が保有する株式を買手に譲渡する行為です。
株主が変更になるだけで、法人そのものの構造は変わりません。
ただし、経営者が変わることにより、譲渡後に会社の形態が大きく変わる可能性があります。
契約当事者と手続きの相違点
<事業譲渡の場合>
事業譲渡における契約の当事者は、法人同士(売手法人と買手法人)です。
譲渡対象ごとに契約の移転手続きが必要であり、契約書の作成や資産評価、債務承継の明確化など、個別対応が求められます。
そのため、手続きが複雑になりやすく、実務負担が大きくなる傾向にあります。
<株式譲渡の場合>
株式譲渡における契約の当事者は、株主(個人または法人)と買手です。
非上場株式であれば、株式売買契約を締結し、株主名簿を書き換えることで手続きが完了します。
手続きは事業譲渡に比べてシンプルで、関係者も限定されます。
従業員・取引先への影響
<事業譲渡の場合>
事業譲渡では、従業員の雇用契約や取引先との契約が譲渡対象に含まれるため、譲渡後の関係維持に配慮が必要です。
労働契約の承継には、原則として従業員本人の同意が必要となります。
また、取引先との契約も、買手法人との間で再締結や通知を求められることがあります。
<株式譲渡の場合>
株式譲渡を行ったとしても、法人の契約主体は変わらないため、従業員の雇用契約や取引先との契約は原則としてそのまま引き継がれます。
ただし、経営者の変更により方針が変わる可能性があるため、信頼関係の維持に向けた丁寧な説明が求められます。
税務における事業譲渡と株式譲渡の取扱い
税務上の取り扱いは、譲渡手法を選択する上で最も重要な比較ポイントです。
法人税・所得税の課税関係
<事業譲渡の場合>
売手法人には、譲渡益に対して法人税が課されます。
譲渡資産の帳簿価額と譲渡価額との差額が課税対象となるため、含み益の大きい資産を譲渡する場合には、税負担が重くなる傾向があります。
<株式譲渡の場合>
売手株主には、株式の売却価額から株式の取得費を差し引いた額に対して、所得税(個人の場合)または法人税(法人の場合)が課されます。
法人の資産評価は行われないため、含み益は法人内に留まり、課税対象とはなりません。
消費税・登録免許税の取扱い
<事業譲渡の場合>
譲渡対象となる資産のうち、建物、機械、在庫などの課税資産には消費税が課されます。
また、不動産や知的財産の名義変更がある場合には、登録免許税が発生します。
<株式譲渡の場合>
株式(有価証券)の譲渡は消費税の非課税取引に該当するため、消費税はかかりません。
登録免許税も原則として不要であるため、税務コストの面では、株式譲渡の方が有利となる場合があります。
繰越欠損金の引継ぎ可否
<事業譲渡の場合>
売手法人が保有する資産のみが移転するため、繰越欠損金は買手法人に引き継がれません。
また、譲渡法人が清算された場合には、欠損金は消滅します。
<株式譲渡の場合>
法人格はそのまま存続するため、繰越欠損金は原則として引き継がれます。
ただし、株主の異動により一定の要件(実質的な支配権の変更など)に該当する場合には、その利用が制限されることがあります。
事業譲渡・株式譲渡の節税面での判断基準
譲渡手法の選択は、税負担の最小化を図る上で極めて重要です。
譲渡益の発生時期や課税対象の違いを踏まえ、売手・買手双方の視点から総合的に判断する必要があります。