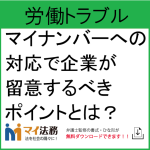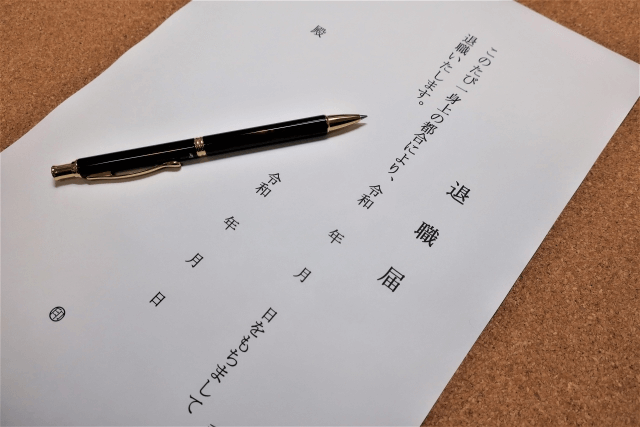


民法改正により、社員が退職する場合の取扱いについても注意しなければならない点があると聞きました。
具体的にはどのようなことに気を付けなければならなくなったのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
2020年(令和2年)4月1日から施行された改正民法の中には、ご質問のとおり、労働者が退職する場合の対応について留意しなければならない条文があります。
ただし、ここでいう「労働者」とは「雇用契約において期間の定めのない」者をいい、「退職する場合」とは「労働者側からの解約申入れ」により退職する場合をいいます。
そこで、改正された第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)を以下記載いたします。
- 第627条
- 1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
- 2.期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
- 3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
改正後は、第2項の「使用者からの」という文言が追加されました。
改正前はこの文言はなかったことから、使用者だけでなく労働者にも適用されていたところ、2020年4月1日以降は使用者にのみ適用されることとなりました。
この改正により、労働者が使用者に解約の申入れをする場合、第2項は考えなくてよいということになります。
また、第3項の「前項の解約の申入れ」は第2項の「使用者からの解約の申入れ」を指しますので、労働者は第3項についても適用されないということになります。
そうすると労働者については第1項のみが適用され、2週間前に申出すれば良いことになります。
したがって、