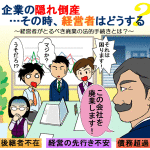開業後、3年を経過して順調に収入が増えており、周囲から“医療法人成り”を勧められました。
医療法人を設立したほうがよいのでしょうか? その場合のメリットを教えてください。
【この記事の著者】税理士法人晴海パートナーズ 税理士 小島 浩二郎
http://harumi-partners.jp/
医療法人の設立を検討する場合、収入だけで判断せず医療法人成りのメリット・デメリットを考えてご検討することが大切です。
メリットとしては、以下のようなことがあげられます。
目次
実効税率が小さくなります。
現在の法人の実効税率は約40%で、個人の最高税率50%(平成27年分からは4,000万円超は55%)と比べると税引後の手取り額が増加します。
今後、法人税率が下がり所得税率が上がるという傾向は続くと思われます。
例えば、開業のための借入金が残っている場合、うまく医療法人に引き継ぐことができれば返済が楽になります。
家計と医療法人経営が分離されるため、医院経営の適正な把握が可能となり、事業も拡大しやすくなります。
医療法人設立後は、先生の給与は役員報酬として医療法人の通帳から払われるため、家計と医療法人の経営が分離され、個人時代と違い「いくら儲かっているのか」が把握しやすくなります。そのため、事業計画などが立てやすくなります。
また、サテライトクリニックや老健施設のような複数施設の開設やその他介護事業を運営することができるようになり、幅広い事業展開も可能となります。
将来的に、理事や理事長に退職金を支払い、医療法人の経費として計上することができます。
医療法人で貯蓄を行い、将来的に理事や理事長に退職金を経費として支払えば、受取退職金は退職所得控除を控除した金額の半分が課税の対象になる分離課税のため節税となります。
ちなみに、個人医院では院長が死亡されても退職金を経費にできないため支給できません。
また、医療法人において弔慰金規定を作成し院長死亡時に支給すると、最終月額報酬の6ヶ月分(業務上の死亡は36か月分)を法人経費として支給することができ、受取った遺族は、この範囲内の金額なら相続税が全額非課税で受取ることができます。
理事長家族への所得分散が容易になり、その分、節税ができます。
所得を分散することで、累進税率である個人の所得税・住民税の税率が下がり、結果的に理事長家族全体の税引後の手取が増加します。
個人時代には支給基準が厳しかった専従者給与ですが、医療法人の場合は、理事長先生をはじめ家族理事にも役員報酬として報酬を支給することが税務的に容易になります。
個人医院時代の専従者給与額より高い役員報酬額を従来の専従者に支給することができるため、いわゆる所得の分散が個人時代より効果的にできるのです。
もちろん、家族が理事として医療法人の運営に関わっていることが前提での役員報酬です。
また、理事長報酬に対しても「給与所得控除」を受けることができるので、ここでも課税所得を少なくすることができます。
一定の生命保険料を損金に計上できます。
いざという時のために個人で契約している生命保険の保険料は、個人事業形態だと最高で12万円までしか所得控除が受けられません。(生命保険料控除)
しかし医療法人の場合、一定の生命保険契約に関しては法人の経費として契約を結ぶことができます。
(ただし、保険の契約によって経費となる部分は変わってきます)
そのため、個人で支払っていた生命保険を解約することも可能となり、家計が楽になります。