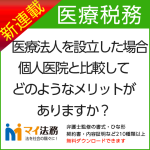税務調査では、棚卸資産の有無が争点になりやすいという話を聞きましたが、なぜでしょうか? また、どのような場合に問題になるのでしょうか?
【この記事の監修者】税理士法人桜頼パートナーズ会計 小髙事務所 小髙 正之
実際の税務調査では、棚卸資産の有無は争点になりやすい項目のひとつといえます。
それは、「棚卸資産の増加=所得金額の増加=税金の増加」を意味するからです。
税法上、棚卸資産とは、「商品」「製品」「仕掛品」「原材料」など将来的に換金されるものが主になります。
当然、それらの在庫を多く抱える業種は狙われやすいわけです。
ところで、上記の棚卸資産の概念を理解しただけでは、じつはまだ不十分です。
次に問題となるのが、在庫の保存場所です。
たとえば、店舗・倉庫・工場などが在庫の保存場所としてあげられるでしょう。
しかし、「棚卸資産とは、これらの不動産の中にあるもの」という一般的な考え方では、実務では通用しません。
なぜなら、税法上の棚卸資産の概念はもっと広いからです。
今回は、中古の洋服を販売するアパレル企業の税務調査の事例を解説します。
この会社は、次のような取引の流れになっていました。
①海外から洋服とその材料を輸入
②仕入れた材料を洋服に加工
③国内で洋服の卸売り、小売りを行なう
会社としては、店舗での販売にウエイトを置いていたことから、顧客のニーズを先読みして仕入れるために在庫量は月商の2ヵ月分、金額にして5000万円前後になっていました。
社長の持論は、「洋服がひとつ売れたら、ふたつ仕入れなければならない」というものでした。
しかし、前述した通り、棚卸資産が増えれば納税額は増加しますが、洋服で税金を納めることはできません。
社長の持論の通りに事業展開すれば、納税資金を圧迫させることになります。
そこで、脱税スキームとして、決算日時点の棚卸資産を一部除外するという“禁じ手”に出たのです。
具体的には、加工する工場と店舗の洋服、さらにはその材料の数を明細書に記載させて、数十枚のうち何枚かを社長が破棄するという仕組みです。これだけ在庫の量があれば、少し誤魔化しても税務署にバレないという思惑が働いたのでしょう。
こうした決算の繰り返しをしているうちに、税務調査が行なわれました。
予想通り、調査官は在庫の計上漏れに目を付け、次のような会話がやりとりされました。