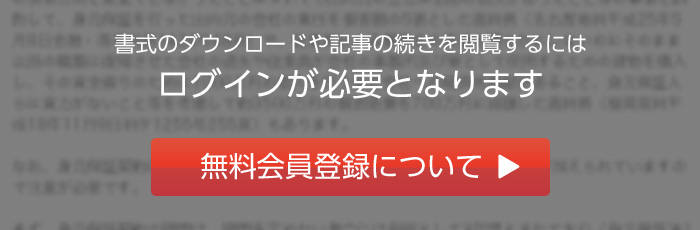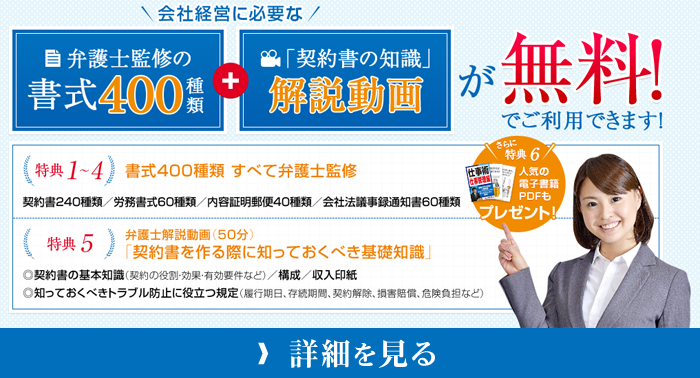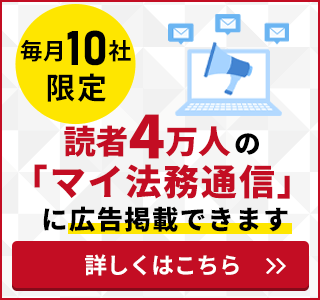法人が会社役員と不動産の賃貸借を行う場合、賃料の設定金額を間違えると、税務上の問題が発生する恐れがあります。
本記事では、法人が役員と賃貸借を行った際の税務上の扱いと、家賃等の金額を決めるときの注意点について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
法人が役員から不動産を借りた場合の課税関係
法人が役員から不動産を借りるときの賃料は、原則第三者と賃貸借する際に支払う賃料が基準です。
たとえば事業用建物を借りる場合、相場の金額を家賃として支払うのであれば、家賃をそのまま経費として計上できます。
支払家賃が相場に比べて極端に低いと受贈益が発生することが想定されますが、支払家賃と受贈益は相殺することになりますので、税務上の問題は起こりません。
反対に、支払家賃が通常よりも極端に高い場合には、高い部分が役員への報酬として取り扱われる可能性があるので注意が必要です。
役員が法人への貸し付けた際の家賃収入は、不動産所得として申告するのが原則です。
ただし、通常の家賃を超える部分の金額は不動産所得ではなく、給与所得の対象となります。
法人が役員へ社宅を貸し付けた場合の課税関係
法人が不動産を借り、役員に対して社宅を貸与するとき、法人は第三者へ支払う家賃を経費として計上できます。
しかし法人が支払家賃を経費計上するためには、家賃の一部を役員が自己負担しなければならず、支払家賃の全額を会社側の経費とすることはできません。
役員が負担すべき家賃の割合は、1か月当たりの賃貸料相当額が基準です。
役員が法人に対して賃貸料相当額を支払っていれば、法人側は社宅関連の費用を経費にできますし、役員が給与として課税されることもありません。
一方、社宅を役員へ無償で貸与するなど下記のケースに該当するときは、役員の給与所得として課税されますのでご注意ください。
<給与として課税される範囲>
(給与所得の対象となるケース)
役員へ無償貸与する場合
(給与として課税される額)
賃貸料相当額
(給与所得の対象となるケース)
役員から受け取る家賃が賃貸料相当額よりも低い場合
(給与として課税される額)
賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額
(給与所得の対象となるケース)
現金支給の住宅手当て、入居者が直接契約している場合における家賃負担
(給与として課税される額)
全額
(社宅の貸与とは認められないため)
社宅を役員に貸与する際の「賃貸料相当額」の判断基準
社宅の費用を経費計上する際の基準となる賃貸料相当額は、社宅が「小規模な住宅」と「それ以外の住宅」のどちらに該当するかによって算出方法が異なります。
また豪華社宅とみなされる社宅については、別途賃貸料相当額の基準が定められています。
「小規模な住宅」の賃貸料相当額の計算方法
「小規模な住宅」とは、次に該当する住宅をいいます。
床面積が132㎡以下の住宅
●法定耐用年数が30年を超える建物の場合
床面積が99㎡以下
※ 区分所有の建物の面積は、専用部分の床面積に按分した共用部分の床面積を加えて判定
役員へ貸し付ける社宅が小規模な住宅に該当する場合、次の3つの合計額を賃貸料相当額とします。
・その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
・12円×その建物の総床面積(㎡)÷3.3㎡
・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
「それ以外の住宅」の賃貸料相当額の計算方法
「それ以外の住宅」とは、「小規模な住宅」に該当しない社宅をいいます。
役員へ貸し付ける社宅がそれ以外の住宅に該当する場合、自社所有の社宅と、他から借り受けた住宅等で賃貸料相当額の算出方法は異なります。
自社所有の社宅の場合(右の合計額の12分の1)
・その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%(※)
※建物の法定耐用年数が30年を超える場合は10%
・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主へ支払う家賃の50%と、自社所有の社宅の場合における算式で計算した賃貸料相当額とのいずれか多い金額