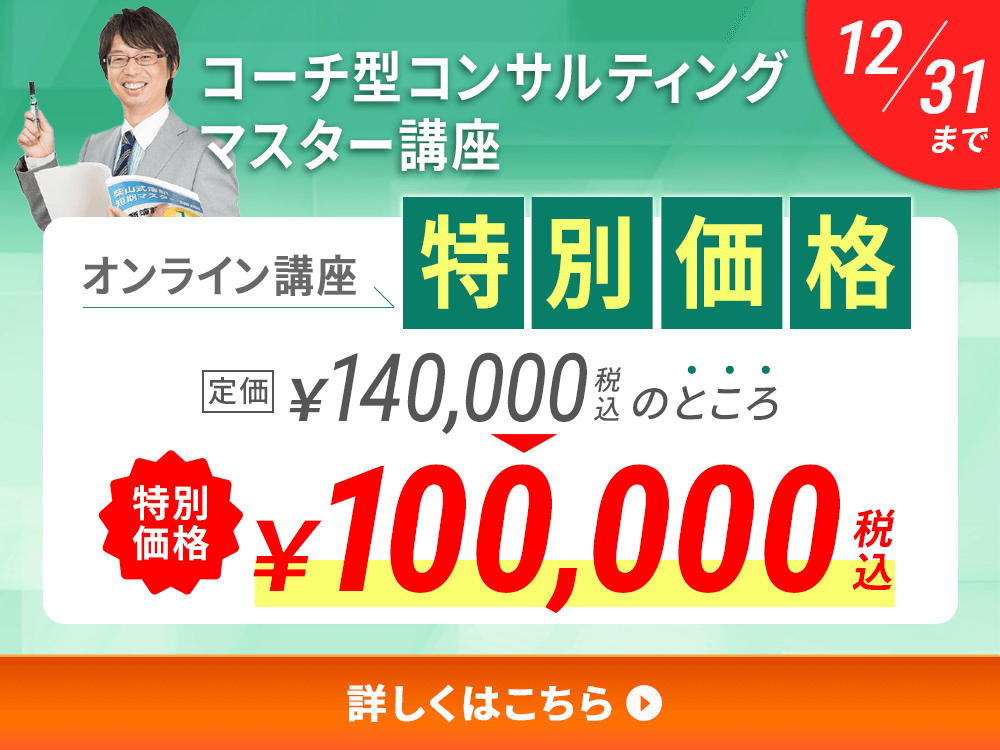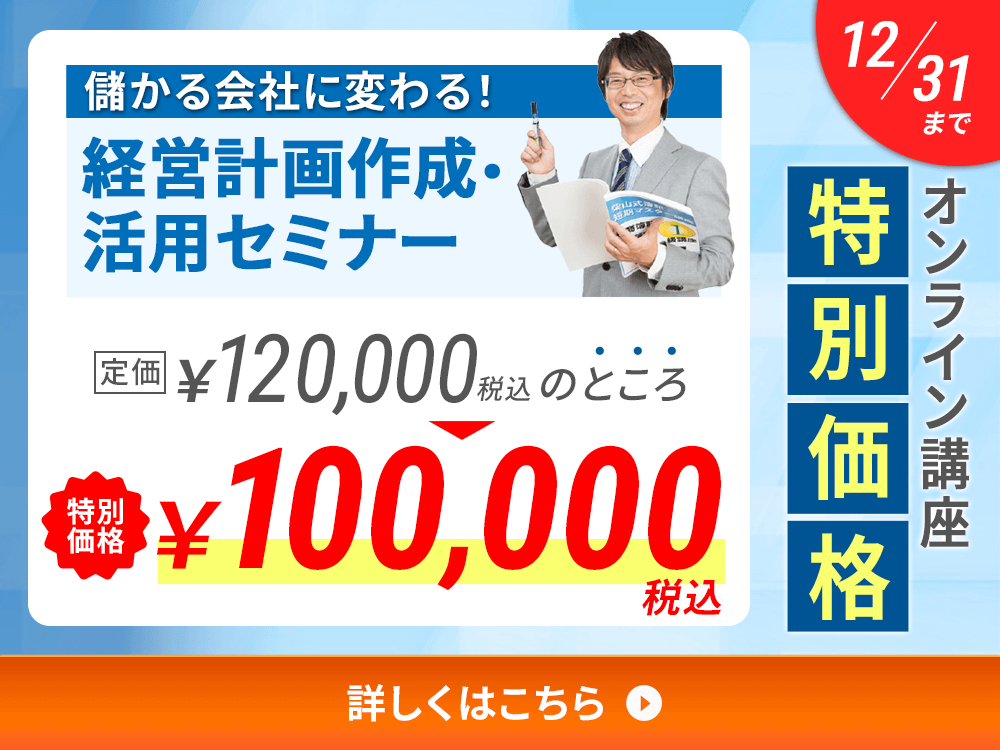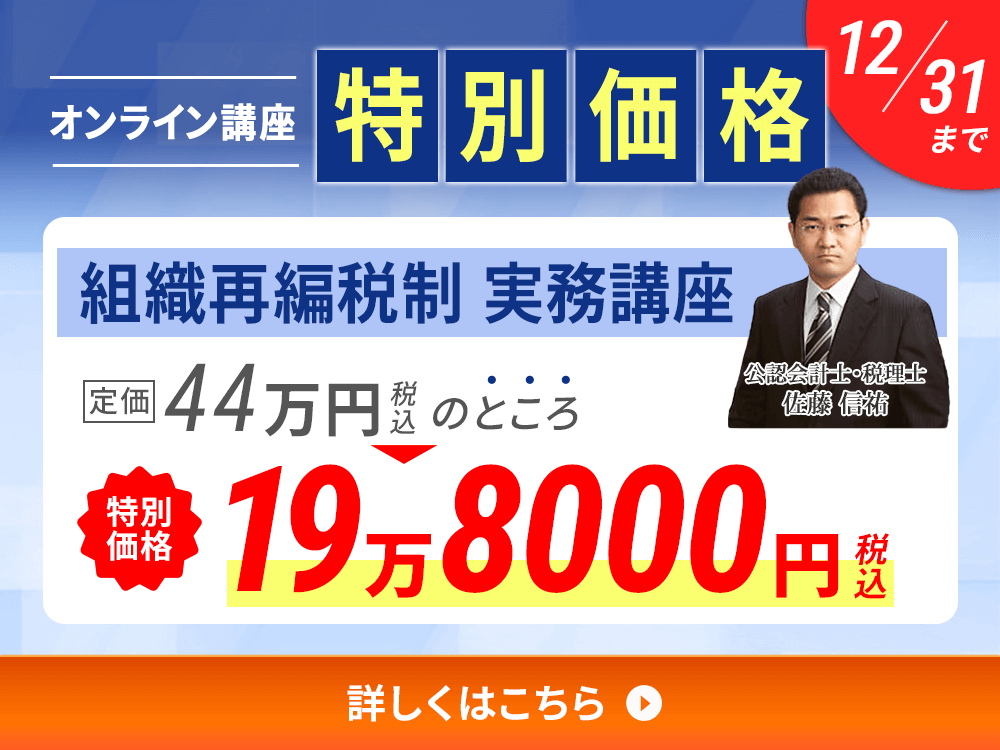電通の従業員の過労死自殺問題に関する報道をきっかけに、「勤務間インターバル」という言葉を知りました。
国も企業の積極的な導入へ向け助成金制度を導入したとも聞きましたが、これはどのような制度なのでしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
交替制勤務(あるいはシフト勤務)は、IT企業(主に客先常駐型)や、医療・介護事業、飲食業など幅広い業界で採用されています。
交替制も、2交替または3交替で実施するのが一般的ではないでしょうか。
ただ、交替制勤務の場合、労働基準法における勤務時間の上限である「1日8時間、1週40時間」に収めることが難しい場合も多く、1か月単位の変形労働時間制、または1年単位の変形労働時間制を採用している例が数多く見られます。
IT企業であれば、システムエンジニアである社員を対象とした専門業務型裁量労働制も積極的に導入されています。
では、夜勤がある業務において、夜勤明けの日を休みにしなければならないという根拠はあるのでしょうか?
労働基準法で定められている労働時間や労働日数に関する「上限」には次のようなものがあります。
・1日の労働時間の上限=8時間
・1週の労働時間の上限=40時間労働(44時間労働の例外事業場あり)
・1か月の時間外労働の上限=45時間(1年単位の変形労働時間制は42時間)
⇒新技術、新商品等の研究開発の業務や自動車の運転の業務は適用除外
・1週に1日または4週に4日の休日を確保すること。
しかし、夜勤明けの休日付与に関して義務化されている法律は現時点でありません(似たようなものにトラック運転者の1日の拘束時間と休息時間について定められたものがありますが)。
従って、社員の請求どおりに休日を与える必要はありません。
それでも過重労働による健康障害防止のため、自主的に対策を講じている企業もあります。
例えば、