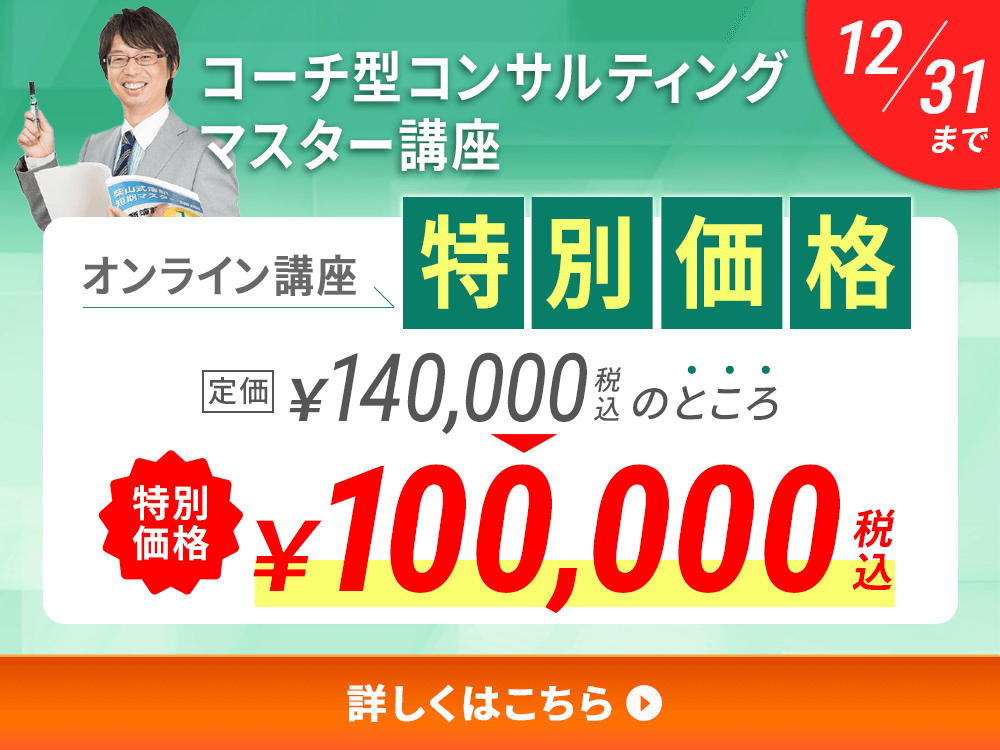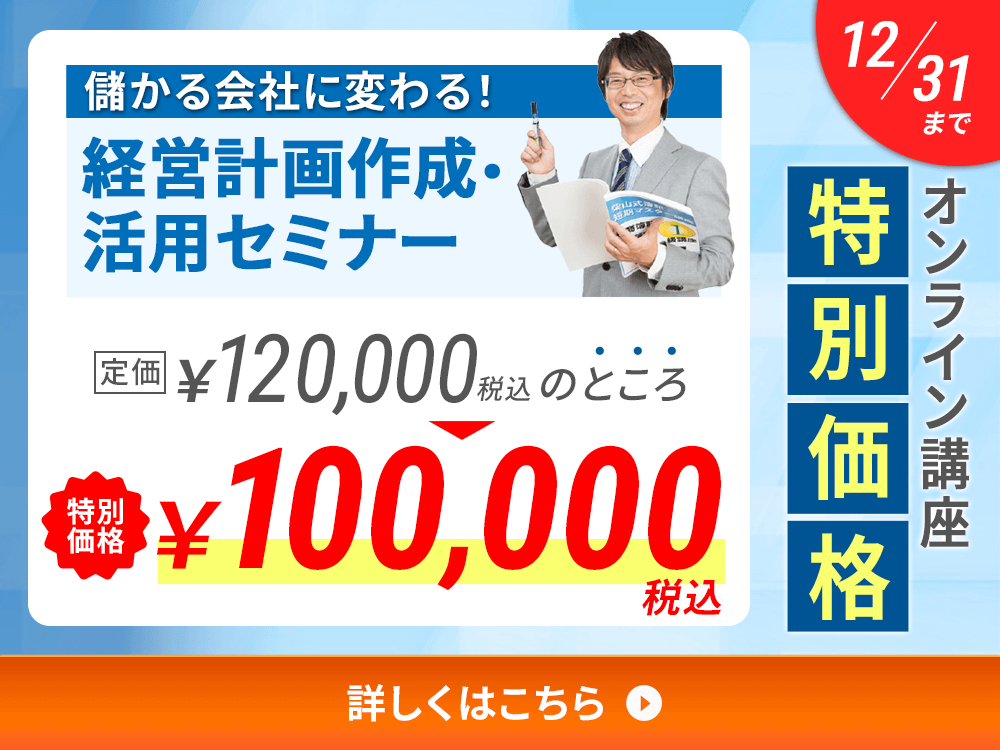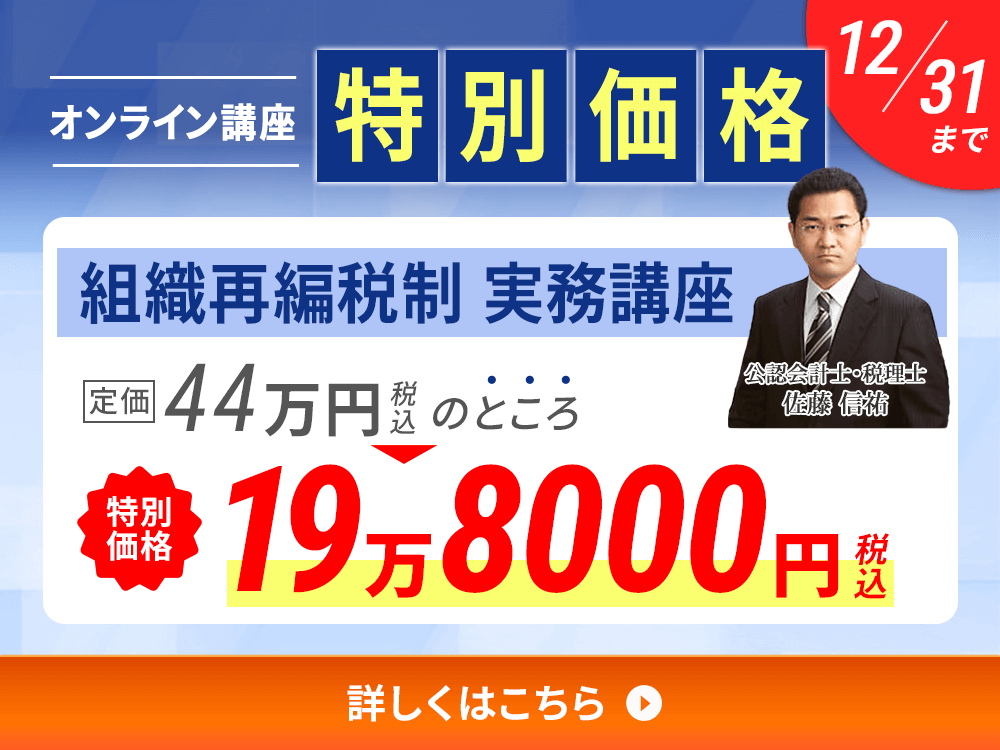国はデフレ完全脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税に定額減税を導入することを決定しました。
給与所得者は、基本的に源泉徴収税額から定額減税額を控除することになるため、事業者は源泉徴収や年末調整において、定額減税に関する事務処理を行わなければいけません。
本記事では、給与支払者が行う定額減税の事務処理と注意点について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
給与支払者が行う定額減税の手続き
従業員を雇用している事業者は、給与等を支払う際に源泉徴収税額から定額減税額を控除しなければなりません。
給与支払者が行う事務処理は次の2種類です。
月次減税事務
令和6年6月1日以後に支払う給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額から、その時点の定額減税額を控除する事務
年調減税事務
年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務
月次減税事務の手順
月次減税事務では、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等について、源泉徴収をされるべき所得税の額(控除前源泉徴収税額)から特別控除額を控除します。
令和6年6月1日現在において給与支払者の下で勤務している人のうち、給与等の源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者を選び出します。
甲欄が適用される居住者とは、給与支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者(基準日在職者)をいい、次に該当する者は基準日在職者には該当しません。
● 令和6年6月1日以後に支払う給与等の源泉徴収において、源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される人
(扶養控除等申告書を提出していない人)
● 令和6年6月2日以後に勤務することになった人
● 令和6年5月31日以前に退職した人
● 令和6年5月31日以前に出国し、非居住者となった人
月次減税事務では基準日在職者の各人別の月次減税額と、各月の控除額等を管理することになります。
選出した者は原則月次減税額の控除対象者となりますが、他の給与支払者に扶養控除等申告書を提出したときは対象外です。
令和6年6月1日以後に行う給与または賞与のうち、支給日が早いものについて源泉徴収されるべき控除前税額から控除します。
控除しきれなかった特別控除額は、以後令和6年中に支払われる給与等に係る控除前源泉徴収税額から順次控除することになりますが、同年において最後に支払われるもの(年末調整をする場合)は除きます。
令和6年6月1日以後に交付する給与明細等には、当該給与明細等に係る控除前源泉徴収税額から控除した定額減税の控除済額を記載します。
ただし、年末調整を行って支払う給与等にかかる給与明細等においては、源泉徴収票において減税額を把握することが可能であるため、定額減税の控除済額の記載は不要です。
定額減税額(所得税)〇〇円、 定額減税〇〇円 等