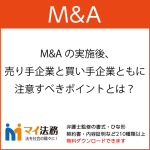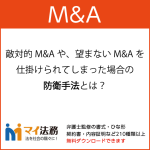動画解説はこちら
会社や職場での「言葉の暴力」=パワハラ問題が急増しているようです。
パワハラ問題が起きてしまうと、被害者の肉体的・精神的苦痛はもちろん、会社にとっても大きな損害となってしまいます。
では、何をするとパワハラになるのでしょうか?
パワハラと教育的指導との違いは何なのでしょうか?
【モラハラ・パワハラの関連記事】
言葉の暴力(モラハラ)は犯罪になる?
パワハラ自殺で会社に高額損害賠償金の支払い命令
事件はこうして起きた
「“威圧され適応障害”…看護師長のパワハラ認定」(2015年2月26日 読売新聞)
元上司によるパワーハラスメントで適応障害になったとして、北九州市の病院に看護師として勤めていた女性(30歳代)が病院の運営元や元上司を相手取り、約315万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が福岡地裁小倉支部でありました。
原告の女性は病院に勤務していた2013年4~5月頃、子供がインフルエンザにかかったり、高熱を出したりしたため、上司だった看護師長に有給休暇を利用した早退を申請。
ところが、元上司は「もう休めないでしょ」、「子供のことで職場に迷惑をかけないと話したんじゃないの」などと発言。
女性はミスを叱責されたこともあり、食欲不振や不眠から、同年11月に適応障害と診断されて休職し、その後、2014年3月に退職したようです。
裁判官は、看護師長の言動について、「部下という弱い立場にある原告を過度に威圧し、違法」と認定し、被告に約120万円を支払うよう命じたということです。
リーガルアイ
パワハラにつては以前にも解説しています。
これらも参考にしながら、今回はもう一度パワハラについて復習していきましょう。
【パワハラとは?】
パワハラについて、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」(厚生労働省)では、以下のように定義しています。
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」
「上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。」
この定義を踏まえたうえで、パワハラが成立するかどうかについて次の3つの要件が認められるかを検討していきます。
・それが同じ職場で働く者に対して行われたか
・職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に行われたものであるか
・業務の適正な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与え、また職場環境を悪化させるものであるか
【パワハラにあたる6つの行為とは?】
具体的には、以下の6つがパワハラとなる行為とされています。
1.身体的な攻撃(暴行・傷害)
2.精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、
仕事の妨害)
5.過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低
い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
【パワハラ・モラハラの関連記事はこちら】
・言葉の暴力「モラハラ」は犯罪になる?
・パワハラ自殺で会社に高額賠償金支払い命令!?
【パワハラに対する会社の責任と損害とは?】
会社には社員に対して以下のような義務や責任があります。
「職場環境配慮義務」
会社は、従業員との間で交わした雇用契約に付随して、職場環境を整える義務=職場環境配慮義務を負います。
社員等にパワハラやセクハラなどの被害が発生した場合、職場環境配慮義務違反(債務不履行責任<民法第415条>)として、会社はその損害を賠償しなければいけません。
「使用者責任」
ある事業のために他人を使用する者は、被用者(社員)が第三者に対して加えた損害を賠償する責任があります(民法第715条)。
よって、セクハラと同様にパワハラが行われた場合、今回の事案のように民事裁判では、被害者は損害賠償を求めて訴訟を起こすことができます。
社員(看護師長)が別の社員(看護師)に対して損害を与えたと認められれば、その責任を会社と使用者(社長)が負い、損害を賠償しなければいけない可能性があります。
【パワハラを防ぐための5つの措置とは?】
パワハラを防ぐための措置として、次の5つがあげられます。
1.会社のトップが、職場からパワハラをなくすべきという明確な姿勢を示す。
2.就業規則をはじめとした職場の服務規律において、パワハラやセクハラを行った者に対して厳格に対処するという方針や、具体的な懲戒処分を定めたガイドラインなどを作成する。
3.社内アンケートなどを行うことで、職場におけるパワハラの実態・現状を把握する。
4.社員を対象とした研修などを行うことで、パワハラ防止の知識や意識を浸透させる。
5.これらのことや、その他のパワハラ対策への取り組みを社内報やHPなどに掲載して社員に周知・啓発していく。
【パワハラと教育的指導の境界線とは?】
「平成25年度個別労働紛争解決制度施行状況」(厚生労働省)によると、総合労働相談のうち、民事上の個別労働紛争の相談内容では「いじめ・嫌がらせ」が59,197件で、「解雇」や「退職」を抑え2年連続で最多となっています。
いかにパワハラやセクハラの問題が増えているかが見てとれます。
ところで、パワハラとなる行為の中でも、前述のような業務への過大な要求や過少な要求などは、業種や企業文化などによっても差異があるため、業務上の適正な指導との線引きや判断が難しいものです。
たとえば、以下のような相談を受けることがあります。
「パワハラについては理解できたけれど、
なんでもかんでもパワハラにされて訴えられたら、たまらない」
「ミスをした社員をしかるのは当然でしょう。
仕事上の叱責までパワハラにされたら、どうしていいのか…」
確かに、職場での部下への対応に困っている経営者や上司の方も増えているようです。
では一体、どこまでの行為がパワハラとなるのでしょうか?
職場での教育的指導とパワハラの違いは、どこに境界線があるのでしょうか?
法的な基準としては、「平均的な心理的耐性を持った人」が肉体的・精神的に苦痛を感じるかどうかが判断基準とされていますが、以下のポイントにも注意をしてください。