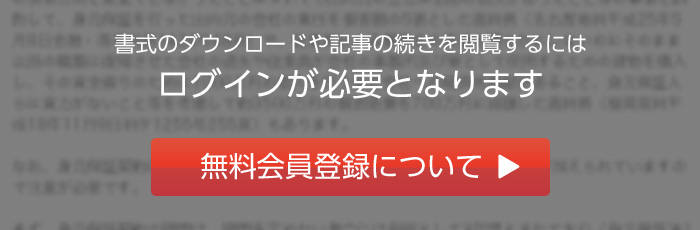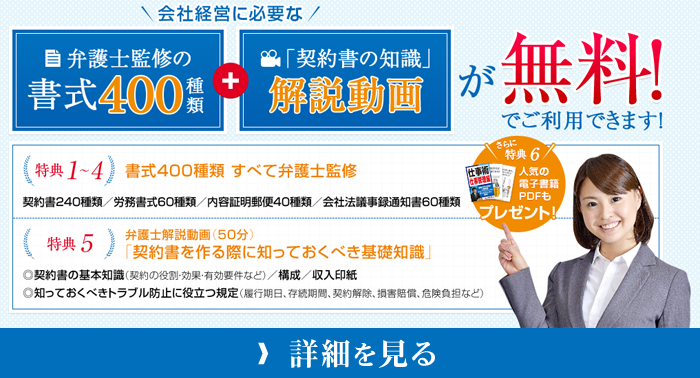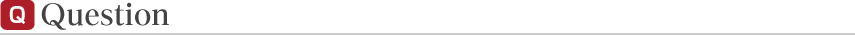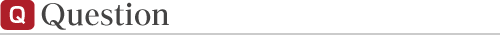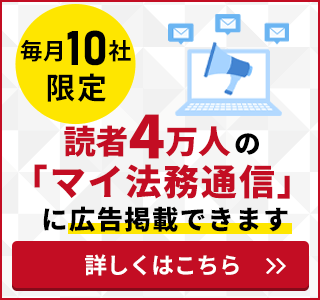就業規則に懲戒処分を規定したいと考えていますが、懲戒処分には、どのような種類があるでしょうか?
解説
企業の存在と事業の円滑な遂行のためには、企業の秩序を維持することが必要です。
そのための制度として、規律や秩序に違反した労働者に対して懲戒処分が行われることがあります。
もっとも、懲戒処分は、労働者に対して労働契約上行うことができる普通解雇や配置転換、昇給・昇格にあたっての低査定などの通常の不利益な処分とは別の特別の制裁罰であるため,懲戒処分を行うためには、就業規則や労働契約の根拠が必要とされています(判例①を参照)。
したがって、就業規則等で定めなかった場合には、懲戒処分を行うことができません。
ただし、就業規則等に記載さえすれば、いかなる懲戒処分も自由になしうるというものではなく、合理的な理由を欠き、社会通念上相当ではない懲戒は、懲戒権の濫用として無効となります(労働契約法15条)。
懲戒処分の種類は企業ごとに違いがあり、また企業内ルールなので、前述の社会通念上相当な範囲で原則として企業が自由なものを設けてよいのですが、一般的な懲戒処分としては以下のものが挙げられます。
①譴責・戒告
譴責・戒告とは労働者を将来に向けて戒めることをいいます。
譴責は、労働者に始末書を提出することを求めることで、戒告は、始末書の提出を求めない処分です。
両者とも、それ自体では実質的な不利益を課さない処分なのですが、昇給・昇格等の査定の際には不利に考慮される可能性があります。
②減給
減給とは、本来支払っている給料から一定額を差し引くことをいいます。
もっとも、給料は労働者の生活を支える大切な経済基盤なので、法律上、減額できる額に制限が設けられています。
まず、1回の違反行為に対して減額する場合には、1日の平均給料の額の半額を超える額を減額することはできません。
次に、複数の違反行為に対して減額する場合には、一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えることはできません(労働基準法91条)。
③出勤停止
労働者の就労を一定期間禁止する処分で、出勤停止期間中の給料は支払われず、勤続年数にも算入されないことが通常です。
④降格
役職・職位・職能資格などを引き下げることをいいます。
なお、懲戒処分としての降格は、企業の人事権の行使(例えば営業成績や勤務成績不良を理由としての降格)ではなく、懲戒権の行使として行われるものをいいます。
⑤懲戒解雇
懲戒処分の中で、最も重い処分です。通常、解雇予告も予告手当の支払いもなく即時解雇されます。
また、退職金の全部または一部が支給されないこともあります。
もっとも、退職金には長年の功労に報いるという側面もあることから、退職金の不支給が有効となるためには、労働者のそれまでの勤続の功を抹消してしまうほどの著しく信義に反する行為があった場合に限られると考えられています(判例②を参照)。
判例①
「フジ興産事件」(最高裁判決 平成15年10月10日 労判861号5頁)
概要
Y社は、H市に本社をおくほか、I市に設計請負部門の業務場(以下「センター」という)を開設している。Xは、Y社に雇用され、センターにおいて設計業務に従事していた。
Y社は就業規則を作成し、H市労働基準監督署長に届け出た。なお、当該就業規則には、懲戒解雇事由が定められ、所定の事由があった場合に懲戒解雇をすることができる旨が定められていた。
Y社は、就業規則の懲戒解雇に関する規定を適用し、Xを懲戒解雇した。
その理由は、Xが得意先の担当者からの要望に十分に応じず、トラブルを発生させたり、上司の指示に対して反抗的態度をとり、上司に対して暴言を吐くなどして職場の秩序を乱したりしたなどというものであった。
そこで、Xは、当時のY社の代表取締役であったYらに対し、違法な懲戒解雇の決定に関与したとして損害賠償の支払を求め訴えを提起した。
これに対し原審は、センターにおいて本件就業規則の内容を周知させる手続がとられていた事実を認定せずに、就業規則に法的規範としての効力を肯定し、本件懲戒処分が有効であると判断した。
最高裁は、「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とした上で、「就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである」と判示し、原審を破棄し、センター勤務の労働者に周知させる手続の有無について更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻した。
判例②
「日音退職金請求事件」(東京地裁判決 平成18年1月25日 労判912号63頁)
概要
原告Xら9名は、音響設備の設計・施工及び管理業等を業としており、カラオケ設備の販売とレンタルを中心業務としているY社の従業員であった。
Y関連会社、H社の取締役であったAは、H社を退社し、Y社の競合会社であるI社を設立した。
Y社の全従業員の3分の1にあたる約500名がH社を退職し、I社に入社した。
原告Xら9名も、退職の意思表示をY社にした。
これに対しY社は、原告Xら9名のうち6名(以下「Xら6名」という)を懲戒解雇するとともに退職金について懲戒解雇のため支給除外とし、残りの3名についても退職金不支給事由に該当するとして退職金を支給しなかった。
そこで、Xら9名はY社に対し、退職金の支払いを求め訴えを提起した。
懲戒解雇されたXら6名の退職金請求について、東京地裁は、