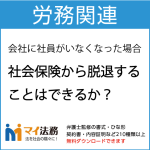会社の決算書を分析する、というと難しく感じるのですが具体的には何をどうすればいいのでしょうか?
【この記事の著者】江黒公認会計士事務所 公認会計士 江黒 崇史
http://www.eguro-cpa.com/
「分析」という言葉を「比較」に置き換えてみると、イメージしやすくなると思います。
そのうえで、まずは前期の数字と今期の数字を比較してみましょう。
決算書分析の第一歩とは
経営者のみなさんの中には、「会計」という言葉に苦手イメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
それなのに、「決算書」の分析をしなければいけないとなると、さらにハードルが一段高くなってしまうと感じてしまうかもしれません。
そこで、「分析」という言葉を「比較」という言葉に置き換えてみましょう。
経営者のみなさんにとってまず大事なことは、次の2点です。
・前期との「比較」
・予算と実績の「比較」
いきなり「決算書分析」と言われるよりも、「前期との比較」や「予算と実績の比較」と言われると、だいぶ馴染みやすいのではないでしょうか。
まずは比較すること!
これで決算書分析の大きな一歩を踏み出すことができるのです。
決算書の時系列比較とは
では、どう比較するか?
第一に、過去からの「時系列比較」を行ってください。
決算書について5期分、少なくとも3期分は時系列に並べて、過去の自社の経営状況や外部の経済環境と決算数値を見ていきましょう。
そうすることで、どのような時期にどのような決算だったのかがわかり、決算数値が分析できるようになると思います。
いきなり、決算書のすべての科目にこだわると全体を見失ってしまう恐れがありますので、まずは大きな「売上」や「利益」、「借入」や「現預金残高」の状況などから比較していってください。
全体の流れをつかんだら、次に「流動資産」と「流動負債」を比較する「流動比率」を算出したり、「自己資本」と「総資産」を比較する「自己資本比率」を算出したりして会社の財務の安全性を分析してみてください。
さらに、