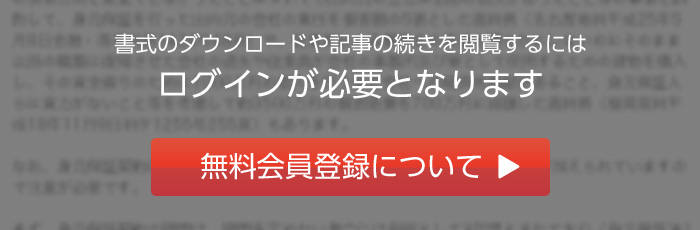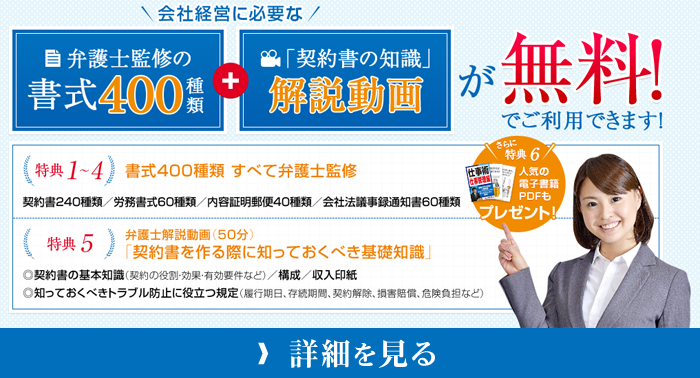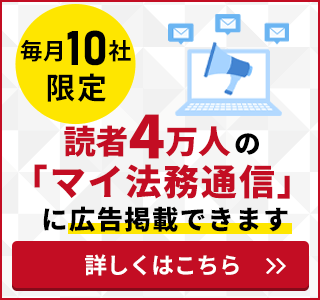目次
現行民法のルール
「時効」とは、ある状態が長期間続く場合に、権利関係をその状態に合わせることをいいます。
取得時効と消滅時効の2つがありますが、改正されたのは消滅時効のみです。「消滅時効」とは、権利を持っていても長期間行使しなければ、その権利がなくなるというものです。
人に何かをしてもらう権利のことを債権といいますが、債権の時効期間は10年とされています。いつから10年かというと、権利を行使できるときからです。
この「権利を行使できるとき」は時効期間の数え始めの時点になるため、「起算点」といいます。
たとえば、友人にお金を貸した場合、あなたは友人からお金を返してもらう権利を持っています。
しかし、返済期日を過ぎても返してくれない場合に、権利行使しないまま10年が経過するとお金を返してもらう権利がなくなります。
この例では返済期日から権利を行使できるため、返済期日から10年を数えます。
時効は当事者(債権者と債務者)の意思によらずに時間の経過にともなって進行します。
進行を止めるための制度として、中断と停止があります。
裁判を起こすなどの裁判所を通した手続を債権者が行ったり、借りていたお金の一部を返すなどの債務があることを前提とした行為を債務者が行ったりすると、進行していた時効がふりだしに戻ります。これが「中断」です。
債権者としては、時効が完成すると自分の持つ債権がなくなってしまうため、時効の進行を止めたいと考えます。
債権者が時効の中断をするためには、催告をするか裁判所の手続を利用する必要がありますが、もう少しで時効が完成するときに時効の中断をすることが難しい事情がある場合に時効の進行を止めるための制度として「停止」があります。
厳密にいうと、時効の進行を止めるのではなく、時効が完成する時点までは進行し、その後に完成が猶予される停止期間があるということになります。
停止にはいくつかのパターンがありますが、わかりやすい例として、天災による時効の停止があります。
変更点
(1)時効期間に主観的起算点を追加し、実質的に期間を短縮
現行民法では、債権の時効期間の起算点を「権利を行使できるときから」としていましたが、これを客観的起算点といいます。
権利を持っている債権者の主観、つまり、権利行使できることを債権者が知っているかどうかとは関係のない客観的な起算点です。
現行民法では、すべての債権の時効期間が10年だったわけではありません。
債権者の職業によって短期消滅時効が適用される債権があります。
飲食店の代金請求権はそのひとつであり、時効期間は1年です。
会社が行う取引などによって生じた商事債権には民法ではなく商法の規定が適用され、5年で時効消滅することになっていました。
一般の債権に適用される「権利を行使できるときから10年」という時効期間は、外国に比べて長すぎると批判されていました。
また、短期消滅時効が適用される債権や商事債権を一般の債権と分けて規定することは古い考え方によるものであり現代においては合理的な理由がないこと、債権の種類によって時効期間を変えることは複雑であり国民にとってわかりにくいことが指摘されていました。
改正民法は、債権の時効期間を「権利を行使できることを知ったときから5年」と「権利を行使できるときから10年」のどちらか早い方としました。
「権利を行使できることを知ったとき」は、債権者が権利行使できることを知っているかどうかを基準にしているため、主観的起算点といいます。
お金の貸し借りなどの契約によって生じる債権の場合で、特に返済期限を定めていない場合には、契約を結んだときに権利を行使できる時期を知っているため、「権利を行使できることを知ったときから5年」が適用されることになります。
つまり、「権利を行使できるときから10年」の時効期間の規定は現行民法から変わらず置かれているものの、改正後は「権利を行使できることを知ったときから5年」が適用されることが多くなると予想され、実質的に時効期間が短縮されたといえるのです。
適用される場面が少ないのであれば、「権利を行使できるときから10年」の規定は不要ではないかと思うかもしれません。
しかし、不法行為による損害賠償請求権などの契約以外から生じる債権は、権利を行使できることを知るのが遅れるため、「権利を行使できることを知ったときから5年」を経過していなくても「権利を行使できるときから10年」を経過することが考えられます。
そのため、「権利を行使できるときから10年」の規定を置いておく意味があります。
また、現行民法の短期消滅時効の規定、商法の商事債権の消滅時効の規定が削除され、改正前に短期消滅時効が適用されていた債権も商事債権も一般の債権と同じ時効期間になりました。
(2)協議をする旨の合意による時効の完成猶予を新設
現行民法の「中断」と「停止」の制度は、言葉どおりの意味ではないためわかりにくいと指摘されていました。
「中断」という言葉は、時効の進行が止まった後に再開すると誤解されがちです。
「停止」という言葉は、時効の進行が止まるという意味に思えますが、先に説明したとおり正確には進行が止まるわけではありません。
改正民法では、用語を実際の意味に近づけるために、「更新」と「完成猶予」に改めました。完成猶予のひとつとして、協議をする旨の合意が新設されたことが重要です。
現行民法の下では、当事者間の合意によって時効の進行を止める(または完成を猶予する)ことはできませんでしたが、改正民法ではそれができるようになりました。
債務者が話合いに応じてくれれば裁判を起こさなくても時効の完成を遅らせることが可能になったのです。
当事者間で、債権者が債務者に対して持っている債権についての協議をすることを合意したときは、原則として1年間は時効が完成しません。
協議で1年未満の期間を定めたときや当事者の一方が協議を続けることを拒絶した場合は1年経過前でも時効が完成します。
協議をする旨の合意は、電話など口頭で行うだけでは足りず、書面または電磁的記録で行わなければならないこととされています。
猶予期間中に再度合意を行うことで猶予期間を延長することもできますが、延長を繰り返しても当初の時効完成時点から5年を超えることはできません。
契約書への影響
(1)通常は契約書に時効期間に関する定めを置くことはありません。
消滅時効は、契約によって法律の規定と異なる定めをすることで変更できるものではないからです。そのため、契約書への影響はありません。
短期消滅時効が適用されていた債権については、債権があることの証拠となる契約書などの書類の保存期間が延長されます。
時効が完成するまでは債務者に対して債権があるという証拠を残しておく必要があるからです。
(2)通常は契約書に時効の中断や停止に関する定めを置くことはないため、契約書への影響はありません。
いつから適用になるか
消滅時効に関する改正民法は、施行日である2020年の4月1日から適用されます。
現行民法と改正民法のどちらが適用されるかは、債権がいつ発生したかによって決まります。
つまり、施行日前に発生した債権には現行民法が適用され、施行日以後に発生した債権には改正民法が適用されます。
契約日ではなく債権発生日が基準であるため、施行日前に結んだ契約によって施行日以後に債権が発生した場合は、改正民法が適用されることに注意しましょう。
協議をする旨の合意による時効の完成猶予については、合意をした日が基準となり、施行日前に合意をすれば現行民法、施行日以後に合意をすれば改正民法が適用されます。