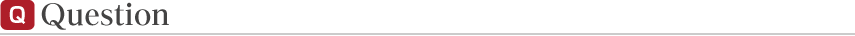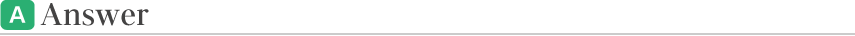いわゆる「年収の壁」対策により、国は配偶者手当の見直しを企業に求めているようですが、なぜ配偶者手当の見直しが「年収の壁」対策に関係あるのでしょうか。
また、見直す場合には、どのようなことに留意すべきでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
「配偶者手当」(あるいは「家族手当」や「扶養手当」などともいいます)は、その名のとおり、配偶者がいる社員に対して支給される手当であり、支給基準として「税法上の扶養親族に該当する者」あるいは「健康保険上の扶養親族に該当する者」としている場合が一般的です。
このように、年収が一定額を超えてしまうと企業の定める「配偶者手当」の支給基準から外れたり、税法上の扶養から外れることにより税負担が発生してしまうため、配偶者は年収が基準を超えないよう就労時間を調整するようになります。
一方、企業の人手不足は年々深刻度を増しており、国としても人手不足は喫緊の課題となっていることから、「年収の壁」対策の一つとして企業が「配偶者手当」を見直すことで配偶者に働き控えすることなく、より多くの時間就労してもらおうという狙いがあります。
同一労働同一賃金の導入の際にも「配偶者手当」の廃止・見直しが進んだように、「配偶者手当」支給する企業は減少しているところ、今回の対策でその傾向がさらに進んでいくことが予想されます。
では、「配偶者手当」を見直す場合、どのような点に留意しなければならないのでしょうか。
今回の「配偶者手当」の見直しにおいては、手当そのものを廃止・縮小したり、他の手当を増額する、あるいは全く新しい手当を創設することが考えられます。