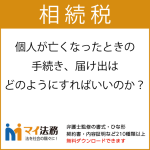役員報酬(役員給与)を損金算入するためには、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかの要件を満たさなければなりません。
定期同額給与は支給額だけでなく、支給時期も要件となっていますので、今回は役員報酬の定期同額給与が否認され、損金不算入となる事例を解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
年俸制による役員報酬の支給
定期同額給与は、1か月以下の一定期間ごとに支給する給与のうち、事業年度の各支給時期における支給額または、支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるものをいいます。
支給時期が1月以下の一定期間ごとの給与は、あらかじめ定められた支給基準に基づいて、月以下の期間(毎日、毎週、毎月)を単位として、規則的に反復または継続して支給されるものが対象です。
たとえば、非常勤役員に対して、年俸または事業年度の期間俸を年1回または年2回所定の時期に支給するような場合、支給額が各月ごとの一定の金額を基礎として算定されているものであったとしても、定期同額給与には該当しません。
ただし、非常勤役員に対する年俸または期間俸等の給与で、所定の時期に確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給するもののうち、次に掲げるものは事前確定届出給与に該当します。
- ・同族会社に該当しない法人が支給する給与
- ・同族会社が支給する給与で事前確定届出給与に関する届出書を納税地の所轄税務署に提出しているもの
役員に対する歩合給
役員に対する歩合給は、支給時期によって金額が変動することから、定期同額給与には当たらず、損金不算入となります。
定期同額給与は、支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であることが条件となっています。
したがって、役員報酬を一定の算定基準に基づいて規則的に反復または継続して支給している場合でも、支給額が同額でなければ定期同額給与には該当しません。
なお、役員に対して定期同額給与の要件を満たす固定給を支給している場合において、固定給と歩合給の部分があらかじめ明確になっているケースでは、固定給の部分は損金に算入することが認められます。
業績等の悪化による役員給与の減額が認められない場合
定期同額給与は、同じ額を継続的に支給することが要件となっているため、役員報酬の増額だけでなく、減額した場合も損金不算入となります。
ただし、法人の経営状況が著しく悪化した場合や、その他これに類する理由により行われた定期給与の改定については、損金算入が認められます。
「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなど、やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいます。
法人の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことを理由に減額した役員報酬は、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」には該当せず、損金不算入となるので注意してください。
役員報酬の改定が複数回
行われた際の取扱い
要件を満たす定期給与の額の改定があった場合、事業年度開始日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から、給与改定後の最初の支給時期の前日または事業年度終了日までの間の各支給時期における支給額が同額であれば、定期同額給与に該当します。
一方、同じ事業年度の期間中に複数回の改定が行われたときは、改定の前後で期間を区分し、各期間ごとに、その期間中の各支給時期において支給される定期給与の額が同額であるかを判定します。
たとえば、3月決算の法人(支給日は毎月20日)において、5月末に開催した定時株主総会で定期給与の改定を決議し、9月初旬の臨時株主総会で増額改定(臨時改定事由による改定に該当しない改定)を行った場合、次の①から③までに掲げる各支給時期における支給額が同額であるかを判断します。
①事業年度開始の日(4/1)から、定時株主総会による改定後の最初の支給時期の前日(6/19)までの期間
- ・支給時期 4月20日、5月20日
- ・役員報酬の額 40万円
②定時株主総会による改定前の最後の支給時期の翌日(5/21)から、臨時株主総会による改定後の最初の支給時期の前日(9/19)までの期間
- ・支給時期 6月20日、7月20日、8月20日
- ・役員報酬の額 50万円
③臨時株主総会による改定前の最後の支給時期の翌日(8/21)から、事業年度終了の日(3/31)までの期間
- ・支給時期 9月から翌3月までの各20日
- ・役員報酬の額 60万円