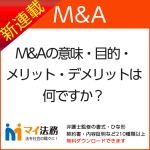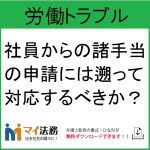中小企業の経営において、企業の財政状態を客観的に把握するには、貸借対照表が重要な手がかりとなります。
資産・負債・純資産の構成を分析することにより、経営の健全性や投資判断の材料を得ることが可能です。
本記事では、貸借対照表の読み取り方と構造分析の実務上のポイントについて解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
資産構成から読み解く企業の経営体質
資産は、企業がどのように収益活動を展開しているかを示す指標です。
資産構成比に着目することで、経営姿勢や潜在的なリスクを把握することができます。
資金運用傾向を示す流動資産・固定資産の構成比
貸借対照表における資産項目は、企業が調達した資金をどのように活用しているかを表しており、資産の構成比率を確認することで、企業が保守的か成長志向かといった資金運用の性格を読み取ることが可能です。
資産は、大きく「流動資産」と「固定資産」に分類されます。
流動資産(現預金、売掛金、在庫など)が多い企業は、資金の流動性が高く、短期運用を重視する傾向があります。
一方、固定資産(建物、機械、投資など)が多い企業は、将来的な収益獲得を見据えた長期投資型の経営スタイルと捉えられます。
在庫過多による資金滞留リスク
流動資産のうち、在庫が占める割合が過度に高い場合、資金の滞留や陳腐化リスクが懸念されます。
商品や原材料の購入・生産に投入された資金は、販売を通じて回収されるべきものですが、在庫として滞留すると資金が回収されず、キャッシュが減少します。
さらに、在庫過多に陥ると、倉庫費用や保険料などの在庫管理コストが増加し、陳腐化による価値低下も資金繰りを圧迫する要因となります。
このように、在庫の過剰保有はキャッシュフローの悪化につながるため、流動資産の中で棚卸資産が突出している場合には、販売効率や在庫回転率の検証が不可欠です。
特に、在庫の増加が売上高の伸びと連動していない場合は、過剰在庫による資金拘束の可能性が高まります。
設備投資型か身軽経営型かを見分ける視点
企業の資産構成を確認することで、その戦略や経営体質を俯瞰的に把握することが可能です。
固定資産の比率が高く、建物や機械類が多く計上されている企業は、設備投資型の傾向が強く、「資本集約型」の事業モデルであると推察されます。
一方、資産構成が軽く、外注や無形資産を中心に運営している企業は、「身軽経営型(アセットライト型)」と位置づけられ、環境変化への柔軟性が高いと評価されます。
近年では、感染症の流行を契機として、アセットライト型経営への関心が高まっています。
外部委託やリース調達の増加に伴う業務管理上のリスクも存在しますが、初期投資の抑制や財務リスクの軽減といったメリットがあるため、企業の事業特性に応じて検討すべき選択肢といえます。
負債構造から読み解く財務リスクと安定性
貸借対照表の負債項目は、企業が外部から調達した資金の性質や返済義務の内容を示します。
負債構造を適切に分析することで、短期的な支払リスクや長期的な財務安定性を把握することができます。
短期・長期の資金負担を示す負債構造
貸借対照表上の負債は、大きく「流動負債」と「固定負債」に区分されます。
流動負債は、1年以内に支払義務が生じる項目であり、買掛金や短期借入金などが該当します。
一方、固定負債は、1年以内に支払義務が発生しない、長期的な返済義務を伴う項目です。
社債や長期借入金などが固定負債に該当し、両者の比率を確認することで、企業の資金繰りにおける短期・長期のバランスや、財務運営の余裕度を判断する手がかりとなります。
加えて、固定負債の比率が高い場合は、長期的な資金負担に対する返済能力や、資金調達戦略の妥当性について検討が求められます。
借入依存度による財務健全性の見極め
企業がどの程度借入金に依存しているかは、財務の健全性を評価するうえで重要な指標です。
負債総額に対する借入金の比率が高い場合、返済負担が大きく、利息支払による利益圧迫が懸念されます。
一方、適度な借入れは、成長投資の原資となる可能性があるため、収益力とのバランスを踏まえて判断することが求められます。
支払能力とキャッシュフローの相関分析
流動負債の返済能力は、手元資金や営業キャッシュフローの状況に左右されます。
たとえば、流動比率や当座比率などの指標を用いて、短期負債に対してどれだけの資金的裏付けがあるかを検証することで、支払能力の安定性を判断できます。
キャッシュフローが弱い場合は、借入返済や仕入支払に支障をきたす恐れがあるので注意が必要です。