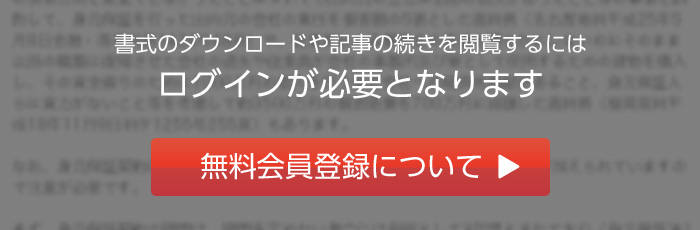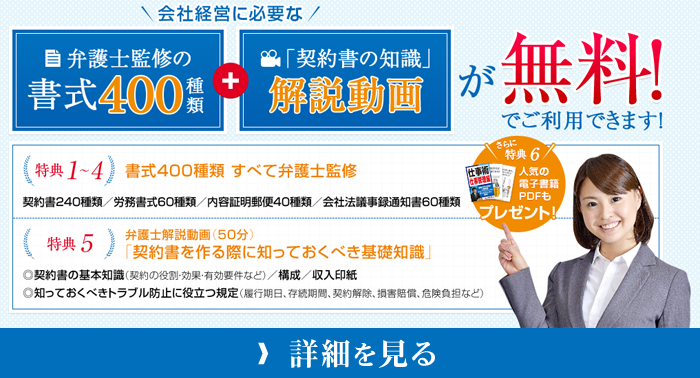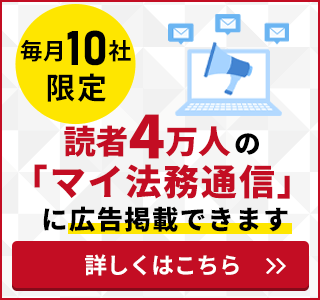相続税を節税するためには、基礎控除額や特例制度を活用することが重要です。
ただ、各制度には要件や制限などが設定されているため、制度内容を理解していないと、期待していた節税効果が得られないこともあります。
また過度な節税行為は、相続人間のトラブルにも繋がりますので、本記事では相続税対策の注意点をご説明します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
孫養子による基礎控除額の増額は1人までしか認められない
相続税の基礎控除額は、相続財産から直接控除できる金額で、法定相続人の人数が多いほど基礎控除額は増額します。
<相続税の基礎控除額の計算式>
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数 = 相続税の基礎控除額
被相続人(亡くなった人)の養子は、法定相続人に該当するため、たとえば孫を被相続人の養子にするだけで、基礎控除額を600万円増やすことも可能です。
ただ、相続税の基礎控除額の計算に含める養子の人数には上限があり、法定相続人に実子がいる場合には1人しか認められませんので、複数人の孫と養子縁組をしても節税効果は得られないです。
(法定相続人に実子がいない場合には2人まで)
一方で、多くの養子縁組をしている場合には、遺産分割協議に参加する相続人が多くなるため、話し合いの場を設けるのに苦労しますし、節税対策のための養子であっても、実子と同等の相続権が与えられているため、本来の相続人が取得できる相続財産が減少する可能性もあります。
また養子になった孫が相続した財産に対する相続税は2割増しになるという制度もあります。
配偶者の税額軽減は二次相続まで考えて利用すること
相続税の節税方法として有名なのが、『配偶者の税額軽減』です。
『配偶者の税額軽減』とは、配偶者の取得した財産が1億6千万円以下までなら相続税が課税されない制度で、配偶者が相続財産をすべて取得すれば、相続税をゼロにすることも可能です。
ただ、配偶者がすべての相続財産を取得すると、その配偶者が亡くなった際(二次相続)に支払う相続税が、多くなることも考えられます。
夫から妻の順番で相続が発生した場合、夫の相続時には妻が相続人として存在するため、配偶者の税額軽減を適用できます。
一方、妻の相続時には配偶者(夫)はいませんので、法定相続人は1人減少し、配偶者の税額軽減を適用できる人もいません。
(夫が亡くなった後に再婚していれば、後夫は配偶者の税額軽減を適用できます)
また夫の相続財産を妻がすべて相続した場合、妻の相続時に相続税の対象となる財産は、妻の財産と夫の財産の合計です。
相続税は、課税対象財産が多ければ税率が高くなる仕組みとなっているため、二次相続の際に多額の相続税を支払う可能性もあります。
小規模宅地等の特例は相続前3年以内に始めた事業には適用できない
小規模宅地等の特例は、土地の相続税評価額を50%または80%減額できる制度です。
たとえば不動産貸付用の土地は、相続税評価額を50%減額できる『貸付事業用宅地等』に該当します。
『貸付事業用宅地等』は貸付駐車場も適用対象となるため、空き地を貸付駐車場として利用し、相続税評価額を半分にする方法も節税手段としてあります。
ただ、相続開始前3年以内に貸し付けを始めた土地は、原則として『貸付事業用宅地等』を適用することはできません。
したがって『貸付事業用宅地等』を利用しての相続税対策は、長期的な計画に基づいて行う必要があります。
(相続開始前3年以内に貸し付けを開始した物件でも、特例が適用できるケースもあります。)
不動産の購入・売却には諸経費や税金の支払いが発生する
相続税は亡くなった時点の金額で計算しますが、土地は路線価方式により相続税評価額を算出します。
路線価方式により計算した相続税評価額は、時価の8割程度とされています。
そのため相続財産を預金から不動産に変更するだけで、時価よりも2割低い金額で、相続税を計算することが可能です。
ただ不動産を購入する際には、不動産仲介手数料や登録免許税・不動産取得税などの諸費用の支出が発生します。
また相続税の支払いは金銭で行いますので、預金の多くを不動産に変えてしまうと、相続税を支払う金銭が不足する可能性もあります。
相続発生以後に相続した不動産を売却し、その資金を相続税に充てることもできますが、売却時には、不動産の仲介手数料などのコストがかかります。
期待する節税効果よりも、相続税対策による支出額が多くなっては本末転倒ですので、ご注意ください。
中途半端な相続税対策はむしろ逆効果になる
相続税の基礎控除額や特例制度などを上手く利用すれば、相続税を抑えることも可能です。
ただ