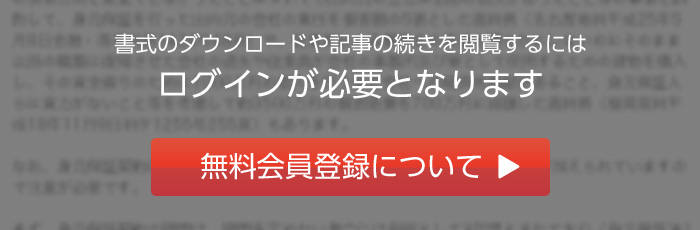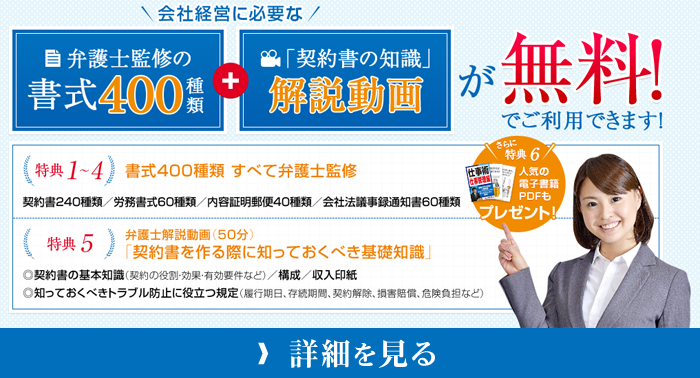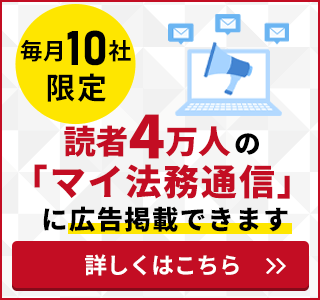小規模宅地等の特例は、相続税の中で節税効果が高い制度であることから、税務署は特例の適否について厳しくチェックします。
税務調査で適用誤りを指摘されれば、百万円単位で相続税が増える可能性もありますので、今回は小規模宅地等の特例を適用する際の注意点について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
小規模宅地等の特例の各制度に共通する注意事項
小規模宅地等の特例は特例対象地の種類によって限度面積や減額割合が異なるため、効果的に節税するためには特例を適用する土地選びも重要です。
特例対象地によって限度面積の計算方法は異なる
小規模宅地等の特例は要件を満たしていれば、複数の土地に対して適用することができますが、貸付事業用宅地等を適用するか否かによって限度面積が変わってきます。
貸付事業用宅地等を適用しない場合、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等および特定同族会社事業用宅地等の限度面積の計算は別々に決められています。
しかし、貸付事業用宅地等を適用するケースにおいては、限度面積を合算して計算することになるため、適用できる面積は小さくなる点に注意が必要です。
<小規模宅地等の特例の限度面積の計算式>
(適用する特例制度の種類)
【貸付事業用宅地等を適用しないケース】
①特定居住用宅地等
②特定事業用宅地等
③特定同族会社事業用宅地等
(限度面積の計算式)
A ①≦330㎡
B (②+③)≦400㎡
※限度面積はA+Bの合計730㎡
(適用する特例制度の種類)
【貸付事業用宅地等を適用するケース】
①特定居住用宅地等
②特定事業用宅地等
③特定同族会社事業用宅地等
④貸付事業用宅地等
(限度面積の計算式)
①×200/330 +(②+③)×200/400+④≦200㎡
特例対象地の選択変更ができないケースがある
小規模宅地等の特例を適用できる土地の面積が限度面積を超える場合、相続人が特例対象地を選ぶことになります。
特例を適用した土地が要件を満たしている場合、期限内であれば特例対象地を変更することは可能ですが、申告期限を過ぎてから特例を適用する土地の変更はできません。
ただし、特例対象地として選んだ土地が小規模宅地等の特例の要件を満たしていないときは、他の土地に対して小規模宅地等の特例を適用する変更は認められています。
特定居住用宅地等の適用誤りが起こりやすいポイント
特定居住用宅地等は、原則被相続人と同居していた親族が取得した際に適用する特例です。
同居人が自宅を相続し、申告期限まで所有していれば基本的に特例を受けることができますが、別居親族が特定居住用宅地等を適用するためには、以下の要件をすべて満たしていなければなりません。
<別居親族が特定居住用宅地等を適用する際の要件>
・特例対象地を相続開始時から相続税の申告期限まで保有している
・居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち、日本国籍を有しない者ではない
・相続開始の直前において、被相続人の自宅に同居相続人がいない
・相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の3親等内の親族または、取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがない
・相続開始時において、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがない
別居親族に対する特定居住用宅地等の適用は、土地を相続する人が持ち家を有していないことが要件となっていることから、「家なき子特例」と呼ばれることがあります。
家なき子特例は平成30年の税制改正で要件が厳しくなり、相続開始前3年以内に特例適用者の親族が所有する家屋に居住したことがある場合、特例は適用できませんのでご注意ください。
特定事業用宅地等の適用誤りが起こりやすいポイント
特定事業用宅地等は、被相続人の事業用として利用していた土地を引き継いでいた際に適用できる特例です。
被相続人の事業には、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業は除かれているため、被相続人が事業用として利用していた土地であったとしても、特定事業用宅地等を適用できないケースがあります。
不動産貸付業等の用途で利用していた土地については、貸付事業用宅地等の対象となりますが、貸付事業用宅地等を適用すると小規模宅地等の特例の限度面積が小さくなることから、特例対象地選びは重要です。
特定同族会社事業用宅地等の適用誤りが起こりやすいポイント
特定同族会社事業用宅地等は、相続開始の直前から相続税の申告期限まで、一定の法人の事業用として利用していた宅地等を引き継いだ相続人が適用できる制度です。
「一定の法人」とは、相続開始の直前において被相続人および、被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数(出資の総額)の50%超を有している場合における法人をいいます。
法人の事業用の範囲は特定事業用宅地等と同様、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業は含まれず、土地を取得する相続人は相続税の申告期限において、その法人の役員でなければいけません。