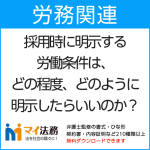近年、経理業務の自動化・効率化を目的としてデジタル技術の活用が進み、帳簿書類を紙ではなく電子データとして保存する企業が増えています。
一方で、帳簿書類のデジタル化に伴い、税務調査における書類確認の方法も変化しており、適切な管理が求められます。
本記事では、経理のデジタル化が税務調査に及ぼす影響と、適切な対応方法について解説します。
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
電子帳簿の保存方法と注意点
帳簿書類を電子データで保存するには、真実性(改ざん防止)と可視性(検索性)の要件を満たす必要があります。
保存要件を満たしていない場合、税務調査で指摘される可能性があるため、適切な管理が求められます。
従来、帳簿書類は紙で保存することが原則でしたが、平成10年(1998年)に電子帳簿保存法が制定され、電子データによる保存も認められるようになりました。
電子帳簿保存法の制定当初は保存要件が厳しく、紙で保存するのが一般的でした。
しかし、複数回の改正を経て要件が緩和され、現在では一般の企業や個人事業主でも帳簿書類を電子データとして保存しやすくなっています。
電子取引データの保存要件
注文書や契約書、請求書などを電子データとして受領または交付する場合、電子取引データ保存の要件を満たすことが求められます。
改ざん防止の措置
原則として電子取引データを保存するためには、以下のいずれかの改ざん防止措置を講じる必要があります。
- ・タイムスタンプが付与されたデータを授受
- ・受領したデータにタイムスタンプを付与
- ・訂正・削除の履歴が残るシステム等でデータを授受・保存
- ・改ざん防止のための事務処理規程を策定・運用・備付け
ディスプレイ・プリンタの備え付け
帳簿書類を電子データとして保存する場合、税務調査等において電子取引データを確認できるよう、ディスプレイやプリンタの備え付けが必要です。
なお、ディスプレイやプリンタの性能や、設置台数に関する要件はありません。
検索機能の具備
電子データは、「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つの記録項目で検索できる必要があります。
検索方法としては、取引年月日または取引金額の項目について範囲指定ができる「範囲指定検索」と、2つ以上の記録項目を組み合わせて検索できる「組合せ検索」があり、いずれかの方法で検索できる仕組みを整えることが求められます。
ただし、範囲指定または組合せ検索ができない場合でも、税務調査等の際にダウンロードの求めに応じることができれば、要件を満たしているとみなされます。
また、検索機能を備えていない場合でも、以下のいずれかに該当するときは、ダウンロードの求めに応じることで要件を満たすことが可能です。
- ・基準期間(2年[期]前)の売上高が5,000万円以下
- ・電子取引データを出力した書面を、取引年月日および取引先ごとに整理し、提示・提出できる状態にしている