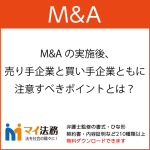最近「働き方改革関連法案」が成立したようですが、社員の労働時間を客観的に把握するよう企業に義務付けることになったと知りました。
しかし、もともと出勤簿をつける等の方法により、労働時間を把握しなければならなかったのではないのでしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
ご指摘のとおり、労働者の労働時間を把握することは、法改正以前から使用者(企業)に義務付けられていました。
ところが、労働時間については労働者の自己申告制により把握しているケースが多く、結果として不適切な運用により未払い賃金や長時間労働の諸問題が発生していました。
つまり、適切な労働時間の管理ができているとはいえない状況にあったわけです。
また過去には、厚生労働省が出した「平成13年4月6日の通達」や、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)などで、労働時間をタイムカード等で確認し、記録する等「客観的」に把握するよう規定していたものの、ここでいう労働者に「管理監督者」や「みなし労働時間制が適用される労働者」は含まれていませんでした。
管理監督者は、深夜の割増賃金を支払う可能性はあるものの、通常の時間外や休日労働については支給対象外です。
「みなし労働時間制」も、所定労働時間や労使協定で予め定められた「みなし労働時間」に基づき割増賃金を支払います。
そのため、いずれも「客観的に労働時間を把握する必要はない」として除外されたのです。
【関連記事】所定労働時間の計算方法とは?
今回の改正では、これを改め、「労働時間の状況を省令で定める方法により把握することを原則とする」という方向で進んでいましたが、最終的には法律で義務付けられる=条文化されることで落ち着きました。
過去の通達は、主に割増賃金を適正に支払うことを目的としていましたが、改正後は「健康管理の観点」から、管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者も含めて、客観的方法により労働時間を把握しなければなりません。
適切な方法により労働時間を把握することができれば、今まで把握されていなかった「かくれ労働時間」が明らかになるでしょう。
そして、