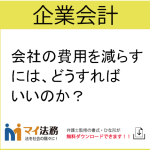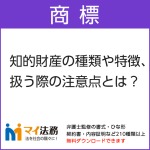先日、ある社員から「パワハラを受けているので相談に乗ってほしい」と言われました。
これまで考えたこともありませんでしたが、このような場合の対応として適切な方法があれば教えて下さい。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
パワハラの相談内容によっては対応の仕方が変わることもありますので、ここでは一般的な対応例を挙げてみたいと思います。
相談者との面談を行なう場合
例えば「本当にパワハラなの?」などと偏見を持ったりせず、真摯に相手の話を聴く必要があります。
偏見や外見での判断は「セカンドハラスメント」といって、相手に対する更なるハラスメントにつながる恐れがあります。
プライバシーが確保できる場所(個室)を用意するとともに、秘密を厳守する旨を伝えるべきでしょう。
なお、相談時間は1時間以内が適切です。
事実関係を確認する場合
パワハラ行為が疑われる者(行為者)へのヒアリングや、第三者に対するヒアリングを行なう場合は、必ず事前に相談者の了解を取ってから行なわなければなりません。
また、第三者へのヒアリングは1人だけでなく、複数人にあたるべきでしょう。
事実関係の確認においては、調査目的を明確に伝えるとともに、ヒアリング対象者の人格を尊重することに留意しましょう。
パワハラの可能性が極めて高い場合でも、行為者に弁明の機会を与えるべきです。
それとともに、相談者への報復が行なわれないよう十分な指導が必要です。
調査の結果、対応を検討する場合
パワハラ行為があったと認定した場合は、行為者に対する処分を検討しなければなりません。
懲戒とする場合は行為の内容と程度に従い、就業規則の「譴責」「減給」「降格」「懲戒解雇」処分などにします。
行為者を処分しても、例えば当事者が同じ部署でそのまま勤務を続けた場合は、将来またパワハラが起きるかもしれません。
従って、どちらか一方あるいは両名の配置転換をしなければならないこともあるでしょう。
相談者及び行為者に対するフォロー
パワハラがあったと認定されたのならば、行為者が相談者に謝罪できるような環境整備をしなければなりません。
相談者に対してはメンタル面でのケアが必要となる場合もあります。
再発防止策について
パワハラが再び行なわれないように、会社は再発防止策を講じなければなりません。
厚生労働省の調査によれば、パワハラの予防効果として最も効果的な取組は「講演・研修の実施」だそうです。
以上が相談から対応までの流れですが、相談を受けた場合は放置せず、迅速な対応が重要であることを最後に付け加えておきます。