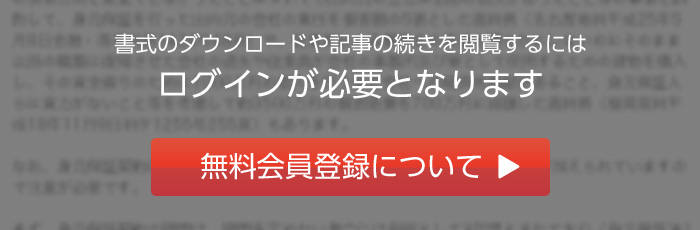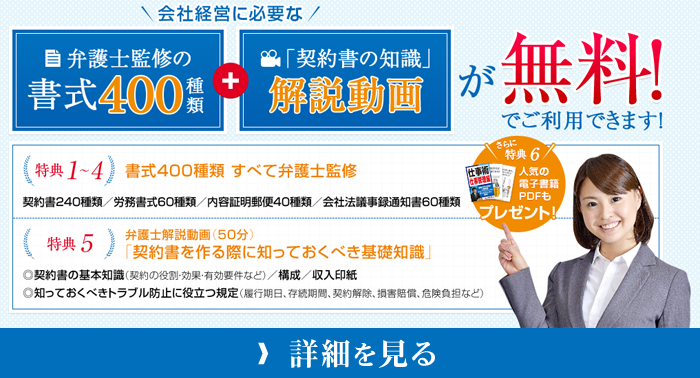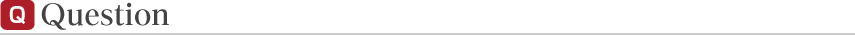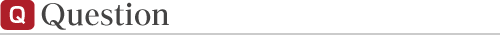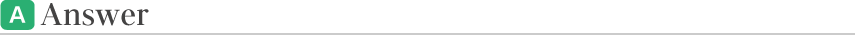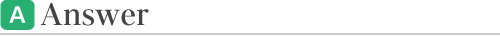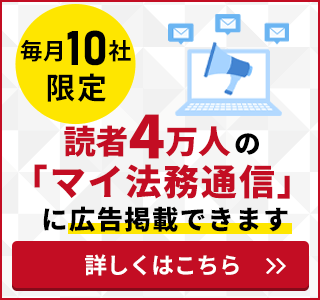労働審判制度とは何ですか?裁判との違いがよくわかりません。
また会社として注意すべき点は、どのような点ですか?
解説
2006(平成18)年4月から始まった労働審判制度は、年々件数が増加していて平成22年度は3,375件の申立てがなされています。
その約80%は、調停の成立または労働審判の確定により訴訟に移行せずに終了しています。
平成22年に終結した労働審判事件の平均審理期間は2.4ヵ月で、同年の労働関係民事訴訟の平均審理期間の11.5ヵ月と比べると、かなり迅速な審理が行われているのがわかります。
扱う案件は個別労使紛争全般です。民間の労使の専門家である2名の審判員が審理に加わり、より紛争の実情に即した実効的な解決を図ります。
たとえば、解雇における訴訟の場合、和解が成立しない限り、裁判所は労働者が雇用契約上の地位を有するかどうかという点について判決を下すしかなく、雇用契約を終了させて金銭での解決を図るという解決はできません。
これに対して労働審判の場合、労働者が仕事復帰にこだわっておらず、金銭的な解決を望んでいるならば、仮に解雇が無効であると判断した場合でも解雇を無効として復職させるのではなく、雇用契約を終了させて解決金の支払いを命じる審判を下すといった柔軟な解決を図ることができます。
労働審判は、当事者本人が申し立て、審判当日に出席することもできますが、代理人に任せることもできます。
その際、代理人は原則として弁護士でなければならないとされています。労働審判では短期間に集中的な審理が行われるため、限られた時間で主張・立証を的確に行い、調停などに対応しなければならないため、対応を弁護士に委任することが望ましいからです。
労働審判手続きが申し立てられた場合、40日以内の日に第一回期日が指定され、第一回期日の1週間または10日前までに答弁書と証拠書類の提出を求められます。
通常、第1回期日で事実関係の審理は終了し、すぐさま調停の試みがされます。
そのため、企業は短期間で関係者からの事情聴取や事実関係の調査、証拠の収集などを行い、かつ自己の主張をまとめておきつつ調停への対応策や方針を検討していかなければなりません。
また当日は、労働者側の言い分に的確に反論し、こちらの言い分を裏付ける事情を伝えていかなければいけません。
以上のことを考えれば、申し立てがなされた場合には直ちに事件を弁護士に委任し、準備を進めていくことが重要でしょう。
労働審判とは、企業と個々の労働者との間の個別労働関係民事紛争について調停による解決をあっせんし、調停が成立しない場合には労働審判を行うという手続きです。
たとえば、不当解雇や賃金・残業代の未払いなどに関して、裁判官1名と民間人の労使の専門家である労働審判員2名とで構成された労働審判委員会が審理をし、事案の実情に即した解決を行います。原則として3回以内の期日で審理が終結されます。